マタギにとって、獲物の風下に位置を取るには風の変化を慎重に読まなければならない。
都会のマタギは長時間の燻製をするときには隣家ではなく、崖の方向に流れる風が続いてほしいと念じながら桜の枝に火をつける。
そして風を見るためには、煙や、雨や霧といった流れゆくものが必要だ。
私は庭や畑の中で流される雨を見て、風を感じるのが習慣になっている。
田舎に行って流れる朝霧を見ていては風を見た気になっていた。
雨や霧ではなく、風を見ていると言い聞かせていた。
果たして自分には本当に風が見えているのだろうか?
ここのところ、そのことが気になっていた。

流される煙といえば最近「炭」について考えさせられることが多い。
先月、和歌山県すさみ町のツアーで再訪した備長炭の窯は後継者がいない状況に変わりはなく、生産量が減っていくのではないかと心配になった。先週開いた我が家のガーデンパーティーで使った「岩手のくぬぎの切り炭」も近くの大型店からは姿を消し、それらの棚は東南アジアのマングローブ産の炭や、おがくず入りの固形燃料に取って代わった。
近くの馴染みの肉屋のおやじが選んでくれた、とっておきの鶏肉を焼きながら、炭の煙の香りをつけるには ‘バーベキュー’ の世界ではない炭が欲しいのだが、と思う。
そんな中、能登半島の珠洲市で炭焼きの再建を図る若者から、クラウドファンディングの返礼品として、お茶会で使う切り炭が届いた。お茶をするワイフの目にかなった高品質の炭。能登半島のクヌギでできる姿は美しかった。

東日本震災前、我が家のお茶の炭は福島県産だった。放射能の風評被害からその製品がなくなり、福島の炭窯は今どうなっているのかわからない。
その意味で風評被害のない能登半島には希望を持てるのではないか?
クラウドファンディングをやったノトハハソのホームページから:
能登半島の里山のなかにある珠洲市の東山中集落。
株式会社ノトハハソは、東山中で周辺の里山に炭材となるクヌギの木を植え、昔ながらの手仕事で炭を焼いています。
古来日本人はコナラやクヌギという広葉樹の森を薪や炭に使ってきました。
秋に伐られた木の切株に翌春にはひこばえと呼ばれる新芽が出て、数年経つとまた、伐ることが出来ます。
人は繰り返し自然の恵みをもたらしてくれる森を柞(ははそ)と呼び大切に守りつないできました。
株式会社ノトハハソでは、柞の森の恵みを活かし、炭製品を通じて持続可能なライフスタイルを提供します。
生命を繋ぐこと。
人と自然の恵みに感謝して生きていくこと。
現代の人々が忘れてしまわぬよう時をかけて山を育てていく。
時をかけて炭を育てていく。
ひとつひとつの仕事が未来に繋がっていく。
そんな生業と仲間たちと共に生きていきたい。
株式会社ノトハハソ
代表取締役 大野 長一郎
大野さんが凄いのは、今後の地震に備えて窯の開発を耐震設計からやっていることだ。
時間がかかっても自分たちの信念を実現する。それは震災前に戻すのではなく「創造的な復興」だ。
森と炭焼きを循環型で営んでゆく、ビジョンのある炭焼きを目指す世代を後押ししてみたい。
やがて訪れる珠洲市の遠くの山に、炭焼きの煙が風に流されていく。
その煙を生み出すところで、確かに「風は見える」のだ。
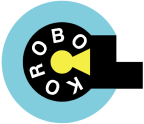



コメント