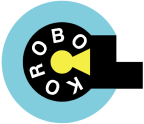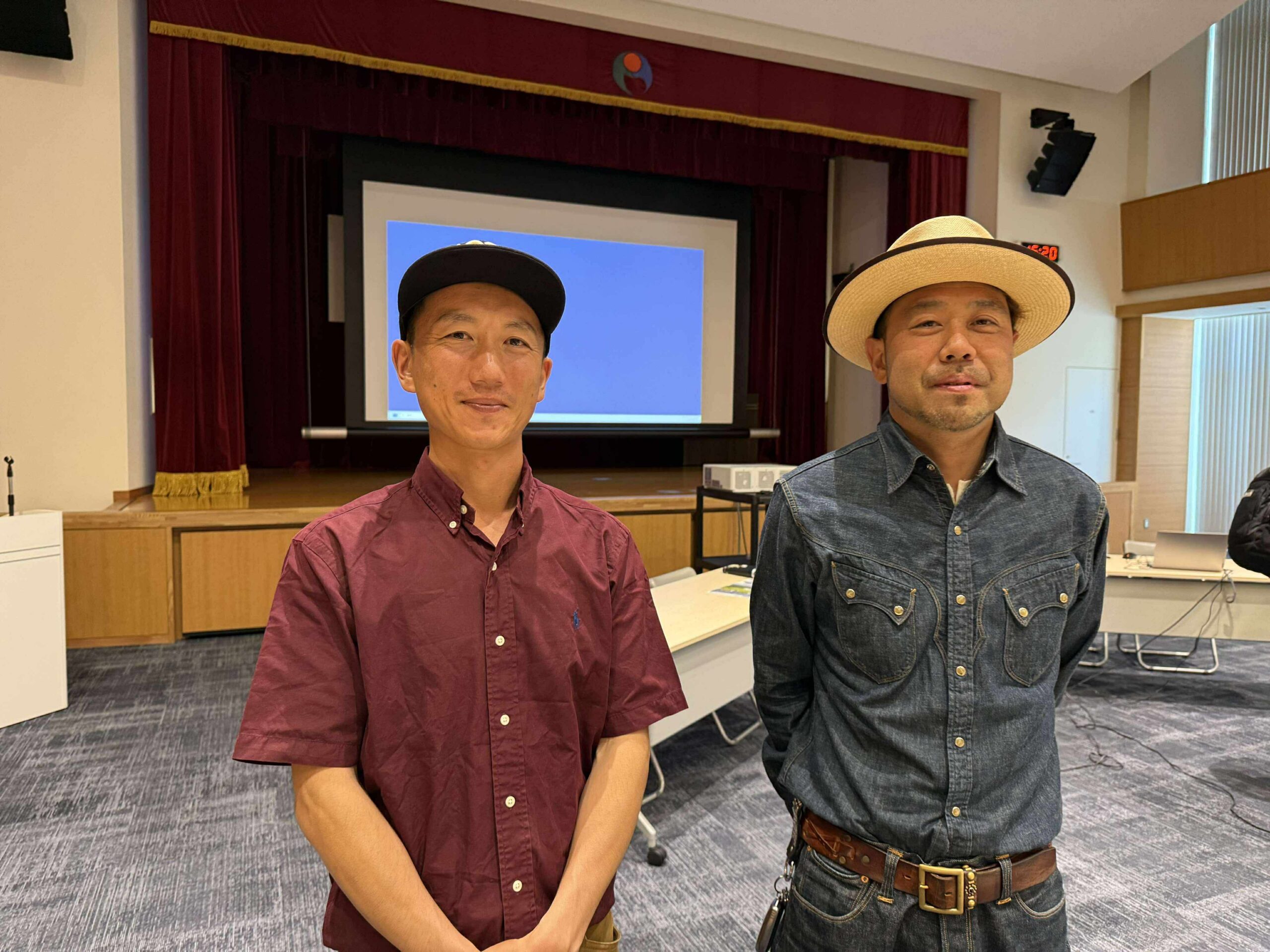講師:原田 英男 「再び、牛と興す、能登。」(元農林水産省畜産部長、元一般財団法人畜産環境整備機構副理事長、前宮崎こばやし熱中小学校校長)
ゲストスピーカー:平林 将さん「能登牛かわいいよ能登牛」(能登牧場専務)
ゲストスピーカー:西出 穣さん「能登らしい酪農の復興とは」(西出牧場代表)
2025年7月12日 能登町役場 大会議室にて
能登半島を襲った未曽有の地震は、地域の基幹産業である畜産業にも甚大な被害をもたらしました。しかしこの困難な状況の中、「牛で起こす能登」という力強いビジョンのもと、畜産農家と識者が一体となり、単なる復旧に留まらない、未来を見据えた「復興」への道筋を模索しています。能登熱中授業での発表は、その現状と展望を浮き彫りにしました。この授業は、大人のための教育実践を行う「熱中小学校」の一環として、宮崎県の小林熱中小学校校長を務めた原田先生が能登町の役場を借りて実施しました。
災害が突きつける畜産の現実と「牛」の可能性(原田先生)

農林省で畜産部長を務めた経験を持つ原田先生は、地震のような災害が畜産農家にもたらす過酷な現実を指摘します。家畜は生き物であり、一日たりとも餌や水、手入れを欠かすことはできません。停電、断水、道路寸断は、餌の運搬や搾乳、水の供給を妨げ、牛舎や施設の被害と相まって計り知れない苦労を生み出します。特に乳牛は、毎日搾乳しないと病気になるデリケートな動物であり、絞ったミルクを捨てざるを得ない状況も発生します。また、肉牛もストレスが肉質に大きく影響するため、災害時のストレスは深刻な問題となります。
しかし原田先生は、こうした困難を乗り越える「牛の力」に注目しました。能登の「里山」は、人の手が加わることで維持されてきた自然であり、牛はその中で大切な役割を担ってきました。単に肉や乳製品を生産するだけでなく、牛が出す堆肥は他の農作物の循環を促し、耕作放棄地で草を食べることで雑草や灌木の発生を抑え、里山の景観維持にも貢献します。これはまさに「牛で起こす能登」の多面的な意味を示しており、能登の豊かな自然と共生する農業のあり方を提示しています。
原田先生は、他の地域の成功事例を挙げながら能登での牛の活用可能性を示唆しました。例えば山口県では、人の背丈ほどに雑草が生い茂った耕作放棄地が和牛の放牧によってきれいな田んぼに戻り、子どもたちの通学路にもなることで地域に活気をもたらしています。栃木県の瀬尾ファームでは、自衛官を辞めて畜産を始めた方が、水田やタバコ畑だった場所を放牧地にし、ねむの木の木陰で牛が休む美しい景観を作り出しています。宮崎県では、だんだん畑だった森を自ら伐採し、牛の放牧地として再生した事例も紹介されました。能登は冬の積雪があるため通年の放牧は難しいかもしれませんが、冬の間は牛舎で飼育し、それ以外の期間で放牧を行うなど、工夫次第で同様の取り組みが可能だと提案しています。
また乳製品についても、国産ナチュラルチーズの可能性を強く打ち出しました。全国には300ほどの小規模な工房があり、酪農家が自らの牛乳でチーズを作るケースや、レストランがチーズを作るケース、あるいは牛を飼わずともミルクを仕入れてチーズを作るケースなど多様な形態があります。能登には豊かな発酵文化があり海産物も豊富であることから、例えば能登特産のイカを使った「イカ入りチーズ」のような、その地域ならではの特色あるチーズ開発ができるのではないかと具体例を提示しました。チーズは牛乳の1/10に圧縮されるため輸送にも有利で、牛乳以上の付加価値を生み出すことができます。
「牛が起こす能登」というテーマは、単に美味しい肉や乳製品を生産するだけでなく、能登の里山を残し、農業を良くするために牛の存在が能登の復興の柱になるという強い思いが込められています。
震災の現場から見た「復旧」と「復興」のリアル(平林 将氏)

能登牧場の平林将氏は、震災直後の牧場の壮絶な状況を語りました。2024年1月1日16時10分、元旦のその時、牧場では「地面が揺れ始め、いつまで経っても収まらず、立っていられない地震だった」と振り返ります。地震直後から停電と道路寸断に見舞われ、牧場へ繋がる山道は一部崩落し、寸断状態となりました。
牧場の牛舎は、4つのうち1号、2号、3号舎が一部損壊、4号舎は全壊判定を受けました。特に、牛舎の柱に走る深い垂直の亀裂や、幅約8mの重量シャッターが落下した様子は、地震の破壊力を物語っています。
最も深刻だったのは牛たちへの水供給でした。能登牧場では地下水を組み上げているため、停電すると電気モーターが動かず、水が出ません。牛は一日20リットル以上の水を必要とするので、水が飲めないことが最大のストレスとなります。地震直後から牛たちが水を欲しがって鳴き続ける動画は、その過酷な状況を雄弁に示していました。スタッフは、残っていた大きなタンクから水を汲み出し、ウォーターサーバーの6リットルボトルに入れ替え、フォークリフトで牛舎に運び込み、餌をどかして水を与える作業を一日中行いました。この作業は1つの牛舎につき1日2回が限界でした。平林氏は 「運が良いことに」1月は例年よりも暖かく、気温7〜8度の温暖な日が続いたため、溶けた雪や雨水を溜めてなんとか凌ぐことができたと語りました。
停電は1月9日17時頃にようやく復旧し、牧場に設置された自動販売機の明かりが灯った時には感動を覚えたと言います。スタッフとぬるいコーラで乾杯した思い出は、過酷な日々の中での小さな喜びでした。しかし電気復旧後に判明したのは、地盤沈下で牛舎が傾き、水道配管が破断していたことでした。水道管の修繕には丸一日かかり、牧場全体に水が行き渡るまでにはさらに1日半を要しました。この間にも、弱っていた牛が死んだり、水を取り合って角が折れる牛もいたといいます。
復旧作業は3月中旬まで続き、落下した換気扇の修理など、スタッフ総出で応急処置を行いました。本来は専門業者に依頼すべき作業ですが、業者も被災者であるため、来てもらうことが困難だったためです。手動で開けるのに30分かかる重いシャッターを、毎日交代で開け閉めした苦労も明かされました。
能登牧場は、2024年9月に全壊した4号舎の再建を開始する予定でしたが、すでに2ヶ月遅れており、完成は2025年11月、最終的な修繕と増頭による1440頭体制の完了は2027年9月頃になる見込みです。
平林氏は、この経験から「復旧」と「復興」の言葉の重みを改めて問いかけます。
- 「復旧」とは、傷んだり壊れたりしたものを元通りにすること。
- 「復興」とは、一度衰えたり壊れたりしたものが再び盛んになり、より良い状態に地域社会全体を立て直すこと。 そして 「現状は、復興なんか全然進んでいないのです。まだ復旧ですら進んでいない状況なのです」と力強く訴えました。能登牧場が震災前の1050頭から現在897頭に減少し、将来的に1440頭体制を目指すのは、牧場としては「復興」にあたると言えるが、それだけが復興しても意味があるんでしょうか」と問いかけます。
能登牧場では、アニマルウェルフェアを重視し、オスは30ヶ月以上、メスは34ヶ月以上(平均40ヶ月、最長48.9ヶ月)の長期肥育を行うことで、きめ細やかな肉質と上質なオレイン酸を特徴とする能登牛を育てています。日本の出荷月齢平均が28ヶ月である中で、長期肥育は大きな挑戦です。これは能登の、涼しく、空気や水の綺麗な環境が牛のストレスを軽減し、長期肥育を可能にしているためだと平林氏は語ります。しかし、長期肥育はコストがかかり、肥育期間が長すぎると体が大きくなりすぎる問題もあるため、30ヶ月という基準を設定しています。オレイン酸は30ヶ月までに体内に蓄積される特性があるため、この期間が重要です。オレイン酸の数値は牛が肉になった後に測定され、特定の餌や遺伝的要素によって高める努力をしています。
しかし、同氏が最も強調したのは、能登全体の復興のためには「自社牧場だけが復興しても意味がない」という点です。震災前から続く人口減少、特に30代と0~5歳の若い世代の流出は深刻であり、もはや農業・畜産単独の「自助努力だけでは限界が来ている」と危機感を募らせます。
そこで平林氏が提案するのが、「他産業との連携(クロスインダストリーコラボレーション)」です。
- 料理人:能登の食材を使ったフルコース料理の開発
- 塾経営者:静かで集中できる能登での受験生合宿。携帯電話の電波が良くないことが集中できる環境になるという逆転の発想
- 人狼ゲーム、サバイバルゲーム:能登には閉鎖された廃校が多く、これらを活用してユニークな体験を提供
- ドローン:空が開けている場所が多く、ドローンレースの開催
これらは都会ではできない能登ならではの価値を創出するアイデアであり、農業生産者としても何らかの形で関わりたいと述べています。学生や研究者に対しては、単なる手伝いではなく儲かる話や具体的な研究計画を持ってくるよう、厳しいながらも本質的な期待を表明し、牛が能登の復興に役立つ新たなモデルを構築したいと締めくくりました。牧場見学は家畜防疫法の規制があるため難しいが、オンラインツアーや、料理人などと共に能登牛の美味しさを伝える活動を通じて価値向上を目指したいと語っています。
能登らしい酪農復興の理想像(西出 穣氏)

西出牧場の西出穣氏は、自身も震災で搾乳舎の損壊や給水困難、牛乳の廃棄といった大きな被害を受けながらも、酪農家としての視点から能登の復興を語りました。西出牧場は、祖父が1956年に旧全市(現白山市)で創業し、父の代に能登町に移転してきました。現在は搾乳牛約30頭を飼育し、牧草地で取れる自給飼料でほぼ全ての餌を賄っているのが特徴です。
震災後、奥能登の酪農家はすでに2戸が離農し、牛乳の出荷量も激減している現状をグラフで示しました。震災前と比較して、震災直後の牛乳出荷量は約25%にまで落ち込み、その後も75〜80%程度で頭打ちになっていると指摘。その理由として、震災と地域で約300頭もの牛が減少していることを挙げました。これは、石川県内の子どもたちに県産の牛乳を届けられなくなるだけでなく、酪農を支える関連産業(飼料メーカー、ヘルパー、獣医、運送会社など)の雇用にも影響が及び、地域全体の人口流出を加速させかねないという危機感を共有しました。
西出氏は、生産量を増やすために新規就農者を呼び込むことや、既存の酪農家の増産、または個体乳量の向上といった努力が必要だと述べます。その上で、彼が譲れないのは「能登の農地で育てる自給飼料を牛に与えること」です。能登の酪農家はもともと自給飼料生産の割合が高く、輸入飼料価格高騰の影響を受けにくい安定した経営が可能な地域であり、9戸中7戸が30代・40代と若い世代が経営を担っているという特徴もあります。
西出氏の考える能登らしい酪農復興の理想は、大規模なメガファームではなく「能登の各地に家族経営の酪農家が分散して存在すること」です。これにより、それぞれの牧場が周囲の牧草地で飼育できる頭数の牛を飼い、地域の景観維持にも貢献しながら、能登全体に酪農の営みが広がることを望んでいます。この形こそが、消費者や乳業者が能登の牛乳に求めるものではないかと力説します。耕作放棄地を飼料畑として活用するなど、地域に根差した耕畜連携の取り組みも重要だと考えています。しかし、能登半島に広く分布する牧草地を効率的に管理するコントラクター組織の設立や、人口減少・人手不足の中での運営には課題も多いと認識しています。
さらに、復興計画を立てる際には、酪農家だけでなく、牛乳を届ける乳業者、販売店、そして牛乳を使って商品を作るシェフやパティシエなど、多様なステークホルダー(関係者)の声を聞き、彼らがどんな牛乳を求めているのか、どのようなストーリーのある牛乳が欲しいのかを理解した上で進めるべきだと提言しました。単に生産量を増やすだけでなく、消費者や関連産業が求める価値に合致した酪農のあり方を追求することが、能登の酪農の未来を切り開くと考えています。
復旧から復興へ、能登の未来を拓くために
三者の発表を通じて共通して見えてきたのは、震災からの道のりがまだ「復旧」の途上にあり、単なる元通りにするだけでは能登の未来は開けないという切迫した認識です。人口減少と高齢化が加速する中、「震災は能登のトレンドを加速する」という言葉が示すように、従来の農業・畜産といった自力の産業だけでは限界があり、地域を越え、産業を越えた連携といった今までにない新たなアイデアが不可欠であると訴えかけます。
「牛で起こす能登」というテーマは、単に畜産を再建するだけでなく、牛の力を借りて耕作放棄地を維持し、里山の豊かな景観を守り、食を通じた観光の目玉を創出し、そして何よりも地域に新たな人の流れと活力を生み出す、能登全体のより良い復興を目指す壮大な挑戦です。それは、ハードルの高い課題ではありますが、能登の畜産農家は、それを実現するための情熱と具体的なアイデアを持っています。
登壇者たちは、能登に興味を持った人々に、ぜひ一度現地に足を運び、能登の美味しいものを食べて応援してほしいと呼びかけます。それは復興への最も直接的な支援であり、能登の畜産業、そして地域全体が、この困難を乗り越え、持続可能で魅力的な未来を築き上げていくための、力強い一歩となるでしょう。