2025年5月18日、輪島市で開催された第4回「のと復興音楽ツアー」は、輪島和太鼓・虎之介、輪島高州太鼓の皆様と「天地人」との共演だった。会場は輪島中学校体育館。地震発生後、輪島市では100か所以上の避難所が開設されたが、中でも輪島中学校体育館は頑丈でまた大きな場所であることから最大限利用されてきた場所だ。
午後1時の開場前から観客が詰めかけて開演時には約300人となった。
演奏は、第1部が輪島高州太鼓、第2部は輪島和太鼓・虎之介、第3部 が「天地人」 、第4部は合奏となった。大きな体育館に静かな熱気があふれてくる。太鼓の音と拍手が体育館の天井に響く。


地震、水害の被害が深刻な輪島市では、4校合併時に建てたこの体育館が唯一演奏ができる場所であった。輪島高州太鼓は子から親に引き継がれている伝統の技を披露。
輪島和太鼓・虎之介は全国のジュニアの大会で優勝経験があり、常に革新的な演奏を行ってきた。「天地人」の大間ジローさんに「輪島の太鼓は噂には聞いていたが、これほど素晴らしい演奏とは感激しました」と言わせるものだった。
輪島の太鼓チームは能登の太鼓のリーダー格として、日本各地から呼ばれる機会も多い。 抜けたメンバーもいる中、「能登は元気だ」と知ってもらいたいと、極力そうした機会には応えているという。そうした姿を輪島市民は知っていて、久しぶりに地元の皆さんが高州太鼓の元気な姿を確かめる場、という雰囲気だった。誰もが熱演をじっと聞きながら自分自身と対話しているような、そんな厳粛な時間の様だった。


輪島市の演奏を聴いた後しばらくして、8月に、まきりかさんの「のと熱中授業」、―「祭りが、日本を救う。」 〜能登にこそ、地域課題解決の「ひな型」があった〜 を聞いた。2025年6月と7月の二度にわたり能登を訪れ、その目で見て、肌で感じたことを伝えるまきさんのお話を聞きながら、輪島の太鼓のことを思い出していた。
「祭りが日本を救う。2ヶ月取材をして、本当に思ったのがこの一言。これがすべてなんです」。まきさんは、能登の地で目の当たりにした震災の爪痕、それでもなお燃え盛る祭りの熱気、そしてそこに生きる人々の姿を通して「なぜ今、祭りが日本を救うのか」、「地域課題解決の『ひな型』が能登にあるとはどういうことか」を語っていく。
『取材中に最も驚いたことの1つが、被災地であり高齢化が進んでいるはずの能登の祭りに「若い人が多い」ことでした。
なんかね、若い人が異様に多いんですよ。どこ行っても若者、若者、若者なんですよ。能登は高校もいくつかしかないし大学も専門学校もなくて、また若者の仕事もないから、皆金沢とかに行って就職する。能登の人は皆、学校を出たら外へ出ろというように育てられる。そうやって皆能登を離れるのに、なぜか祭りの時にはいっぱいいるんですよね。この謎を解いてみると、そこには祭りを中心とした、見事なまでの「世代間継承の仕組み」がありました。』
その祭りを支えるのが音楽であり、その中心に太鼓がある。輪島で見たものもまさに、世代を超えた伝統の継承の姿だったのだ。
それは8月23日の大阪・関西万博での演奏会に向けて8月11日に七尾市で行われた「能登Dream Drummers」の太鼓チームの壮行会でも感じたことだ。会場の最前列に小さな子供たちを座らせて太鼓の音色をガンガン聞かせる。小学生、中学生の演奏者も大人が見守りながらも対等に扱っている。それを幼い子が、年寄りが応援する。
能登の太鼓は、同じ土地の人だけでなく他の土地の人にも技術を教え合い、切磋琢磨の中で技術を磨いていくというおおらかさがある。毎週各地で順々に展開されるキリコ祭りの音楽も、そうやってそれぞれの土地で囃されていく。


「能登Dream Drummers」の壮行会での挨拶。
目指すは、「能登の未来が、日本の未来になる!」
8月23日午後3時の万博会場は暑い! 皆さん汗だくになる。
「能登の汗は、日本の汗だ!」とこぶしを上げて叫んでいる自分がいた。
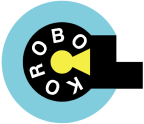



コメント