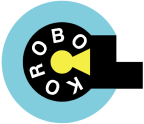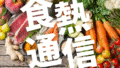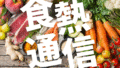【今月の特報】
一般社団法人熱中学園がジャパンタイムス主催“Sustainable Japan Award 2025”でSatoyama部門審査員特別賞を受賞!! (9月18日:表彰式/パネルディスカッション)




◆記念講演会を開催します。
いまからでも間に合います!どなたでもリアル、ZOOMで参加可能です。参加は無料です。
日時:2025年9月30日(火)18時30分 ~ 20時30分(受付開始18時)
会場: ユビキタス協創広場 CANVAS
式次第:
18:00 ~ 受付開始
18:30 ~
開会 司会 綛谷久美 食の熱中小学校教頭
ご挨拶 堀田一芙 一般社団法人熱中学園代表理事
来賓挨拶 末松弥奈子 The Japan Times 代表取締役会長兼社長
来賓講和 雜賀慶二 株式会社東洋ライス株式会社代表取締役 食の熱中小学校名誉校長
19:10 ~ 20:20
記念講演 柏原光太郎 日本ガストロノミ―協会会長 食の熱中小学校校長「日本各地に続々誕生! デスティネーションレストランの魅力」
終了挨拶 大久保昇 株式会内田洋行代表取締役社長 一般社団法人熱中学園理事
申し込みサイトはこちら https://forms.gle/SGq57rpKgHGKxevYA

第5期 申し込み受付中!
申し込みサイトはこちら:https://peatix.com/event/4515187

**************************************************************************

座学: 2025年8月27日(水曜) 18:30~ ユビキタス協創広場 CANVASテーマ:「日本の食はエシカルフードを目指す」 講 師: 山本 謙治 先生(農畜産物流コンサルタント/新渡戸文化短期大学フードデザイン学科教授)
日本の食はエシカルを目指す!
山本 謙治 先生
私は農業や野菜果物の流通の端っこで、畜産関係の仕事や食全般のことを一般に伝えるジャーナリストとして、また並行してコンサルティングとして商品開発や販売のお手伝いをすることをやってきました。新渡戸文化学園の教員ですが、今年4月にフードデザイン学科を新設し、商品開発やマネジメントなどを学べるようになっています。

私は、二戸市の短角牛の母子放牧風景を見て惚れてしまい、これが畜産との最初の出会いで、短角牛のオーナーになり20頭ぐらいの子を産んでもらい肥育して肉にしてきました。最初の1頭をと畜で最後立ち会った時には涙が止まりませんでした。でもそれが肉になり3週間後にレストランに届いて食べたとき、今度はもう幸福感がいっぱい。こんなにもあの命が人を幸せにしてくれるんだと思いました。
今日のテーマはエシカルです。2019年、オーガニックの世界で一番大きなBIOFACH (ビオファ) というイベントに行きました。世界中からバイヤーやメーカーが集まる中、展示品はプラントベース食品で畜産物は一切並んでいないことに衝撃を受けました。またEUの域内全体には環境への悪影響として若者の牛肉離れが起きていることも知りました。ヨーロッパではエシカル基準で商品を選ぶように変わってきていることに直面し、そこから私はエシカル、倫理の部分をしっかり学ばなければと、北海道大学の農業経済学博士課程に入り直し、日本の人々に普及させるにはどうするのが効果的なのかという研究をしてきました。エシカルの考え方によって、生産者の人たちが一番報われてほしい。でも生産している人ほど価格決定権がなく、その値段に妥当性はあるかといった考え方がもっと普及しなければいけない。そういう思いでこの取り組みを始めています。エシカルコンサンプション、倫理的な消費は投票行為です。この商品はフェアトレードをしていて環境にも悪くない配慮をしているから買う、つまり1票を投じる、そんなふうに皆がエシカルな基準に基づいて商品を選ぶようになればいいなと思っています。
ただ、日本の中での道徳や倫理は世界標準とは同じではないです。エシカルとは世界各国の倫理観や道徳観、宗教的な背景や文化的な背景に基づいていて、人や国、地域によって異なるといえ、グローバルにおいてエシカルの議論は基本的には米国が主導しています。でもこの問題に対しどこよりも先に社会実験を繰り返してい解決に向けて実践してきたのはヨーロッパで、もっと言えばイギリスです。イギリスは大英帝国の時代から植民地支配や工業型畜産をしてきたこともあり、その反動で昔からエシカルな考え方に先進的でした。日本では健康のために無農薬のものを食べるのがオーガニックだと思っている人が多いのですがそれは利己的な考え方で、欧米で意識高い系の人はオーガニックというと必ず「環境に対する負荷が低い」と言う。それがオーガニックの本当の意義だと思います。つまり、すでにある有機物動物の糞や植物の残渣と発酵させたものを途中に入れることでそれをエネルギー源にして植物にまた再生してもらう。そうやってできたものを牛や豚にも食べてもらう、という有機物の循環で食品を作っていけばプラマイゼロだ、ということです。エシカルとは他己的に考える態度なのです。
『Ethical Consumer』というイギリスの雑誌があります。例えばある号ではトップ・オブ・ザ・フードチェーンスーパーマーケットいう特集で、小売り市場で最もお客さんに近く巨大な力を握っているスーパーマーケットのエシカル度をランキングしています。編集長であり創始者のロブ・ハリスンさんはエシカルな消費者を育てるためにエシカルの基準を考え、企業に対する基準で320もの評価項目を作りそのデータベースに基づくEthicスコアという素晴らしいスコアリングシステムを持っています。
その取り組みの象徴となったのが2012年のロンドンオリンピック/パラリンピックです。選手村で消費される1億4000万食の食材はすべてサステナブルなものにする、とするフードビジョンという基準書を作りました。例えば、卵はフリーレンジ放牧で育てた卵しか使ってはいけない、などです。環境問題、気候変動対策では、具体的な話としてはフード産業から出てくるCO2が課題です。食の生産現場でのCO2排出源1位は牛のげっぷではなく、ビニールハウスの暖房設備や農器具、農機具を動かす燃料燃焼です。日本人は季節に敏感で旬のものを早く食べたい欲望があるので、料亭などで今年も出ましたと言って喜ばれたいために促成栽培で暖房だって作っちゃうんです。第2位は驚くことに稲作です。田んぼ
というのは大量の有機物の集合体である土の上に水を張り水が染み込みます。すると草の根っこの端や動物の死骸といったものが腐って分解されて炭酸ガスを出すんです。稲作に携わる人たちはこれに衝撃を受け回避しようという研究も進み、その技術が今全国に普及しようとしています。第3位がようやく牛のゲップや排泄物になります。世界では、燃料排出を正そうとしている取り組みは北欧、フィンランドが非常に徹底しています。例えばアタリアというフィンランドポークで知られる養豚企業は メガソ
ーラーと風力発電で自家消費電力を賄っていて、この豚肉はびっくりドンキーのハンバーグに使用されています。世界レベルのエシカル基準の取り組みは日本にはないのが現状です。世界では有名シェフがTV番組で水産資源枯渇に警鐘を鳴らしたりしていますが、日本人はクロマグロにウナギにと絶滅危惧種を食べています。

次は人権の話です。残念ながら日本人は、環境問題に関しては意識が高いですが人権に関してはあまり興味を持っていないと言えます。イギリス人でエシカルトレーディングマネージャーの肩書を持つ方に、一番倫理的と思う施策を聞いたところ、8段階先のサプライヤーに労災を適用したことだと言いました。インドネシアの地方のエビの漁師が海難事故に遭ってしまい、労災適用されず家族の人たちが困窮していて問題になった。しかしコーペラティブグループは、8段階先なのにも関わらず、ちゃんと労
災認定して労災の負担をしたそうです。フェアトレード品は、日本人はドイツ人の1/17、スイスの1/100しか買っていないのが現状です。アニマルウェルフェアでは、例えばフランスではフォアグラを育てる際、ガチョウに強制的に栄養価の高い餌を胃に送り込んで太らせて脂肪肝を作るようなことをしているのが問題になり、世界的にフォアグラの生産・販売禁止の動きもあります。実は日本でも和牛をヨーロッパに輸出する際、鼻環の装着が問題視されて、寸前で取りやめになったことがありました。日
本と海外の倫理観が必ずしもイコールではない例です。黒毛和牛は日本の文化に根付いた素晴らしい牛ですが、通常はずっと牛舎内で育てます。ヨーロッパでは牛は放牧が普通です。しかし放牧経験をさせず運動制限をし、ビタミンコントロールをして肥育すると、下手な場合目が見えなくなることもある。そういう観点から和牛はエシカルでないと見られる可能性があります。欧米ではアニマルウェルフェアの取り組みは投資の判断基準になってきていますが、このあたりも日本企業は周回遅れと言えます。友人で食ジャーナリストのメリンダ・ジョーは 「日本のレストランは美味しいだけのところが多い」と言います。日本のレストランというのはとにかく贅を尽くしおいしさを追求しているが、ヨーロッパの一流シェフであれば料理を通じて何を解決したいかを表現する。たとえばヴィルヒリオ・マルティネスというペルーのモダンな料理を出す一流シェフは、先住民族に対するリスペクトをテーマにし、絶滅しかけている品種のジャガイモを自分たちで育てていくというメッセージをするといった、社会的な位置づけとしての料理を出すそうです。ただここは考えるべきで、エシカルだけでお客さんの満足度があまり高くない料理を出しても意味はないでしょう。でもこれからはおいしさだけではちょっと足りないかもしれない、そのベストバランスを誰かが実現していってもらえないかなと思っていますし、最近ようやくそうしたことを料理に表現する人たちが出てきました。例えば、フロリレージュの川手寛康シェフは、サステナビリティという皿をコースに組み込んでいて、一流レストランでは普通出さない経産牛、お母さん牛を出し、おいしいとされてきた未経産牛はサステナブルではないとメッセージしているんです。畜産農家からするとちょっと一言あるとは思いますが、でも僕はそういった思考で料理をクリエーションしていくシェフが出てくるというのは素晴らしいことだと思っています。

その他、日本では数少ないエシカルの事例として僕がよく紹介するのが佐渡市の「朱鷺と暮らす郷」の認証米と兵庫・豊岡の「コウノトリ育むお米」です。渡り鳥は体が大きく、水生昆虫などの生き物をたくさん食べないと個体を維持できないので、渡り鳥が居着く場所というのは生態系の多様性が保持されているところだと評価されています。佐渡島の人たちも豊岡の人たちも、農薬使用量を少なくした特別栽培の稲作にして、冬の間も水を張ったままにしておく冬期湛水をすると着くのでそれが渡り鳥の餌になります。そうしたらトキの個体数が、環境庁の目標を前倒しするぐらい増えたという結果が出たんです。コウノトリ米は銀座三越の米売場で長いこと売上2位だったそうで、消費者にちゃんと売れています。エシカルを希求する心というのはもちろん日本人にもあるんだと思います。ですので、おいしさはもちろん必要な上にそれをどううまく表現するかでようやく売れるようになる。どうやったら仕掛けとしてうまくいくかということをもっともっと研究していかなきゃいけないと思っています。
今、本当にいろいろなものの値段が高くなっています。これだけ気候変動で暑くなって、人間だけでなく動物も植物も大変なんです。食べものの価格はどんどん上がっていくなあと僕は思います。でも実は、需要と供給がマッチしてようやく生産者の人たちが一息つける金額になったというのが僕の考えなんです。フランスでは、生産者や中間流通の報酬を守る取り組みとして、たとえば不当な契約を押し付ける取引先に対し生産者が申し立てすると政府や組織が介入して指導に入る、エガリムⅡ法という法
律が制定されました。日本でもこういった法律がちゃんとできなきゃいけないと思います。ロブ・ハリソンに日本でエシカルフードを広げるにはどうしたらいいかと聞いたことがあります。すると彼は笑って、「大丈夫、エシカル消費を支えるのはときどきエシカルを買う60〜75%の普通の人であり、この層が少しでもエシカル消費を増やしてくれればいい。日本もこれから皆がエシカルとは何なのかということをちゃんと知識を付けていけば変わっていくはずだよ」と言ってくれました。時々エシカルの消費者、10回に1回だった消費者が、8回に1回、5回に1回と頻度が高くなってきたら、それがどんど
ん消費のエシカル度合いの底上げになっていくと私は思います。これがちゃんと視覚化できる仕組みがたらいいなあということでカルチャーコンビニエンスクラブ、CCCが、エシカルフードラボという組織を作り、一緒にエシカルコンシューマーの作ったスコアリング基準の日本版を作りました。エシカルな商品を買ったらVポイントがつく。1ヶ月経ったら、あなたは今月3000円分エシカルなものを買いましたよなんていう通知が届く仕組みができたら面白いと思いますので、ぜひもっと進めていきたいと思っています。
今日の話は『エシカルフード』という本に書いておりますので、興味のある方はぜひ読んでいただければと思います。ということで、日本はまだエシカルは発展途上ですが、もし皆さんの中で、これはエシカルだと思うよという事例をご存知でしたらぜひ教えていただければと思います。本日はご清聴ありがとうございました。


①北海道・十勝・芽室ツアー 2025年8月23日(土)〜24日(日)(1泊2日)
中塚(森泉)麻美子さんレポート














***************************************************
②かつらぎツアー 2025年8月30日~31日 (1泊2日)
立松結花里さんレポート











***************************************************
事務局より:
本格的な秋の到来です。日本には「○○の秋」という表現が数多くあります。「食欲の秋」「読書の秋」「スポーツの秋」「芸術の秋」などが代表的ですね。これと似た言い回しに「風物詩」があります。こちらはもっと幅広く、モノやコト、文化や生活全般にまで使われる言葉です。
今回は、この「詩」という字に注目してみました。風物詩を英語に訳すと「scenic feature=景勝地」とされることもあるようですが、どこか趣に欠ける印象です。もともとは、季節の風物を詠み込んだ詩歌を指し、そこから「詩」の要素が薄れていき、今のように使われるようになったといいます。語源をたどれば、特定の季節の情趣を描写する「詩」に由来しており、食べ物や行事、文化などを詩に読み込む――なんとも日本人らしい繊細な表現ですね。
ところが、あるランキングサイトでは「秋の風物詩」として一位に紅葉、二位にハロウィンが挙げられていました。他国の文化や風習が、これほど自然に日本の季節感に取り込まれていくのは驚くべき早さです。

「食熱通信第18号」発行:食の熱中小学校事務局(一般社団法人熱中学園内)
公式サイト:https://shoku-no-necchu.com/

Mail to:hello@shoku-no-necchu.com