皆さん、こんにちは。熱中小学校プロジェクト開始10年目で、Japan Times社主催の Sustainable Japan Award 2025 Satoyama部門の審査員特別賞をいただけたのは、大変ありがたい思いです。これも、地方の生徒や事務局の皆様や今日ここに来ていただいている先生方、生徒の皆様のおかげであり、関係者全員が受賞させていただいたというふうに思っています。
熱中小学校の取り組みは、10年前に山形県高畠町から小学校の廃校を再生してほしいと頼まれたことがきっかけでした。学区に子供が少ないので廃校になったのですが、広域では大人がたくさんいるのだから、大人の学びの学校として再開校しようと決めました。その学校が以前、水谷豊主演のドラマ「熱中時代」の撮影場所だったことがわかって「熱中小学校」と名を付けました。自分の座る椅子を作れない人は入学できないというルールにして、入学式の午前中、たくさんの大人の生徒さんに自分の椅子を作ってもらうということをやりました。入学6ヶ月1期の授業料が1万円なのに椅子の材料費が8000円かかった、というように熱が入ったスタートでした。「学びを大切にする地域が繁栄する」ということを役場にも理解いただきました。
「熱中小学校」の特徴は、地域に関わる人達が自主独立の精神で運営する大人の学び舎であること。7歳の目、つまり好奇心旺盛な時の気持ちに立ち返り地方での生き方を考えようという理念は最初から今まで一貫しています。「もういちど7歳の目で世界を」が合言葉です。
現在、廃校や休校した地域もありながら国内15校・海外1校に広がり、2025年7月時点で 約1000人の受講生 が参加。350人を超えるボランティア講師による授業を通じて、地方創生を担う人材を育成してきました。来月12日には高畠熱中小学校では10周年記念行事が予定されています。

この学校の最初の特徴ですが、肝はボランティアの先生をシェアするしくみです。先生には教室の熱量を感じていただき、忙しいけど楽しいからまた次も、となっていただければ学校が継続されるしくみです。先生は、決して行く機会がないような土地で熱量を感じる。こんな体験はしたことがない。忙しいけど、もし次に他の学校からその要望があったらできるだけ行ってみようかなと。で、次に行った場所でもし熱量がたまらければそれで終わってしまいます。でもそれをなんとか繰り返してつないで、学校が維持できているという、そういう形で継続してきました。

2番目の特徴は、先生の授業は楽しかった、では終わりません。セミナーのように1回1回集まっているわけでなく、クラスメートがいるのが学校です。自分自身のことはわからないけれども、人の目を通じて自分がわかってくるということがあるわけで、多様な人達の中で、自分はこんな人間なんだとか、気が付かなかったけれど自分にはこんな良いところがある、ということがだんだんわかってきます。つまり自己肯定の形が出てきます。
現在、7周年を迎えた学校が6つもあって、ここまでくると各地の交流が盛んです。どこかの学校に入学すれば、他の学校は無料で参加できる熱中パスポートという制度があります。
徳島県の上板町、藍染めの一番盛んな町にある熱中小学校では8月の阿波踊りの ‘熱中連’ の中に入れてくれて練り歩きます。だんだん自分の学校以外の人達とも仲良くなる、楽しい!ですが、ここで終わらず第3ステップに行けるかが、熱中小学校の持続可能性がかかっています。一生懸命地方のことをやっても、東京一極集中というのはまったく変わってないです。東京に1400万人、なんとかできないか、首都圏の消費者を地方に行っていただいて、生産者と ‘食’ でつなごうということで、2年前にできたのが「食の熱中小学校」です。

さて、3番目のステップにくると、地元を愛して地元のために何か始めるという生徒さんが出てきます。高畠では、ずいぶん前から耕作破棄地を耕して、みんなでぶどうを作って、地元の高畠ワイナリーさんのご協力を得て、毎年 ‘熱中ワイン‘ を販売しています。
たくさんの生徒さんの新しい発想を得てこれまでと違う活動をしていると、その学校は地元から理解を得て継続の可能性が増していくでしょう。このように熱中小学校の取り組みは、経験から自然に成長してきたまったく新しい地方での学びのしくみです。
一方、首都圏で開校した「食の熱中小学校」はこれまでの熱中小学校とは違う ‘世界で初めて’ の試みが初めから設計されました。東京で生き残って、世界で通用する学校を目指しています(詳細は今後別の章にて)。
最後になりますけれども、私共が今年力を入れているのが、能登半島の支援です。能登半島は里山里海の世界遺産です。我々がSatoyama部門という賞をいただいたからというわけではありませんが、毎月能登の現状を様々な角度から熱中小学校の先生に能登に行って学んでいただき、能登の方々と共同で授業をし、10月からは既存の熱中小学校授業とのコラボをします。
株式会社内田洋行様の115周年記念支援事業としてご支援をいただき、1年間、活動しています。能登半島では一瞬にして町が壊れましたが、日本のどこにおいても、20年、30年かかって世代が交代するたびに同様の現象になっています。七尾市の一本杉商店街の復興の熱気は、全国のシャッター通りなどよりも高い危機感に向き合う ‘創造的な復興’ の現れだと私は考えています。まさに「能登の未来は、日本の未来」なのです。
どの地区でも、熱中小学校開校のきっかけは、常にこの危機感の共有から始まったことを私は忘れません。
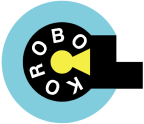



コメント