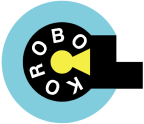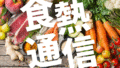一般社団法人熱中学園が
ジャパンタイムズ主催 “Sustainable Japan Award 2025” で
Satoyama部門審査員特別賞を受賞!!




2025年9月30日(火)18時30分より、記念講演会を開催いたしました。
この特別号では各スピーチの抄録をお届けいたします!
会 場 : ユビキタス協創広場 CANVAS
司 会 : 綛谷 久美 食の熱中小学校教頭
ご挨拶 : 堀田 一芙 一般社団法人熱中学園代表理事
来賓挨拶: 末松 弥奈子 株式会社ジャパンタイムズ 代表取締役会長兼社長
ビデオメッセージ: 雜賀 慶二 株式会社東洋ライス株式会社代表取締役 食の熱中小学校名誉校長
来賓講話: 江原 崇光 東洋ライス株式会社 上席執行役員 コンソーシアム推進室 室長
記念講演: 柏原 光太郎 日本ガストロノミ―協会会長 食の熱中小学校校長
「日本各地に続々誕生!デスティネーションレストランの魅力」
クロージング挨拶: 大久保 昇 株式会内田洋行代表取締役社長 一般社団法人熱中学園理事



皆様、本日はお忙しいところお集まりいただきまして、そしてオンラインで参加の皆様もお時間を頂戴しまして、ありがとうございます。では、ジャパンタイムズ社主催の Sustainable Japan Award 2025 Satoyama 部門の審査員特別賞受賞記念講演会を始めさせていただきます。
本日の司会を務めさせていただきます「食の熱中小学校」教頭の綛谷です。それでは、一般社団法人代表理事の堀田一芙よりご挨拶とお話から始めさせていただきます。
代表挨拶 堀田一芙 一般社団法人熱中学園代表理事

皆さん、こんにちは。熱中小学校プロジェクト開始10年目で、ジャパンタイムズ社主催の Sustainable Japan Award 2025 Satoyama 部門の審査員特別賞をいただけたのは、大変ありがたい思いです。これも、地方の生徒や事務局の皆様や今日ここに来ていただいている先生方、生徒の皆様のおかげであり、関係者全員が受賞させていただいたというふうに思っています。
熱中小学校の取り組みは、10年前に山形県高畠町から小学校の廃校を再生してほしいと頼まれたことがきっかけでした。学区に子供が少ないので廃校になったのですが、広域では大人がたくさんいるのだから、大人の学びの学校として再開校しようと決めました。その学校が以前、水谷豊主演のドラマ「熱中時代」の撮影場所だったことがわかって「熱中小学校」と名を付けました。自分の座る椅子を作れない人は入学できないというルールにして、入学式の午前中、たくさんの大人の生徒さんに自分の椅子を作ってもらうということをやりました。6ヶ月1期の授業料が1万円なのに椅子の材料費が8000円かかった、というように熱が入ったスタートでした。「学びを大切にする地域が繁栄する」ということを役場にも理解いただきました。

「熱中小学校」の特徴は、地域に関わる人達が自主独立の精神で運営する大人の学び舎であること。7歳の目、つまり好奇心旺盛な時の気持ちに立ち返り地方での生き方を考えようという理念は最初から今まで一貫しています。「もういちど7歳の目で世界を」が合言葉です。
現在、廃校や休校した地域もありながら国内15校・海外1校に広がり、2025年7月時点
で 約1000人の受講生 が参加。350人を超えるボランティア講師による授業を通じて、地方
創生を担う人材を育成してきました。来月12日には高畠熱中小学校では10周年記念行事が予定されています。

この学校の最初の特徴ですが、肝はボランティアの先生をシェアするしくみです。先生には教室の熱量を感じていただき、忙しいけど楽しいからまた次も、となっていただければ学校が継続されるしくみです。先生は、決して行く機会がないような土地で熱量を感じる。こんな体験はしたことがない。忙しいけど、もし次に他の学校からその要望があったらできるだけ行ってみようかなと。で、次に行った場所でもし熱量がたまらなければそれで終わってしまいます。でもそれをなんとか繰り返してつないで、学校が維持できているという、そういう形で継続してきました。

2番目の特徴は、先生の授業は楽しかった、では終わりません。セミナーのように1回1回集まっているわけでなく、クラスメートがいるのが学校です。自分自身のことはわからないけれども、人の目を通じて自分がわかってくるということがあるわけで、多様な人達の中で、自分はこんな人間なんだとか、気が付かなかったけれど自分にはこんな良いところがある、ということがだんだんわかってきます。つまり自己肯定の形が出てきます。
現在、7周年を迎えた学校が6つもあって、ここまでくると各地の交流が盛んです。どこかの学校に入学すれば、他の学校は無料で参加できる熱中パスポートという制度があります。
徳島県の上板町、藍染めの一番盛んな町にある熱中小学校では8月の阿波踊りの ‘熱中連’ の中に入れてくれて練り歩きます。だんだん自分の学校以外の人達とも仲良くなる、楽しい!ですが、ここで終わらず第3ステップに行けるかが、熱中小学校の持続可能性がかかっています。一生懸命地方のことをやっても、東京一極集中というのはまったく変わってないです。東京に1400万人、なんとかできないか、首都圏の消費者を地方に行っていただいて、生産者と ‘食’ でつなごうということで、2年前にできたのが「食の熱中小学校」です。

さて、3番目のステップにくると、地元を愛して地元のために何か始めるという生徒さんが出てきます。高畠では、ずいぶん前から耕作破棄地を耕して、みんなでぶどうを作って、地元の高畠ワイナリーさんのご協力を得て、毎年 ‘熱中ワイン‘ を販売しています。
たくさんの生徒さんの新しい発想を得てこれまでと違う活動をしていると、その学校は地元から理解を得て継続の可能性が増していくでしょう。このように熱中小学校の取り組みは、経験から自然に成長してきたまったく新しい地方での学びのしくみです。
一方、首都圏で開校した「食の熱中小学校」はこれまでの熱中小学校とは違う、‘初めて’の試みがあらかじめ設計されました。東京で生き残って、世界で通用する学校を目指すのは容易なことではありません。
「食の熱中小学校」は、世界初の ‘ガストロノミーの今と未来を美味しいツアーと座学で気軽に学びながら地方を応援する学校’ です。こんな食のツアーがあったのか! という感動。忙しい方々が出られない授業は、同時配信Zoomはもちろん映像の提供、そして授業の抄録付きの「食熱通信」が毎月送られてきます。私は過去の素晴らしい先生のバックナンバーを読み直すことがあります。そして4種類の懇親会があります。
①丸の内の会 ― 食熱ツアー先の食材やドリンクを取り寄せて、給食担当の料理研究家・山田玲子先生の食材を活かした料理を楽しみます。普段手に入らない稀少な高級ワインに出会えるようなチャンスも。
②八丁堀の会 ―ケータリング+地域のお取り寄せのお酒、飲み物を楽しむ。
③横浜高台でのガーデンパーティーの会(第2授業の月に開催)― 個人宅の庭の畑で獲れた野菜や果実のサラダ、自家製のスモークサーモンやベーコン、柏原校長をはじめ全参加者が持ち寄る一品、ワインや日本酒、飲み物が揃い、自分だけのピザの窯焼き体験も。広くて明るい日本庭園や芝生での午後のひととき、継続参加のメンバーと新しく参加した生徒さん同士が知り合いゆったりと懇親いただける場です。
④食熱美食倶楽部 ― スペイン・サンセバスチャンの「美食倶楽部」にあやかり食いしん坊が同じキッチンで料理をして互いの料理を分け合って楽しむ、柏原校長が自ら企画・参加する懇親会です。料理の腕前も難しいメニューも不問。食熱ツアーの体験で作った手作り味噌や柏原校長手製のローストポークやスペインオムレツなどの逸品も登場、料理を作ってみんなで楽しめる大好評の企画です

最後になりますけれども、私共が今年力を入れている能登半島の支援について触れさせてください。
能登半島は里山里海の世界遺産です。我々がSatoyama部門という賞をいただいたからというわけではありませんが、毎月能登の現状を様々な角度から熱中小学校の先生に能登に行って学んでいただき、能登の方々と共同で授業をし、10月からは既存の熱中小学校授業とのコラボをします。
株式会社内田洋行様の115周年記念支援事業としてご支援をいただき、1年間、活動しています。能登半島では一瞬にして町が壊れましたが、日本のどこにおいても、20年、30年かかって世代が交代するたびに同様の現象になっています。七尾市の一本杉商店街の復興の熱気は、全国のシャッター通りなどよりも高い危機感に向き合う ‘創造的な復興’ の現れだと私は考えています。まさに「能登の未来は、日本の未来」なのです。
どの地区でも、熱中小学校開校のきっかけは、常にこの危機感の共有から始まったことを私は忘れません。
来賓挨拶 末松弥奈子 株式会社ジャパンタイムズ 代表取締役会長兼社長

最初にジャパンタイムズについて少し紹介をいたします。ジャパンタイムズは明治30年、西暦1897年に創刊された、日本で最も古い英字新聞です。2013年からニューヨーク・タイムズと提携をしまして、ジャパンタイムズを購読すると、ニューヨーク・タイムのインターナショナル・エディションが入っていたりします。多くの方に知られていたのは Student Timesではないでしょうか? 現在はJapan Times Alpha と言われていますけれども、英語学習誌です。デジタルの時代に、スマホの中で英語の勉強を続けることは難しいという事で毎週届く英語学習新聞として愛されています。
さて、今回受賞されました。Sustainable Japan AwardのSatoyama 部門。この ‘里山’ という言葉が注目されるようになったのは、多分、2013年に発行されました「里山資本主義」という本の影響が大きいのではないかなと思います。この本、累計で40万部を超えておりまして、文庫もまだ売れているそうです。藻谷浩介さん、それから、当時NHKの広島放送局で番組になっていたものを本にしたものになります。私は広島県の生まれで、大学から東京に出て、東京の方が長くなって、学生時代はもうこんな田舎から早く東京に出たいと思って東京に出てみると、年を取れば取るほど田舎の良さとか魅力がわかってくるものです。この本に出会って藻谷さんともご縁をいただいて感銘を受け、この本をテーマにして、全国各地にさまざまな形で地域の持続可能性を追求している方がいるということで、2017年に周防大島で最初の交流会を開きました。

2018年に、これをジャパンタイムズで世界に発信していこうということで、Satoyama推進コンソーシアムというものを立ち上げました。私の地元の広島県の神石高原町で実践者交流会をし、2020年、三重県の志摩市では「SDGsを里山里海で考える」をテーマで実施しました。2020年にはジャパンタイムズ出版から「進化する里山資本主義」という本を出しました。その後も青森県むつ市で「ガストローツーリム」、2023年には鳥取市で「Satoyama × Global (里山 × グローバル)」、昨年は北海道の余市町で「里山×インバウンド」で北海道のポテンシャルをテーマに実践者交流会をやってきています。この流れの中で、交流会でコンテンツとして、皆さんを紹介するだけではなくてアワードにすると、より内外から注目を浴びるのではないかなということで、ジャパンタイムズの Sustainable Japan Awardを2019年に開始しました。

今年 Satoyama部門を受賞したのが、ファクトリエをやっているライフスタイルアクセント株式会社さん、そして株式会社中川さん、ヤマロク醤油株式会社さん、そして皆さんの一般社団法人熱中学園さんでした。

ファクトリエさんは熊本県に本社があります。日本のアパレルの製造をしている町の工場の多くは、ずっと裏方でオーダーする会社からの言い値で商品を作っていたのを、その工場の希望する価格で商品を作ってファクトリエのブランドで売るということで、日本中で60カ所の工場で366のアイテムを販売していらっしゃるそうです。株式会社中川さんは和歌山県の企業で、木を切らない林業ということをしています。切った後にどんぐりから植栽をして、木を植えて育てる会社ですけが、これを起点に全国で同じような取り組みをするところが増えてきているのです。
ヤマロク醤油さんは小豆島にある小さなお醤油屋さんですが、木桶でお醤油を作っている会社です。木樽での醤油作りは本当に少なくなっているそうです。この木桶職人がもういなくなるということで、木桶を作るところから醤油会社の方が勉強して、一緒に木桶を使ったお醤油を増やしていきましょう。国内流通量が今1%だけど、それを2%にしましょう、というような取り組みをされています。現在、その取り組みを一緒にやる仲間が増えて、国内は25都府県、50社の醤油会社さんが、木桶を使ってお醤油を作っています。海外ではイタリアで木桶仕込みにチャレンジしされているそうです。
一般社団法人熱中学園さんの活動は2015年から始まって、ちょうど記念すべき10年目に受賞となりました。私たちは長く続けていらっしゃるところにスポットライトを当てたいということで、審査をしています。
全国に大人の学び舎が展開されていて、しかもシアトルにもある。実は今回、2025年に受賞したすべての会社さん、団体さんの活動は日本のいろんなところでスタートはしていますが、それが全国にあるいは世界に広がるという企業や団体が今回選ばれています。それはあえて選んだのではなくて、本当に偶然でした。
私たちは同時多発的に日本で起こっていた事象を表彰することによって皆さんにクローズアップしていただきたいなと思っていました。このように、1つのモデルタイプからいろいろな広がりがあるものをよく文鎮型モデルと言うんですけど、では英語で文鎮型モデルはペーパーウェイト? 難しいよねということで編集部でいろいろ議論しまして、もともとのコンセプトは里山ということで、里山がプラットフォームになっている。そういった里山プラットフォーム、あるいは里山プラットフォーマーというのが、今年の里山アワードの特徴ではないか考えています。

熱中小学校はまさにその典型でして、10年かけていろんな地域に広がっていますし、そこにフレキシビリティもあるから、多様な人々に受け入れらているのではないかなと思っています。この素晴らしい皆さんの活動を、Satoyamaプラットフォームとして表彰させていただくことができて、私たちも大変ありがたく思っております。こうして、この賞についてご記念講演会を開催いただき、私たちの活動を誇らしく思います。
ビデオメッセージ 雜賀慶二 東洋ライス株式会社代表取締役

「食の熱中小学校」の名誉校長の雑賀です。和歌山県和歌山市からお祝いのメッセージを申し上げます。10年の堀田さんの活動の成果が報いられて、おめでとうございます。
私は今後も日本の、世界の持続可能性向上のための活動を推進するつもりです、ぜひ当社のコンソーシアム活動についてご理解をいただきたく、江原に紹介する機会とさせていただければと思い参加いたしました。よろしくお願いいたします。
来賓講和 江原崇光 東洋ライス株式会社上席執行役員

堀田さん、この度の受賞、誠におめでとうございます。
堀田さんと知り合ったきっかけですが、和歌山県すさみ町の岩田勉町長様に紹介いただきました。岩田町長と堀田さんがお話をされているときに、和歌山市にこんな変わった91歳の社長がいるからと、当社の社長にお会いいただきました。それからお付き合いさせていただいています。
東洋ライスという会社について簡単にご紹介させていただきます。当社は和歌山県和歌山市発祥で、もともとは米の加工機メーカーです。社員は約200人、社長は吹けば飛ぶような中小企業と言っております。
東洋ライスの取り組みと、SDGs への貢献ということですが、当社は1991年に世界で初めて無洗米の製造プロセスを開発しました。無洗米は当初、働く主婦に朗報、とか簡単便利、というフレーズで発売されましたが、開発者の雑賀(社長)は、それを気に入りませんでした。実は無洗米を開発した理由は米のとぎ汁による水質汚染を防ぐためだったのです。
米のとぎ汁って、家庭菜園とかで植木に撒いたりされると思うんですが、これはリンという成分が非常に豊富だからです。とぎ汁がそのまま海に流れ出ると、海水の栄養が豊富になりすぎてプランクトンが死んでしまい、赤潮が発生するのです。米業界にいる自分がなんとか解決したい一心で開発したのが無洗米です。無洗米にもいろいろな種類がありますが、当社のBG無洗米は完全なゼロエミッションです。
米の価格が問題になっていますが、米のとぎ汁を流すだけで1.5%も損してしまうんですよ。そういった観点からも、無洗米というのは環境にも経済的にも優しい米なんです。
当社は、本来とぎ汁として流してしまう肌ぬか(副産物)を、有機質肥料として畑や田んぼに還元します。この取り組みは海外で高く評価され、SDGsの好事例として、民間企業としては初めてスイスの国連本部で講演を行いました。雜賀は英語がしゃべれないので、わしらはSDGsなんて言葉ができる前からSDGsをやっとるんじゃ、と和歌山弁で話してきたそうです。

米の構造について話をしたいと思います。玄米の構造を見ていただきますと、一番表面はロウ層といって、ロウソクの蝋みたいな水をはじく成分です。2番目はヌカ層といって、いわゆる玄米の色をしています。栄養がとても多い部分ですが美味しくはありません。3番目は亜糊紛層といって、とても薄い層です。色は白くて栄養価と美味しさが多い部分です。4番目は皆さんが普段食べられている白米の部分で、澱粉層といいます。炭水化物が豊富で美味しいけれども、栄養価はほとんどありません。雜賀が着目したのは、3番の亜糊粉層という部分です。ビタミンやミネラルが豊富で、非常に美味しい成分も含まれております。金芽米はこの亜糊粉層を残す加工をした米です。
実は雜賀は60歳ぐらいまで奥さんから病気のデパートといわれるぐらい病弱だったそうです。ちょっと風邪を引くと3カ月会社に来ないとか、そういう人間だったらしいんです。自分は米の業界にいるし、玄米というのはもともと漢方薬の成分にも使われていた。米の力を信じて、最初は玄米食をトライしたそうです。でも美味しくなくて、三日坊主で白米に戻ってしまった。次に5分づき米とか7分づき米を試してみても美味しくなくて、やっぱり白米に戻ってしまった。
なんとか美味しくて、さらに栄養価が残っているコメの加工ができないかということで、亜糊紛層を残した金芽米を開発しました。それで本当に自分が健康になったのです。
金芽米は、美味しさを残した健康志向の無洗米です。最近ではロウカット玄米といって、何の栄養素もないロウ層の部分だけを削り、白米と同じように食べやすい玄米を開発しました。玄米と同じ栄養素を持った米です。いずれも米の加工技術であり、基本的には金芽米もロウカット玄米も米は選びません。

ここから本題に入りますが、社長の雑賀も90を超え、今は社業よりも世の中のことをどうにかしたいということに考えを集中しています。
医療費の急増に危機感を持っていて、年間の医療費、なんと48兆円。国の財政を圧迫しています。米の消費が減ったのと医療費が増えたのって、ちょうど逆相関の関係になっています。うちは金芽米を社員食堂で食べさせたところ、保険組合から送られてきた事業所カルテの結果で、和歌山県民の平均医療費よりもうちの社員の医療費が4割ぐらい低かったんです。実はうちの会社、社長の歳が歳なものですから、70代以上の社員がゴロゴロいるんです。医療費、絶対高いはずなんですよ。それが4割ぐらい安い。うちの会社だけじゃなくて、同じように和歌山県の2~300人くらいの会社の2か所に1年間、無料で金芽米を提供して社食で食べていただいたところ、同じように4割ぐらい医療費が下がりました。これを社会実装できないかということで10年ぐらい前、当時の農林水産大臣に、金芽米の特許を国に譲るから国の力で普及してください、と社長がお願いに行ったのですが、当然ですがお断りされました。
病弱だった自分が健康になったのだから信念があります。それならわしが自分でやっちゃる! という考えになり、身体と環境に良い米を世の中に普及させるコンソーシアムを一昨年立ち上げました。
医療費を減らしていこう。次代を担う子どもさんや妊婦さんの健康度を高めていこう。病気を減らしていこう。あるいは食料自給率の向上を図り、コメの価値を高めて農家さんの生産意欲を高めよう。さらには、価値ある米を輸出して海外の人にも健康の貢献をしていこう。こういった取り組みを行っております。
持続可能な取り組みの1つ目として、熱中小学校の関係先の熊本県人吉市の活動をお話します。人吉市では、妊婦さんにお子さんが生まれるまでの間、毎月5キロの金芽米をご家庭に配達しています。栄養価の高い米を食べていただいて元気なお子さんを産んでいただきたいという取り組みが行われています。

大阪の泉大津市は、マタニティ応援プロジェクトということで、毎月10キロの金芽米を妊婦さんのご家庭に毎月お届けしています。アンケート調査をしたところ、妊婦さんの体調不良が軽減されたり、赤ちゃんの出生時体重が、金芽米を食べる前の過去4年間の各年度と比較して増加しています。この結果は泉大津市が発表しています。
持続可能な取り組みの2つ目は、学校給食です。NHKでも紹介していただいたのですが、島根県の安来市では生まれる前から公立中学校まで、すべての子どもが金芽米を食べられるような取り組みをされています。

金芽米の良いところは地産地消が可能な点です。どんな米でも金芽米に加工できますので、地元の米が使えるのです。地元の米を地元の人たちが食べることで、生産者の皆さんのやる気がすごく出るんですよね。そうすると、やっぱり米作ろうって気にもなります。
私たちは地産地消の取り組みを進めています。福岡県の久山町では、昭和36年から九州大学の医学部と連携して久山調査という町民の疫学調査をやっています。40代以上の町民の検診を町が行い健康管理をすることで、生活習慣病を改善したり、認知症の患者さんも減ったということです。来年からは、金芽米を導入し人々の健康がどう変わるかということを一緒に研究する予定です。

3番目はスポーツとの取り組みです。これは「食の熱中小学校」との関わりですが、半年ぐらい前の朝、寝ていたら堀田さんから電話がかかってきまして、相撲を見てるんだ、って。こんな早くから相撲をやってるのかなと思ったら、今「食の熱中小学校」のツアーで糸魚川市に来ていて、海洋高校相撲部の練習を見学していると。その相撲部が米不足で大変だということでですね、熱中と東洋ライスで金芽米100kg支援しようと。こっちも眠いし、いいですよって言って電話を切ったんですけど、何分かしたらまた電話がかかってきて、今度は300kgだっていわれて。何日か経ったら堀田さんから連絡があって、結局1トンになったと言われました(笑)。
7人の部員で毎月300kgの米を食べるそうなので、4月から毎月300kg食の熱中小学校と支援しています。大の里の出身の相撲部ですが、支援し始めた翌月には横綱に昇進、そして今回優勝しました。このご縁は嬉しい結果でした。
血糖値が高い生徒さんでも金芽米で米食に戻ることができたと監督さんに喜ばれています。水産高校ですからとぎ汁で海を汚すのもよろしくないですし、相撲部の皆さんには栄養をしっかり取って体づくりをしていただきたいということで、高校生の健康的な成長を応援させていただいています。

廣瀬俊朗さんという、慶應大学ご出身のラグビー元日本代表のキャプテンのご紹介で慶應大学のラグビー部を金芽米で支援しています。コンソーシアムのつながりで、茨城県のつくばみらい市の市長さんから玄米を提供していただき、神奈川県の工場で加工しています。米の持続的な出口作りです。11月ぐらいから早稲田大学ラグビー部も金芽米で支援することになっていまして、早慶戦の盛り上がりが楽しみです(笑)。
「食の熱中小学校」の柏原校長先生にもお世話になりました。柏原さん、もともと文藝春秋にいらっしゃいました。うちの社長は91歳なんで、なんとか彼の熱い思いを残してあげたいなと思いまして、文藝春秋1月号から4回ぐらい連続で記事を出す予定です。是非ご覧いただければと思います。
私たちはこのような持続可能な取り組みをやらせていただいております。これからも、熱中小学校の皆さんと一緒に楽しくやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。ありがとうございました。
柏原光太郎校長記念講演
「日本に続々誕生! デスティネーションレストランの魅力」

ただいまご紹介にあずかりました柏原でございます。
私が校長を務める食の熱中小学校は、先ほど堀田が話をしましたように、全国に15ある熱中小学校の一番若いよちよち歩きの学校です。なぜ食の熱中小学校が開校に至ったかですが、実は私は、熱中小学校というものがあること、そしてそれにいろいろな方が携わっていること自体は以前から知っていたんですけれども、自分が熱中小学校に関わることに関しては、この食の熱中小学校が初めてでした。この約2年の間に、熱中小学校の授業とはどんなものなのか、そしてどんなふうに地方と首都圏の関係を構築できるのかということを肌身で知ることができました。今日はそんなことを含めながらお話しできればなと思っております。

まず、日本国内にある15の熱中小学校は食の熱中以外はすべて地方にあるんですよね。地方の熱中の1つ1つが独立して、今日本で何が起こっているのかを知るということでだいたい月に一度、2人の先生をお呼びしてお話を聞くというのが地方の熱中小学校の成り立ちだと私は理解しています。
私もこの2年間いろんなところに行かせていただき、お話をする機会がありました。地方の方々と話をする機会も多くいただきましたが、実感したのは、地方に共通する一番強いコンテンツって、食なんですよね。第一次生産者であったり加工業者の方であったり、物流の関係者の方であったりさまざまですが、日本の地方経済を支えているのは食であり、実は首都圏の生活を支えているのも地方の食なんです。
ところが、なかなか地方と首都圏間の交流というのがなくて、あれだけ地方に素晴らしい豊かな食材や食があるのに、なかなかそれが東京に住んでいる我々に伝わってこない。だったら、食だけの熱中小学校を東京に作って、私たちは地方に行って地方の食の豊かさを知ることによって地方と首都圏で何ができるかを考えようよ、というのが食の熱中小学校かなと思っております。
スライドに里山プラットフォームということを書かせていただきました。先ほど末松さんからお話があったような里山の地に対し、私たち首都圏の人間は何ができるかを考えた時に、座学とツアー、というこの2つが食の熱中小学校の大きな武器なんですね。その中でもツアーが非常に重要だと思っています。
座学は、手元の資料にもありますように第5期も月に1回ものすごく素敵な先生方に来ていただいて、地方の食がどうなっているのか、食について首都圏がどんなことをしたらもっともっと楽しいのかということをお話ししていただきます。
一方、実際に現地に行くのがツアーです。この土日は、山形県の鶴岡に行ってきました。この鶴岡のツアー、実は2回行われました。鶴岡にはアル・ケッチァーノというイタリアンレストランがあります。アル・ケッチァーノの奥田シェフは、食べ歩きの好きな方ならよくご存知の方で、この方の料理はとても素晴らしくて、鶴岡がある庄内地方の野菜や魚を使った彼の料理を食べたいという人たちはたくさんいるんですけど、奥田さんと一緒に畑に行って、奥田さんがこういう野菜を使うんだよというのを教えていただき、それを使って奥田さんが作る料理を食べる経験をしている人は稀でしょう。だったらそういうツアーを考えようと思い企画したところ、一瞬で埋まってしまったんです。しかたないので奥田さんにもう1回やりましょうよとお願いして、先週その2回目が終わりました。そんなのが食の熱中ツアーです。
食の熱中ツアーのことを、大手の旅行会社が絶対にできないツアー、と私は勝手に言っているのですが、地元の食関係者との交流ができるツアーというのをやります。これって私たち首都圏の人間にとってとても楽しいことなんですけど、地方の方々にとっても、住んでいるとわからない地方の豊かさに気づく機会になっているかな、と勝手に自負しております。
ジャパンタイムズさんが取り組まれているディスティネーションレストランアワードという賞があります。日本の地方にはわざわざ東京から、また東京だけでなく世界からも行くべき理由のある素晴らしいレストランがたくさんあり、それをデスティネーションレストランというのですが、そこのシェフたちと話をすると、ほぼ全員同じことをおっしゃるんです。
だいたい皆さんUターンの方が多いんですが、18歳までこの田舎にいて退屈でなんとかして外に出たいと言って、食が好きな方は東京や京都や大阪に出て行くんです。東京や京都や大阪にはとても素晴らしい体験があるに違いないと思って行ってみたら、なんだ、俺が18まで食べた魚や野菜の方が美味いじゃないかと気づく。そうは言っても技術を身に付けるには10年ぐらいかかりますから10年ぐらいは都会で技術を身につけて、その後自分たちの生まれ育った故郷に戻ってレストランをやろうという方がすごく多いんですね。
つまり、地方にいるだけだとなかなか気付くことができないものがあるわけです。本当はこの話のように外に出てみるのが重要なんですけど、そうでなくても外の人間が地方に行って一緒に話をすることで、そこでは当たり前だと思っていたことを外の人間が新しい視点で気づくことができる。
例えば鶴岡は、米どころですから水田がたくさんあるんですね。地元の方にとって水田のある景色というのは当たり前の日常なんですど、水田の上にホテルを建てたらどうだろうかということを考えた人がいて、その人がスイデンテラスというホテルを造って、それがものすごく人気になっています。水田の上なんかにホテルを建てて何が楽しいんだろう、と多分地方の人たちは思ったと思うんですけど、そういった外からの視点を持って、我々は地方の方々と一緒に何か新しいことができるような役に立てるんじゃないかな、と勝手に思っています。それが食の熱中小学校の1つの意義かなと思っております。
また、そういうことによって、自治体の方々が自律的に動いてくださるといいなと思っていて、だいたい食の熱中のツアーを受け入れてくださる自治体は、それだけで結構元気なところがあるんですけれども、その方々が、なるほど、こういうことによって、食っていうのがやっぱり地方の一番の武器なんだなっていうことを考えていただけると、嬉しいなと思っております。
実際、この2年、わずか2年ですけれども、いろいろな動きが出てきています。座学で授業をしてくださった先生が、なるほど、じゃあうちでもツアーやりたいねと言ってくださったりとか、ツアーの開催地の周辺の人たちも、今度はうちでもやろうよと言ってくださったりとか、そういった方々がたくさん出てきて、少しでも影響を与えて地方を活性化させることができる助けになるのかなと思っているところです。
食の熱中小学校が時代にフィットしてるんじゃないかなと私は思っていて、というのもその裏には、実はデスティネーションレストランの存在というのがあるんですね。そのデスティネーションレストランのお話と、その前に、ガストロノミーツーリズムの話をさせていただきたいと思います。
ガストロノミーツーリズムという話も、先ほどの末松さんのスライドに少し出てきました。ツーリズムは観光といった意味でよくご存知かと思いますが、ガストロノミーって、いろんな言い方をするんですけど、食文化かな、と私は思っていまして、食文化を使って観光をして人を呼んでみよう。食の熱中がやっているツアーのようなものなんですけど、それがなぜ地方に重要なのかなっていうと、1つは、やっぱり日本は貧しくなったよねっていう話がある中で、特に地方の疲弊というのは深刻ですよね。人口減少と高齢化、地方経済の縮小、東京一極集中、こうした課題があることは皆さんも少なくとも肌感覚でわかっていらっしゃるかと思うんですけど、そうした中で、ガストロノミツーリズムを使って地方を豊かにしていこうじゃないかという動きがあります。
今、ツーリズムというと、アドベンチャーツーリズム、メディカルツーリズム、グリーンツーリズムなどたくさんありますよね。そこへ、なぜガストロノミツーリズムなの? という疑問があるかもしれませんが、その理由の1つにインバウンドがたくさん日本に来ているという背景があります。
東京や京都へ行くと、本当にたくさんの外国人の方に出会うと思います。今年は多分、4300万人は確実に来るだろうと言われています。実は、2021年のコロナの時は24万人しかいませんでした。ほぼゼロです。そこからわずか4年間で4300万人、これは史上最高です。去年は3700万人来たんですけれども、では3700万人のインバウンドがいくら日本に落としてくれたのかというと、8兆1000億円落としてくれたんです。インバウンドが日本で使うお金というのは輸出額に勘定されるんですけど、8兆1000億円というと自動車の18兆円に次ぐ規模なんですね。ですから、インバウンドというと、オーバーツーリズムで大変だから、鹿を蹴ったりする人達もいるからもう日本に来なくていいよという話があったりします。もちろんオーバーツーリズムは解消しなくちゃいけないと思いますが、やはり日本の産業がなかなか伸びていない中、観光立国という言葉は小泉総理の時から始まったんですけど、やはり観光というのはうまく取り入れるべきではないかと思うんですね。
そして中でもなぜガストロノミーなのかというと、日本に来たいインバウンドの人達に日本に来たい理由を聞くと皆、食事が美味しいから、美味しいものを食べたいから、って言うんですよね。2021年のコロナの真っ盛りに実施した、コロナが終わったらどこへ海外旅行に行きたいですか?という調査では日本がトップになりました。しかも食事が美味しいからという理由です。

2023年にコロナが収まった時の日本政府観光局の調査でも、世界の22の市場のうち半分の市場でやはり日本が1位でした。ちょっと両者の調査の仕方が違うので一概に比較はできませんが、旅行の目的はやはりガストロノミー、美食なんです。その中でも富裕層と言われている人達、もう1つはアメリカンエクスプレスの調査ですけど、世帯年収が1000万円以上を対象にしたときに、やはり旅行の楽しみは地元の食べ物や料理を味わうことなんですが、さらに面白いのは、まだあまり人が知らないところを人気が出る前に探したい。それをSNSとかに最初にあげて、いや俺は前から知ってたよというのが多分、彼らが今一番やりたいことなんですね。
ということは、もう東京や京都に行くんじゃなくて、地方に行って地方の美味しいものを探すっていうのが今のインバウンド、特に富裕層の方のトレンドだよね、別にインバウンドじゃなくて日本でも、旅行に行きたい人たちのトレンドは、東京や京都のミシュランに出ている3つ星や2つ星の店を探して行くのではなくて、地方のおいしいものを探そうということなんだよね、というのが今の時代の空気なんだろうなと思うんですね。

これは、世界のラグジュアリーな市場レポートの中でもまったく同じことが書かれています。新たな富裕層が旅に求めるキーワードは、誰も見つけていないものを見つける。そしてそこで新しいビジネスを作れればもっといいよねということなんです。

ただ、皆地方に行きたいけれど実際に地方に行っているかっていうと、これは2023年の調査ですが、旅行先は三大都市圏が70%、残りの地方は30%しか行ってないんです。

皆行きたいのに行ってないというところにミスマッチがあって、ここに行ければ皆美味しいものを探せるよねということで、ガストロノミーツーリズムが今とても関心を呼んでいるということなのかなと思っています。食の熱中小学校がやっていることも、実はそれに結構パラレルなところがあるかなというふうに思っております。
ただ、そういうふうに言うと、特にインバウンドの話をすると、さっき言ったような、日本はオーバーツーリズムだからもういらないよねって話が特にここ数週間で出ていますよね。でも本当なのかなって、まあ本当なんですけれども、じゃあオーバーツーリズムだからもう日本に人来なくていいよっていう話なのかなというのはちょっと違うんじゃないかと思っているのです。
2023年の数字ですけど、世界で最も外国人観光客の多い国はフランスで、1億人来ているんです。2位のスペインも8500万人も来ていて、おそらく去年は1億人に達していると言われています。考えてみると、フランスの人口は6800万人、スペインは4800万人なんですね。つまり、フランスもスペインも人口の1.2倍とか1.5倍ぐらいの観光客が来ているのでオーバーツーリズムだと言っているわけです。最近よくバルセロナが反観光デモをやっているという話がよく出てますけれども、確かバルセロナには人口の10倍ぐらいの観光客が来ているんですね。
それ自体誉められた話ではないかもしれないんですけど。じゃあ日本ってどうなのという
と、去年は3700万人来日しています。日本の人口は1億2000万人ですから人口の30%、今年は4300万人来ているといっても40%に過ぎません。だからといって今大変な、パスに乗れない京都の人がいるといった現状はもちろんちゃんと正さなきゃいけないことなんですけど、それでもこれだけ日本に行きたいというインバウンドの人たちがいることは、日本が貧しくなったと言われる中で日本の観光地方の豊かさというのは日本が誇るべき資源であることの現れであることは間違いないんですよね。
だったら今まで東京や京都、大阪、福岡、北海道ぐらいまでしか来ていない観光客を地方に分散させようというのが、ガストロノミーツーリズムの話なんですね。特にインバウンドの富裕層を政府は分散させたいなと言ってるんですね。それはなぜかというと、官公庁が定義しているインバウンド富裕層というのは、1回の旅行で1人100万円以上使うお客さんのことで、通常は23万円ぐらい使うのでその4倍ぐらい使う層を富裕層と定義しているんですけど、たくさん使ってくれれば地方にもたくさんお金が落ちるよね、という考えです。
じゃあ一方、日本は本当に食が豊かなんですか? ということをちょっと考えてみようと思います。ミシュランの星付きレストラン数は、2025年版、2026年版とも東京がトップです。さらに、人口比でいうと世界一なのは京都なんですね。ですから東京や京都というのはやはり世界中で最も美味しい、そして東京や京都に代表される日本というのはやはり美味しいものがたくさんあると言っていいんじゃないかと思います。
じゃあ東京や京都と地方ではどう違うんですか? と聞かれたら、東京は何でも揃っているけど地方には圧倒的な美味しいものがあります、と言います。豊洲から、また飛行機で世界中から素晴らしい食材がやってくる。ニューヨークやパリやロンドンよりも東京の方が圧倒的においしいものがたくさん集まってきます。だけど、やっぱり時間が経っているんですよね。時間が経っているし、豊洲の美味しいものってだいたい季節によって同じなので、例えば1週間の間に3回お寿司屋さんに行くとだいたい同じネタが出てくるんです。
ところが地方は、多分東京の100分の1ぐらいしか食材の種類はないかもしれないですけど、やっぱり圧倒的に美味しい朝どれ食材っていうのがあるわけです。
この夏、食の熱中小学校で十勝の芽室町に行きました。実は私はこの時初めて芽室町の存在を知ったんですけれども、芽室町はアヲハタコーンのトウモロコシの収穫地で、アヲハタコーンは芽室町のトウモロコシからできているのが一番多く、それぐらいトウモロコシが美味しいんですけども、トウモロコシって夜明け前に食べるのが一番美味しいんです。夜明け前、太陽が出る前に食べるトウモロコシを、本当はポキッと折っちゃいけないらしいんですけど実のまま生でかじると一番美味しいっていう話は私、耳学問で知ってたんです。それを今年の8月、正にツアーで体験できたんですね。皆朝4時半に畑に集合して、朝どれのトウモロコシをかじる。本当にジューシーで、一緒に行った教頭の綛谷が、ジュースが出てくるようだと表現していましたけど、それぐらい美味しいんです。また、食の熱中がなかなかすごいなと自画自賛するのは、芽室町の方々、十勝の熱中小学校方々がとてもホスピタリティ満点で、畑の真ん中にテーブルを作って、朝のトウモロコシを使ったここでしか食べられない朝食っていうのを作ってくださったんですね。こんなことっていうのは絶対東京じゃ味わえないんですよね。
だから、やっぱり都会は凡庸で、地方というのは美味さに満ちているんだなっていうことが、行けばわかる。行けばわかるんだけど、なかなか最後背中を押すことができないよねっていうところが、今皆がなかなか地方に行かないもどかしさだろうなと思っているわけです。

ただ、今のトレンドとしては、人が行かないところにいち早く行きたい人たちがたくさんいます。先ほど言ったデスティネーションレストランというのは本当に山奥にあるんですね。
富山のL’evoというフレンチレストランは、本当に富山から車でしか行けない、車で1時間半以上かかるところにあります。利賀村という、今南砺市の一部で、人口は400人もいない、観光も何もないところです。そこにL’evoの料理を楽しみに世界中からお客さんが年間8,000人来ます。8,000人のうちの1,000人はインバウンドです。1,000人というと毎日3人も来ていることになります。今はネットが発達したことで、L’evoという美味しいレストランが富山の田舎にあるらしいと、世界の人は多分金沢も富山もL’evoも一緒だと思っていると思うので、そこに行ってみようかと思うのでしょう。とにかく地方の美味しいものの情報が世界中から取れることで地方のレストランが経済的に潤うようになったというのが1つ大きい点だと思います。
じゃあL’evoがなぜそんな田舎にできたのかというと、やはりそこの周囲に生産者がいるからなんですね。L’evoの場合だと、裏山に行けばおいしい山菜がありキノコがあり、そこに住んでいる漁師さんが獲るジビエがおいしいし水も当然おいしい。こういう場所で自分は料理をやりたいとシェフの谷口英司さんは思ったと言います。生産者との連携をローカルガストロノミーというのですが、シェフも農家さんも単体でいるわけではなくて、そこの人達がみんなで手を携わって美味しいものを作っている。そういうところに行けば、地方の美味しさがすごくわかるよね、という時代なんだろうなと思うんです。
つまり、地方に魅力あるレストランが1軒でもあれば、人はその地を訪れる。それによって周辺が得られる経済効果は思いのほか大きい。これはデスティネーションレストランアワードからちょっとお借りした言葉で、本当に私も実感するんですけど、L’evoは本当にド田舎にあるんですけど、そこに魅力ある店が1軒あれば8,000人の人が訪れます。しかも経済効果は大きいんです。
こんなことがありました。L’evoに行って料理にすごく感動した外国人の方が、この料理誰が作ったんですか? 紹介してください、と言って生産者を紹介してもらってL’evoに食材を入れている人のお米で今アメリカの西海岸でお寿司が作られたり、L’evoの器は全部富山の器なんですけど、この器は素晴らしい、世界中に輸出したいと言って世界に輸出されたりしています。L’evoと取引することによって、L’evoが利賀村に移ったのが2020年の終わりなので5年ぐらいの間にもう売り上げが5倍とか10倍になった生産者がたくさんいるんですね。ですから、その周辺が得られる経済効果は大きいというのはその通りなんです。
それだけではなくて、せっかくL’evoに行ったんだったら他も回ろうよとなり、冬だったら富山はぶりが美味しいよね。氷見っていうところに行こうよとか、金沢に行こうかとか。滑川っていうところはホタルイカが美味しいらしいしほたるいかニュージアムがあるから行こうかといった形で、目に見える形で観光というところで点が線になり、線が面になるという効果が出てくるというふうに私は思っているところです。
そしてジャパンタイムズのデスティネーションレストランリストを見ていただくと、世界と日本で点が付いているところ、5年で毎年10件ずつデスティネーションレストランを表彰して50件、北海道から沖縄の先まで地方にこんなにたくさんいいレストランがあるのかと思います。すごいなと思うのは、デスティネーションレストランアワードを選ぶ基準ですね。都内23区と政令指定都市は外します。本当に地方にあって頑張っているお店しか選ばないんです。
私のよく知っている中華のシェフが仙台に住んでいるんですが、審査員の人が、仙台は政令指定都市だから選べないんだよね。どこか田舎に行かない?って言ってたら、それが原因かわかりませんが先月政令指定都市でない気仙沼に行っちゃいました。今年は、少なくとも対象にはなるかなと思っています。
これはL’evoの写真です。

地図を見ていただくとわかりますが、本当に山奥にあります。富山はやっぱりジビエとか野菜、でも魚がおいしいので、頑張って2時間かけて山を下りて魚を獲ってくるんです。
オーベルジュとして3部屋泊まるところがあるんですけど、泊まった翌日に出てくる朝食がすごい。私も一度行きましたけど、L’evoの料理が美味しいのは当たり前なので、そういう意味では全部美味しかったんですけど、一番びっくりして美味しかったのが、大豆を通常の3倍ぐらい使った利賀豆腐、堅豆腐という硬い豆腐がすごく美味しくて。東京にわざわざ寄って三丁買って帰ってきました。

L’evoに行こうと思って行ったんだけれども、一番印象に残ったのは実は豆腐だった、というのが、多分旅の面白さ、地方の食の面白さだろうなというふうに私は思っています。
そんな魅力的なデスティネーションレストランがどんなところにあるのかというのを今日はお伝えしたいんですけど、ちょっとどんな人たちがデスティネーションレストランを作ってるんですかというのを考えてみると、私はよく”ヘンタイ”と言うんですが、圧倒的にヘンタイなシェフがいるところですね。圧倒的にヘンタイなシェフがいる地域に魅力的なデスティネーションレストランがあると思っています。
さっき言ったL’evo、それから照寿司。照寿司は政令指定都市の北九州市にあるんですが、ただの飲み放題付き5,000円の宴会で持っていた寿司屋を3代目の大将がもっといいものにしたいと言って、カウンターから作り直して頑張ってやったんです。もともと客が5,000円の寿司でいいっていう客ですから、全然彼の寿司に目もくれなかったんですね。
ところが九州大学医学部のネットワークに引っかかってですね、照寿司うまいじゃん、とそこから少しずつ発見されて、するとインスタの時代なので、大将ちょっと太ってて目が可愛いけど睨むと怖いから、メガネを外してこう睨んで、ここに寿司でも出せよって言われてそのとおりに写真を撮ったらインスタでバズってですね。本当に企業城下町の普通の町寿司が、今やサウジアラビアに支店があったり、ついこの間はウズベキスタンかな? で握ったりとか、そんな寿司屋になりました。世界中で一番インスタのフォロワーがいる寿司屋。そんなところがデスティネーションレストランになっています。
ただ、これまでシェフのことばかり言ってきましたけど、ヘンタイはシェフでなくてもいいんですね。例えば静岡にはサスエ前田魚店という魚屋さんがいるんですけど、そこの前田さんの魚の締め方、目利きが素晴らしいと言われていて、前田さんの魚を使いたいばかりに広島から移住したレストランもあります。その移住したレストランも素晴らしいので、やはり世界中からお客さんが来るようになっています。
そんなふうに、ヘンタイがいるローカルガストロノミーには素敵なレストランがあり、素敵なガストロノミーが存在します。ただ、ヘンタイってそうそこら中にはいない。なら合わせ技で呼ぼうよと、地域においしいところがたくさんあったらそれはそれで楽しめる、行くに値する場所だよね、というふうに思っています。
例えば丹後半島に飯尾醸造という、この人もヘンタイと言えばそうなんですけど、お酢屋さんがあるんですね。彼を含めて丹後半島を食の街にしよう、食の地域にしよう。ここにいらっしゃる方はご存知かもしれませんが、スペインにサン・セバスチャンという、世界で一番美食での町おこしに成功した土地があるんですけど、丹後半島をサン・セバスチャンにしようと言っていろんな活動をしています。中心にいるのは京丹後市の縄屋さんという日本料理の料理人です。彼もやはり京丹後で生まれ育ち、一度京都に行って和久傳というすごく有名な料亭で修行したんですけど、いや和久傳の魚より俺が食べていた京丹後の魚の方がうまいねって言って京丹後に戻ってきた。彼が年に何度か、営業が終わった後11時ぐらいから皆で飲む会をやっていて、私も1回お邪魔してご一緒させていただいたことがあるんですけど、東京だと新宿の焼き肉屋に夜11時半集合って来れますけど、京丹後に夜11時半集合ってなかなか来れないのに20人ぐらい集まるんですよね。みんなで談義をしながら、そしてジャンルの違う料理屋さん同士が教え合うんですよ。面白いなあと思ったのは、天橋立がある宮津町というところにポルトガル人がオーナーの寿司屋さんがあって、そのポルトガル人は寿司が大好きで寿司屋を開いちゃったんですけど、まだまだ日本の魚を知らないと言っていたら、京丹後で料理旅館をやっている料理長が、カニのさばき方、京丹後には間人ガニという有名なズワイガニがありますけど、それをどう捌いてどう料理したら美味しいのかを教えているんですね。
そういうようなコミュニティが存在するというのが合わせ技の面白さだなというふうに思っています。そういうところはたくさんあると思っていて、今私が個人的に推しているのは紀伊半島美食街道です。紀伊半島は伊勢神宮、熊野大社、高野山といった素晴らしいところがあるんですけど、紀伊半島自体が大きくて交通の便が悪いので、なかなかつながらないんですね。だけど、1つ1つに美味しいものがある。これを巡る紀伊半島美食街道って作れないかなと思って、三重県や和歌山県、奈良県と一緒にできないかな? なんて話をしたりしているところです。
このようにうまくいった例をいくつか時間が許す限りご紹介できればと思います。先ほどのアル・ケッチァーノの鶴岡は、ヘンタイシェフの奥田さんが2000年にアル・ケッチァーノを作りました。2000年というとL’evoができる20年前です。彼も鶴岡の出身でやはり都会に出て行って戻ってきて、やっぱり鶴岡は美味しいよね、こんなところをもっと知ってもらいたい、と言って始めました。鶴岡は本当に何もないところだったそうで、そこでイタリアンを始めるというのはかなり無謀だと、皆に大丈夫かと言われたんですが、彼の志に共鳴する人たちがたくさん付いてきて、鶴岡はもともといろいろな郷土料理があるところですからそれがいい形で外に出てきた。奥田シェフが情熱大陸に出たりとかいろんなことがあったんですけど、その結果、行政が付いてきたんです。
行政が、こんなに民間が頑張っているんだったら鶴岡を食の街で売ろうよと。では行政は何ができますか? 食文化創造都市というのがユネスコにあるんですけど、まだ日本は1つも認定されていない。認定されるには行政が一緒にやってくれないとなかなかできないからやりましょう、と言って頑張って、2014年に食文化創造都市に認定されました。そこから鶴岡は、世界中から食文化のある都市だと認定されたわけですね。
もともとインバウンドの方は日本に観光に来ると、いわゆるゴールデンルートと言われる東京から大阪にまず行くわけですけど、東北には行かないんです。東北ってだいたい5回以上日本に来ているインバウンドが初めて考えるところだと言われています。でも5回も来たということは、日本面白いよね。日本って素晴らしいよねって思っているわけです。
札幌に行ったけど、そういえば札幌の手前に東北っていう空白地帯があるよね、今度東北へ行ってみようかとなった時に、東北のどこに行けばいいのかな、そうだユネスコが言っている食文化創造都市の鶴岡があるじゃないかと。そうして鶴岡にたくさんインバウンドが押し寄せて、すると観光都市としてさらに発展していくという形で、民間と行政がいい形にタッグを組めています。しかもここにサスティナ鶴岡という、先ほどの丹後半島のようなコミュニティができている。そうすると若いシェフ達、若い生産者達がどんどん育っていくわけです。

東京の近く、関東にも、デスティネーションレストランの本当に先駆けと言われている人がいます。宇都宮にあるオトワレストランの、1970年代にアラン・シャペルという、当時、巨人のようなフランスの素晴らしいシェフのもとで修業をした音羽和紀シェフです。
ミシュランガイドってもちろんパリのレストランにたくさん星が付いているんですが、地方にも美味しい店があって星が付いているんですね。アラン・シャペルももちろん3つ星のレストランなんですが、そこに来るシェフたちは皆、おらが村の自慢ばっかりするわけです。「アラン・シャペルで修業した俺は人口300人の村に帰ってそこに3つ星レストランを作るんだ」と。
音羽さんは、日本人は皆、地方にいるとかっこ悪いと思って東京に出てそれからフランスに行くのに、なんで地方の自慢をするのかなと思っていたんだけど、彼らの話を聞いていると、そりゃそうだよね、と腑に落ちたそうです。
地方の方が美味しいものがあるんだからその美味しいものを使って料理を作れば東京から人が来るよね、と言って、1981年、アル・ケッチァーノのさらに20年前にオトワレストラン、正確には前身のオーベルジュという名前のレストランを作って、彼はまだお元気でそこから50年ぐらい経つんですけど、50年じゃ地方に美味しいものを作れないな、やっぱり子供や孫に引き継ぎたい、別に俺の職業を継げとは言わないけど背中で見せたいよね、と言った結果、息子さんたちが全員オトワレストランに戻ってきて、お嬢さんも帰ってきて、全員でローカルビジネス、ファミリービジネスをやっています。宇都宮から車で10分ぐらいですね。宇都宮は観光的要素としては何せ餃子の街ですから、餃子の街とフレンチ、なかなか相容れないと思われるんですけど、ここも素晴らしいと思います。
次に新潟。新潟も魚と米が美味しいんですけど、なかなかここも1つ1つおいしいレストランがあるだろうと思いながらあまり発見されてなかった街で、これもやはり1人のヘンタイが出てきまして、岩佐十良さん、里山十条という旅館をやっている方ですね。この方は東京から来たので、外からの視点を持っているから、新潟は素晴らしいものがあるのに全然発見されてないよね、認知されていないよね、ということで新潟ガストロノミーアワードというのを作って、しかも審査員には東京の食いしん坊の人たちを呼んできたんですね。
そうすると、田舎っていろいろしがらみがあるじゃないですか。例えば、町の共同組合に入ってないアイツはいいや、っていうようにのけ者にするところって結構あったらしいですね。でもそういう変なやつほど情熱があって変な料理を作る。東京から審査に来ている人たちにとっては変であろうとなんだろうと美味しければいいわけです。じゃあ、この店すごいよねって言うと、これも地方のあるあるですけど、いやいやあの店はやめておいた方がいいよと言われたりするんですが、岩佐さんは、文句があったら自分に言ってこい。なんとかするから、と言ってくれて、その結果、これまで全然出てこなかった素晴らしいお店が発見されていって、新潟っていうのはすごく美味しいレストランがたくさんある県であると認知されて、日本中から視察に来るようになっています。
あと富山。富山は2年ほど前に県知事が、寿司といえば富山、になりたい、10年後に寿司と言えば何県と言われたら富山県と言われたい、と言い出したんですね。私は祖父が富山で私も富山には行っていてよく知っているのですが、知事には、それ無理ですよ、この近くだったらやはり金沢でしょう、富山が美味しいのはわかりますけどだいたい魚の美味しいところってなかなか技術の研鑽をしないので富山の寿司って野暮ったいでしょう、ちょっと無理だと思います、と申し上げたんです。
でも、いややりたいんだと言う。知事は気さくで腰が軽い方なので、若い人たちが皆じゃあちょっと頑張ろうかと言ってはじめました。富山の寿司って、まあ楽しいんですよ。散々美味しい魚と日本酒を飲んで最後に4、5貫食べていくらっていうと5,000円とか6,000円と言われて、いや、これすごく楽しいねと。美味しいって言うより楽しいねと思うんですけど、でもそのために3万円かけて東京から行かないじゃないですか。ということでまずは、3万円かけても美味しい寿司屋がきっと富山にあるはずだと思って2年間かけて寿司屋を回ったんです。そしたらちゃんとあるんですよね。やっぱり寿司といえば富山、っていけるんじゃないかなというふうに思ったりもしました。

その富山の寿司を見習って、これも同時多発的な話なんですが、北九州市の市長がすしの都課っていうのを北九州市に作っちゃって、やはり北九州も寿司で盛り立てたいと。彼ら北九州市は福岡市をすごくライバル視していて、福岡市は玄界灘しかないよねと。うちは玄界灘も響灘も周防灘もあるよと。魚種もたくさんあるよと。しかもそれだけじゃなくて技術がすごい。彼らは白身に圧倒的な自信を持っていて、白身って醤油で食べると皆同じになっちゃうよねと言う。特に九州の白身は、あの甘い醤油で白身の味が消されちゃうよね、ということで、小倉では柑橘と塩で食べる「小倉前」という食べ方ができたんですね。これを北九州で広めようよということを言い出して、先行する富山と連携してこの8月に連携協定を結んで、富山から北九州に通じる寿司のゴールデンルートを作ろうという話をしたりしています。

そんなふうに今、実は地方にたくさんレストランがあります。とりあえず1県につき1つ、こんなところが美味しいというのをスライドにして挙げてみました。北海道から沖縄まで、ほぼ私が行ったところばかりです。
1店、岡山のsowaiだけは行ってないですど。sowaiは多分これもヘンタイで、このネットの時代にハガキでしか予約できないんです。だから届いているかどうかわからない。きっとヘンタイだと思います。だから近々行きたいなと思っているところです。
じゃあ、日本にそんな素敵なデスティネーションレストランってどれぐらいあるの? ということで数えてみて、まあ500件ぐらいか、もうちょっとあるかな、それぐらい今、日本って素晴らしいレストランがあると思います。食の熱中は決してファインダイニングと呼ばれるすごく高くて高級なレストランに行くツアーではないですけど、ツアーで地方に行くとそこの食材を一番よく知っているシェフのいるレストランにみなさんと行こうと思っています。
この間糸魚川に行った時にはムリールという、お米で表現をするフランス料理屋さんに行ったりしました。十勝に行った時はマリヨンヌという、横丁から誕生したビストロに行ったりしています。そんなふうに食の熱中というのは、食を使って地方を盛り立てている人たちを応援しようという学校です。
宣伝になりますけれども、食の熱中はこれから5期が始まりますので、ぜひ5期にいらしてください。さらにちょっと2つほどプライベートの宣伝をさせていただきます。さっきから言っているように地方に必要なのはデスティネーションレストランとローカルガストノミーの結合なんですね。で、今なぜ地方にレストランがたくさんあるのか、できているのかというと、これまで首都圏への食材供給基地だったところが、わざわざ訪れる魅力的な地域になろうとしているということなんだと思います。特に関東近郊がそうですが、栃木とか茨城とか、食材だけを東京に持ってきていたのが、逆にそこにレストランがあればもっと何倍もお金が取れてわざわざ東京から来るよね、そういうレストランを作ろうよ、というのがデスティネーションレストランの1つの動きだろうなと思っています。
食熱はどこに向かうのかと言うと、デスティネーションレストランを核にしたツアーを作る、またこの先、生徒さんにもツアーを企画していただきたいなと思っています。そして食熱のツアーが楽しいということで、首長や議会、もっと言えば国も巻き込むような楽しいものにしたいと思っているところです。

そして私、来月10月29日に『日本人の9割は知らない 世界の富裕層は何を食べているのか? ガストロノミーツーリズムの最前線』という本を出します。ビジネスの得意なダイヤモンド社の出版なのでちょっとおどろおどろしいタイトルなんですけれども、この本文の中で紹介しているお店を含めて200ぐらいのレストランのリストが本に載っていて、さらに言うと、この本をお買い上げいただくと450店アクセスできるという特典を用意しております。ぜひぜひ、よろしくお願いします。Amazonで予約できます。
実はもう1つ、宣伝があるんですが、BS11で10月19日に「柏原光太郎の食紀行」という特番をやります。これ、食の熱中で仲良くなった糸魚川、先ほど東洋ライスの江原さんが話をした糸魚川を訪ねるツアーがこの特番です。大の里の海洋高校にも行きます。以前海洋高校に行ったときはポスト大の里の若い学生達にたくさん会ってきました。とっても皆さん素直で楽しい。こういうのがやっぱり食のつながりだなというふうに思うところです。
というわけで、私の宣伝はこれで終わりですけど、食の熱中、とにかく楽しいツアーです。ですから皆さん、ぜひ食の熱中に参加いただいて、それで食の熱中ツアーは全国各地の熱中小学校にも参ります。来月は16番目のシアトルにも参ります。ですからそうやって全国各地の熱中小学校を巻き込んで、熱中学園を楽しく面白い場所にしていきたいなと思っております。
どうもありがとうございました。
クロージング挨拶 大久保昇 株式会社内田洋行代表取締役社長
一般社団法人熱中学園理事

参加された皆様、内田洋行ユビキタス協創広場CANVASにご来社いただきありがとうございます、私は「熱中小学校」では理科の教諭として全国各地を回りましたが、東京での「食の熱中小学校」では正式な生徒です。今日もしっかりと学ばせていただきました。ただ、生徒になれば参加できる食のツアーは、行きたくても仕事の関係で日程的に参加が叶いません。それで参加した方に素晴らしかった場所をお伺いし、夏休みなどに幾つかの地区の食を選んで堪能している次第です。本当に美味しかったです。
さて、私は日本の将来を心配する多くの人の1人です。私が内田洋行に入社したのははるか昔。高度成長は過ぎていましたが、毎年成長をするのがその頃は当たり前でした。その後日本はバブル期に突入します。夜遅くまで飲んだらタクシーは一切捕まらない乱痴気騒ぎの時期を経てバブルはその名の通り破裂。これからは虚業より実業だ、汗を流す製造や流通業で安定した成長で日本は復活するぞと個人的には期待したのですが、残念ながら長い停滞の空白の20年が続きます。しかもバブルがはじけても東京だけは成長を続き、残りの全国各地は成長が止まりました。人が東京の一極集中になり、人が少なくなった地方の苦境が強くなります。挙句の果てはリーマンショック。米国に端を発したのに日本は米国以上の落ち込みになり、地方に追い打ちをかけたのです。
現在、経済は漸く上向きになり、なんとか自動車産業と一部の素材産業は今でも世界での強さを維持していますが、過去には圧倒的に強かった半導体から電気製品などの多くの製造業は皆厳しくなってしまった。残念ながら地方に多様な工場が戻ることはもう無理なのです。
しかし、日本には観光があるぞ。おもてなしの心とまだまだ未開拓な観光地がある。そこに滞在する観光客を増やし、多くの美食を味わう機会を設ける。観光は一時でも食材はそれ以降遠くからでもリピート購入できる。だから日本はもう「観光」と「食」、特に継続する「全国の食文化」で将来は稼いでいくしかない、とリーマンの痛手が残る頃に私は確信した次第です。
先ほどの柏原校長の講演では、私は美食の場所をメモしながらもしっかり計算をしておりました。自動車産業の輸出は全部で18兆円ですが、日本へのインバウンドが4000万人で8兆円分の輸出になるくらいに成長しました。フランスは人口の1.5倍の海外からの観光客が来ている。日本は、人口が1億2000万人とするとまだわずか人口の3分の1です。目標が人口と同じとしても3倍はいける。皆さん計算してください。8兆円の3倍の24兆円で、これからの増加額は16兆円。要はトランプ関税で悩む自動車の代替産業にもなるのです。こういうことですから、日本の地方と日本全体が、元気を出すためにも「食の熱中」をもっともっと発展させましょう。しかも今回ジャパンタイムズ様から表彰を受けたということは、これからは英字でも全世界に発信されるわけです。
最後に理事としてのお願いです。今は次期の入学募集期間です。「食の熱中小学校」を必ず継続していただき、さらに仲間を募りましょう。ユニークな地方の食のツアーに参加し、地方の皆さんと共に、世界に誇れる食の旅を開発しましょう。 ご参加ありがとうございました!

今回のアワードの受賞理由(The Japan Times Webサイトより):
2015年には地方創生交付金を活用してプロジェクトを始動し、現在までに国内15地域と米国シアトルを含む16地域で展開。リスキリングや人材育成、起業支援や移住促進を実現し、教育と地域振興を融合させた先進モデルです。少子化で廃校となった校舎を再生し、多世代・多職種が交流する学びと地域再生の場を構築。受講者は経営者から農業従事者、主婦まで幅広く、異業種・異世代の出会いから新たな事業や活動が生まれています。さらに北海道から九州まで広がる分校は、地域ごとの特色を活かしつつ理念を共有し、「*里山プラットフォーム」として展開。地域資源や文化の発信力を高めています。地域の文化や特産品を取り入れることで、外部からの参加者にも地域の魅力を伝え、単なる学習にとどまらず地域課題の解決や新しい事業のきっかけづくりにもつながっています。人と地域をつなぎ直す“社会教育+地域再生”モデルであり、持続可能な地域づくりに資する取り組みとして高く評価されました。
第5期 申し込み受付中! 2025年10月20日(月)まで
申し込みは:https://peatix.com/event/4515187


「食熱通信特別号 no.1」発行:食の熱中小学校事務局(一般社団法人熱中学園内)
公式サイト:https://shoku-no-necchu.com/

Mail to:hello@shoku-no-necchu.com