前章では水谷豊さんと時沢小学校とのご縁について書いたが、この学校との出会いにはたくさんの偶然と出会いがあった。
佐藤理事長と私が最初に役場の方と尋ねたのは、高畠駅に近い中学校だった。中学校の統廃合の計画作成の過程だったそうなのだが、まだ使われていて生徒さんがいる日だった。この学校は鉄筋コンクリートで大きく、利用のイメージが湧かなかった。廃校再生が部分的なものでは失敗するという直感があったので、私の力では無理ですとお断りした。すると、すかさず当時の高畠町の企画財政課長の斎藤さんが、駅から遠くて不便なところですが、小さい学校もあります、と役場に連絡して、雪かきを指示して我々を連れて行った。これが旧時沢小学校だった。

閉校になって4年、雪の中の学校は恐ろしいほど寒い。温泉か、熱燗か、どっちか連れてってください。。そして熱燗が進んで行くうちに、何か考えてみましょうということになった。これが初対面の役場の役場幹部さん達との運命の雪の日だった。
もう1つの話は、初代の校長、教頭決定の話をしよう。
先生の選定は任せていただいたが、佐藤理事長は起業人材の育成を目的の一つとされていたので、日本アイ・ビー・エムの後輩営業に、ベンチャー業界の人材を何人か紹介いただいた。その1人がNTT東日本を退職してスペースマーケットというシェアビジネスを始めていた、重松大輔さん。
初対面で趣旨を話したら、なんとあっさりと「私でよろしかったら、ぜひ」と言っていただいた。あとで、お父様が学校の先生で、親父より早く校長になった、と笑って話をされたことがある。
教頭は私が日本アイ・ビー・エム時代に補佐をやってくれた、玉川憲さん。ソラコムというベンチャーの立ち上げ直前だった。お二人とも20歳前後で、この学校を25年廃校としないためには若い校長、教頭で開始したいという思いがあった。
2人の会社は今や上場し、業界でもリーダーとして大活躍している。2人が素晴らしいものを持っていて直感が働いたご縁とはいえ、時沢小学校には何か再生をしてくれた人たちに恩返しするものを持っていると思いたい。
3つ目は、当時から学校のすぐ後ろにある、フレンチレストラン、フレール・ドュ・ソレイユについても書いておこう。山形市あたりからも食べにくる隠れ家的なレストラン(今で言うデスティネーションレストラン)の存在は大きかった。先生とランチを食べたり、始業式などにパーティに使ったり、10年のお付き合いで、今回も懇親会にいろいろ作っていただいた。時沢まで来るのが楽しくなり、私はいつも必ずマスターに挨拶に寄っていたものだ。
― 高畠熱中小学校10周年記念式典でのスピーチから ー

本日は、高梨忠博高畠町長様、内田洋行大久保昇社長様そして倉崎憲先生、開沼博先生に記念講演をしていただき、小寺雅仁さん、横山寿一さん、齊藤壽江さん、池田めぐみさん4人の生徒さんのプレゼンテーションを楽しく聞かせていただき感謝申し上げます。高畠熱中小学校の生徒さんと事務局がかなり前から準備をされたと聞いています。
佐藤理事長から高畠熱中小学校は、廃校の活用と地域人材の育成にあるという明快なお話がありました。今日の生徒さんのお話はそのどちらも成果を上げているということを感じました。
佐藤理事長とこの旧時沢小学校の廃校を見学したのは大雪の11年前の年末のことでした。当時の役場の斎藤利明企画財政課長、金子昭一課長代理、八巻祐一係長様と杯を重ねるうちに、いったん廃校になった学校を大人の学校として再開校すること、それも高畠町のみではなく、置賜や県外からも多様な人の参加がある大人の学校として、我が国で初めての廃校利用という企画にすることに決まりました。翌年すぐに近くの公民館で、旧時沢小学校に通っていた住民の皆様に説明会をいたしました。その時後ろの方におられた現教頭の宮原先生の拍手を皮切りに皆さんに拍手いただいて、今日があります。国はちょうど石破さんが初代の地方創成大臣になり、地方創成交付金を始めたときで、このプロジェクトが内閣府の山崎史郎地方創成総括官の目に留まり、やがて学校は、村も、町も、市も対等に参加できる、ユニークな「ボランティアの先生をシェアできる独立自営の教育ネットワーク」を全国に広げていきました。廃校だったこの学校の窓を開き、片付けを始めたところ、つがいの燕が入ってきて階段や廊下をひらりひらりと飛び回りました。何かとても幸先がいいな、と思いました。
本日、倉崎憲さんは公演中感動されて、少し涙ぐまれました。実はもう1人、この体育館で行われたオープンスクール講師で涙をこらえた講師を見ました。当時の山崎史郎内閣府地方創生総括官には最初のオープンスクールの講師をこの体育館でやっていただきました。この体育館の空気を入れるために上の窓を開けていましたが、その燕のつがいが入って来て天井で止まって参加していました。私はいつ観客の頭に糞が落ちないか、気が気でなくて燕を見ていたところ、突然山崎さんの声が止まり、舞台を見ると涙をこらえておられました。山崎さんは東日本大震災の時、首相補佐官として目のあたりにした我が国の放射能汚染の絶体絶命の危機を思い出されたようでした。山崎さんは地方創成総括官の後リトアニア大使になられ、そして帰国後は少子化問題の内閣参与として我が国の将来のために邁進されています。ここのところの政治の流動化で当分は東京を開けられないとのことで、今日は来られなかったのですが、懐かしい皆さんによろしくと、事づかってまいりました。
学校は、やがて仙道富士郎元山形大学学長を通じて田中敦准教授や古川英光教授の研究室を理科室として3Dプリンターの教室を支援いただき、鉄道研究会とも連携し、高畠ワイナリーの村上健社長を始め、高畠の実業界とも接点を持ち現在に至っております。役場、大学、民間企業という応援団が揃っている環境は素晴らしいと思います。2階の6つの教室と図書室には起業されたさまざまな方が住居して、普通の学校より少し広めの廊下に鉄道模型製作の好きな内海弦現校長の心をとらえて自腹で鉄道模型つくりをされて校舎と共に学校が進化し続けた10年でした。
オープンスクールで使われたこの体育館で開かれた、2015年10月の入学式では、樹齢20年以上のきめの細かい金山杉を材料にして、‘午前中に自分が座る椅子を作らないとこの体育館で午後入学式ができないぞ!’ と驚かせて、無事84個の椅子が時間内に完成し、第一期生の名前を彫って、今でも現役の生徒さんが使っています。
熱中小学校のロゴマークは1期からの図工の前田一樹先生(残念ながらお亡くなりになり現在は田中裕子さんに継いでいただいていますが)にボランティで作っていただいたものです。ロゴマークは上が駒、下がセロテープで、よく遊びよく学び、つまり楽しい遊びを上にして、9つのパーツは小学校の教科を現したもので、全国共通です。
ここから国道113号線で1時間半ほどの宮城県丸森町で2019年発生した台風19号からの復興を支援すべく計画された熱中小学校丸森復興分校は、たくさんの高畠の生徒さんの支援で開校にこぎつけました。そして宮城県美里町で来年4月の開校準備をしています。本日は教頭先生で有名なサックスプレイヤーである名雪祥代さんが来られています。懇親会での演奏が楽しみです。オープンスクールには原田英男先生と私も参加して東北で3校目の開校を支援しますが、高畠の皆様にはぜひリードして欲しいとお願いします。
経営環境が異なる全国の自立独立した学校を継続するのはそれぞれ至難のことですが、これまでに6つの学校が7周年を迎えました。新たに2年前東京に「食の熱中小学校」が開校し、昨年4月に「ちば銚子熱中小学校」がいったん廃校になった後に再開校しました。
さて、このプロジェクトは先月ジャパンタイムズ主催のJapan Sustainable Award 2025 で表彰されました。これに励みに、持続可能な日本は「学びの力で地方から生まれる」ということを私たちはさらに試行錯誤しながら進めてまいります。しかしながら、熱中小学校の持続可能性はとても困難です。廃校になった地域もあります。役場、大学、民間企業が広域でこの学校を見守っていただき、今日の生徒さんのような思いと熱量のこもった学校として、この校舎と共に進化を続けていただきたいと思います。
情報があふれる今、全員がスマホで情報を作り出している時代では、「何を先生から学ぶか」から「誰と学ぶか」忙しい中で「どんな人たちと時間を共有するか」を大切にお互いに成長し、励まし合っていく時代になりました。それをスマホの仲間以外に、熱量で交流するリアルな学びの場の重要性は増しています。
この大変僭越ですが、この高畠を、東北を、日本を「学びを大切にする人と地域は繁栄する」を信念として皆様としっかりと歩いてゆきたいと思います。
今年、内田洋行様の115周年記念事業として協賛いただき、能登半島の復興支援を行っています。お配りしたチラシのように、毎月熱中の先生が能登について学び、能登の方と授業を創ってきました。私たちのテーマ、創造的復興とは? 能登でできること、成果を上げたことを日本の復興のために役立つ手法を学ぶことです。最後になりましたが、私、佐藤理事長の下でNPOはじまりの学校の理事でもあります。来月から始まる第21期にたくさんの皆様が入学、継続してただき熱中小学校プロジェクトを是非トップランナーとしてリードし続けてください。それをお願いしてクロージングの挨拶といたします。
そして懇親会! クロージング挨拶をする宮原教頭、講師の倉崎憲さん、サックスを吹かれた名雪祥代さんと記念撮影!


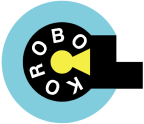

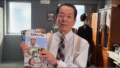
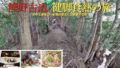
コメント