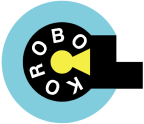講 師 蒲原 亮平先生(蒲原水産 代表取締役社長)
講 師 南谷 良枝先生 (南谷良枝商店 店主)
モデレーター: 堀田 一芙先生(一般社団法人 熱中学園代表理事)
会 場 : 熱中小学校白老分校(しらおい創造空間「蔵」)
日 時 : 2025年12月13日(土) 13時15分〜14時30分
レポート作成 「のと熱中授業」モデレーター 吉沢隆
1. 南谷良枝先生 講演レポート ―― 輪島朝市とともに生きてきた私のこれまで、そしてこれから ――
※このレポートは先生の情感あふれるお話をお伝えするため原文に近い形で作成しています。

こんにちは。
石川県輪島市から来ました、南谷良枝商店の南谷良枝です。
私は十七歳のときに、この商売の世界に入りました。行商をしていた祖母から魚の加工や商いの技術を学び、三十年近く輪島朝市に店を構えてきました。早朝から夜遅くまで続く厳しい仕事でしたが、「おいしいね」「ここのじゃないとだめなんだよ」と言っていただけるお客様の声が、私の支えでした。
商売は生活の糧であると同時に、私自身の生きがいでした。
娘も後継者として加わり、売上も少しずつ伸び、さあこれから、という時に、あの能登半島地震が起きました。
元旦、突然奪われた日常
地震が起きた元旦、私は家族と初詣に出かけ、輪島から離れた場所にいました。帰り道、突然鳴った緊急地震速報。その直後、車がジェットコースターのように揺れ始めました。
道路沿いの家々の瓦が落ち、壁が崩れ、目の前で街が壊れていく。何が起きているのか理解できず、「北朝鮮から爆弾が落ちた」と本気で思ったほどです。

津波警報が鳴り響く中、土地勘のない場所で高台を探し回りました。いつ津波が来るかわからない恐怖で、体が震えたのを今でもはっきり覚えています。
ようやく避難できる場所を見つけ、車中泊をしました。ガソリンを満タンにしていたことが、あの夜どれほど心強かったか。エンジンを切れず、凍りついた車の中で夜を越した方も大勢いました。
燃えゆく輪島朝市、助けられなかった命
車のテレビに映ったのは、燃え始める輪島朝市の映像でした。
その時、主人の携帯に電話が入りました。「朝市の店にいるけど、地震で戸が挟まって外に出られない。助けてくれ」。
けれど、私たちは輪島にいない。助けに行くことができない。電話は途中で切れ、その後はもう繋がりませんでした。
テレビでは火が広がり、その店も燃えてしまいました。
助けられなかったという苦しさと無力感の中で、燃え落ちていく朝市を見つめながら、一睡もできない夜を過ごしました。
失われた加工場と「もう終わった」という思い
翌日、崖崩れや通行止めを避けながら、何時間もかけて輪島へ戻りました。
自宅にたどり着いたとき、母が生きていてくれた。その姿を見た瞬間、涙が止まりませんでした。

被害を確認して、言葉を失いました。
商売の命だった加工場は半壊。倉庫は全壊。そして、家族みんなで仕込んできた輪島の誇り、魚醤「いしる」の樽が割れ、八トンから九トンもの汁が地面に流れ出していました。
その光景を見た瞬間、私は膝から崩れ落ちました。
「もう終わった」
全てが消えてしまったと感じました。
出張輪島朝市、そして未来へ
それでも、被災者だからといって、立ち止まっているわけにはいきませんでした。
生活は続きます。社員のお給料も払わなければならない。家族も守らなければならない。
「生きるために、今できることをやろう」
そう自分に言い聞かせながら、車を二台売って資金を作り、仕事を探し始めました。
輪島の運送会社も被災し、全国発送ができない。
「じゃあ、能登の外でやるしかない」
そう考えて、富山県砺波市の友人に相談すると、「うちの会社の一角を使っていいよ」と言ってくれました。その言葉に、どれほど救われたかわかりません。
そこで、冷凍のガスエビやアマエビ、茹でガニなどを販売し、全国へ送り続けました。そんなある日、避難生活をしている朝市のおばちゃんたちとLINEで話していた時のことです。
「このまま家におったら、私らボケてしまうわ」
「何か仕事せんと、体も心も動かん」
そんな声が次々に上がりました。
すると、誰かがこう言ったんです。
「私ら、包丁一本あれば、どこでも商売できるがいね」
その言葉を聞いた瞬間、胸の奥が熱くなりました。
「そうや。私らは朝市のおばちゃんや」
「だったら、輪島に戻れんでも、外で朝市をやればいい」
そうして生まれたのが、「出張輪島朝市」でした。私も、その発起人の一人として動き出しました。
第一回出張輪島朝市イン金岩が最初の一歩でした。建設会社の社長さんをはじめ、商工会や婦人会、地域の皆さんが信じられないほどの協力をしてくださいました。

「テントはこっちで用意する」
「朝市のおばちゃんたちが来るなら、町をあげて迎えるわ」
その一つ一つの言葉に、何度も胸がいっぱいになりました。
当日、会場には一万二千人ものお客様が来てくださいました。
「待っとったよ」
「大変やったね。でも、また会えてよかった」
「輪島の味、忘れられんかったわ」
お客様の笑顔と声を聞いた瞬間、朝市のおばちゃんたちは皆、涙をこらえながら包丁を握っていました。
その日、私は確信しました。
「私たちは、もう一度立ち上がれる」
出張輪島朝市は、私たちにとって商売の場であると同時に、生きる力を取り戻す場所でした。これをきっかけに、私たちは全国各地のイベントに呼んでいただけるようになりました。
こうして、「全国を巡業する輪島朝市」が生まれたのです。
輪島朝市は、必ず戻ります。
令和九年まではワイプラザで、そして海沿いのマリンタウン、大屋根の下へ。
軽トラ市やキッチンカーとも連携し、世代交代を進めながら、震災前よりもパワーアップした朝市を目指しています。
時間はかかります。簡単な道ではありません。
それでも、私たちは輪島で商売できるその日を夢見て、今日いただける一つ一つの仕事を大切に、精一杯生きていきます。
もし、皆さんの地域でイベントがありましたら、ぜひ出張輪島朝市を呼んでください。
また必ず、笑顔でお会いしましょう。
2.蒲原亮平先生 講演レポート
モデレーターの堀田一芙先生は、南谷良枝先生の話を受けて、能登では朝市や温泉といった象徴的な営みが一瞬で失われ、そこで働いていた人が「生活の立て直し」と「仕事の立て直し」を同時に抱えざるを得ない現実をあらためて確認しました。復旧復興は一括りにできず、一人ひとりの状況が違うからこそ難しさがある……その点を会場と共有したうえで、北海道白老町で水産加工に携わる蒲原亮平先生へバトンを渡しました。
「諦めたら、地元が終わってしまう」—— 共通点から始まった話
蒲原先生はまず、南谷先生の話を聞きながら「共通点が3つある」と語りました。
生業を継承すること。そこを土台に地元を再興すること。そして何より、今の世代が諦めてしまえば地域が終わってしまう、という危機感です。
「やっぱりこの我々世代が諦めたら、もう地元が終わってしまうんですね」
人口減少や市場の縮小で地方が “シュリンク”していく中でも、何かをやらなければならない。輪島でも白老でも、全国の各地域でも、30代・40代が踏ん張らなければ、日本全体が同じ方向へ縮んでしまう——そんな問題意識が、導入からはっきり示されました。
虎杖浜という土地と、三代目としての自己紹介

続いて蒲原先生は、自己紹介と虎杖浜の紹介に入りました。
「白老町虎杖浜の有限会社蒲原水産代表の蒲原亮平と申します。今年で40歳になります」
虎杖浜生まれ虎杖浜育ちで、大学などで外に出た期間を除けば、ほぼずっとこの土地で暮らしてきたと言います。祖父の代から水産加工業を始め、ご自身は三代目。ここで先生は、これからのテーマを掲げました。
「最高のタラコ体験ができる町・虎杖浜。これをスローガンとして取り組んでいきたい」
地理の話も生活感がありました。虎杖浜は登別のすぐ隣で、生活圏としても登別側と近い。海が目の前にあり、山も近い。さらに近隣には透明度が高い水をたたえる倶多楽湖があり、そこからの湧水が地域の魅力にもつながっている、という説明が続きます。虎杖浜という場所を「小さな端っこ」と表現しながらも、自然条件の豊かさが印象に残る語りでした。
「2%」の希少性と、“冷凍しない”虎杖浜たらこの価値
虎杖浜では昭和30年頃からたらこ製造が始まりましたが、北海道のたらこ産地としては後発だったそうです。そこで地域として、組合を作り、技術や情報を共有しながら産地としての立ち位置を築いてきたと語られました。
キーワードは「虎杖浜たらこ」です。
蒲原先生は、流通量について「全国の2%ぐらい」と言い、希少性を示しました。さらに味の特徴を、一般的に見かける“大粒でプチプチ”のたらこと対比しながら説明します。
「粒は小さいけど、シルキーな舌触り、サラサラっとした舌触りが特徴です」
そして最大の強みは、漬け込み工程で「一度も冷凍しない」ことでした。
「一度冷凍してしまうと風味が飛んでしまうので、虎杖浜だからできる商品かなと思います」
産地・加工地・漁場が重なる土地の条件が、そのまま“風味”という価値になっている、という話はとても分かりやすく伝わってきました。
直売所、無添加たらこ、そして「8万回のいただきます」

先生の構想は、体験と直結しています。工場の向かいに直売所があり、出来立てのたらこを提供できるのは工場を持つ強みだと言います。さらに塩と水だけで漬けた無添加たらこの話では、思わず笑ってしまうような“正直な表現”もありました。
「色は良くないんですよ。アスファルトみたいな色してるんで……」
見た目よりも、素材と工程の価値を伝えたい、という姿勢がにじみます。
ここから話は、蒲原先生のポリシーへつながります。
「8万回のいただきますをもっと価値あるものに」
人の食事回数は一生でおよそ8万回。上限が決まっているのだから、思い込みや偏った情報だけで食を狭めるのはもったいない。国産か海外産かで単純に切り分けず、生産者の話を聞き、管理体制や背景も含めて味わうと“食が豊かになる”——そんなメッセージが、押し付けにならない言い方で語られました。
解体のはずがレストラン計画に。
講演の後半で語られたのは、来年以降の具体的なプロジェクトです。
工場の隣に老朽化した危険な建物があり、当初は解体して安全を確保するつもりだった。ところが補助金は解体だけでは出ない。そこで“とりあえず”として飲食店計画を書いて申請したところ——
「書いちゃったら通っちゃったんですね。なので、やんなきゃダメになっちゃったんですね」
笑いを誘う言葉の裏に、地域の景観と体験を変える覚悟が見えました。300〜400坪ほどを整備し、来年5月に向けて進める計画。たらこを定番の食べ方だけで終わらせず、もっと楽しみ方を増やしたい、と語ります。
「得意じゃないことやってもしょうがないので、私はこれ1本でやっていきたい」
“タラコ一本勝負”を明確にして、虎杖浜に来る理由そのものを作ろうとしていました。
「離れられない」町で、住んで楽しい未来をつくる
最後に蒲原先生は、虎杖浜だけでなく白老全体の未来にも触れました。各地区で同じように動く人が増えれば、町としての魅力が厚くなる。白老町が好きで、特に虎杖浜が大好きだと語った上で、こう締めます。
「僕が死ぬか、会社が潰れるかじゃない限りは、あの街から離れられないので」
だからこそ、残りの人生を過ごす町を「楽しい」「嬉しい」「もっと人を呼びたい」と思える場所にしていきたい。プロジェクトの全貌が固まったら改めて説明に行くので「お時間ください」と述べ、感謝の言葉で講演を終えました。
3.ディスカッションレポート
堀田一芙先生は冒頭で、輪島と白老(虎杖浜)それぞれの話に共通して「再建」「継承」「次の世代が動く」という軸が見えてきたとまとめました。そのうえで、会場側で用意した能登の資料を映しながら、南谷良枝先生に状況を補足してもらう流れに移ります。
写真でたどる、南谷先生の“商いの系譜”と震災の傷
南谷先生は、まずお祖母さまの写真を示しながら、能登半島を汽車で回り、ザルを担いで行商していた姿を紹介しました。小学校が終わると自転車で橋を渡って祖母の家へ行き、イカの一夜干しを袋詰めしたり、サバのいしる漬けを量ってパック詰めしたり、店番をしたり——「ばあちゃんの手伝いをするのがなんせ好きでした」と、誇らしさの混じる語りでした。
次の写真では、南谷先生ご自身が軽自動車の荷台で販売する姿が映されます。十七歳で朝市に店を持ち、十八歳で免許を取ってからは祖母の“運転手”として能登を回り、朝市と行商を両輪に震災まで続けてきたという話が続きました。朝市の写真では姑さん、実のお母さま、そして後を継いだ娘さんの姿も紹介され、「家族みんなで助けてもらって商売ができている」という言葉が印象に残ります。
娘さんの話では、初めて鯛をさばいたエピソードが会場の空気を和らげました。娘さんが「母ちゃん、この鯛買って。さばいてみたい」と言い、初めてさばいた鯛をお客さんに「初めてで下手くそだから、おまけする」と説明しながら売ったところ、「よくぞ案内してくれた」と喜んで買ってくれた——商いの現場の温度が、そのまま伝わる場面でした。
一方で、スライドは次第に震災後の写真へ移ります。庭だったはずの場所が地割れし段々畑のようになっている光景、地震の揺れで大きな樽が飛ばされて割れ、中身が流出した様子、倉庫の床が割れ地面がなくなった状態、加工場裏の庭がぐちゃぐちゃになった様子……南谷先生は一枚一枚を淡々と説明しつつも、その言葉の端々に、失われたものの大きさが滲みます。
輪島朝市の火災跡の写真では、「1月4日に行ったら燃えた臭いがすごかったです。何もかもなくなってしまいました」と短く語り、会場が静かになりました。さらに、断水の中で家族が順番に外で頭を洗う場面や、寒い中でぬるく沸かしたお湯をかけ合った話も続き、生活の厳しさが具体的に伝わってきます。
その後の写真は、富山の友人の会社でカニを仕入れて全国発送した場面、出張輪島朝市の立ち上げに集まった場面、金岩地区での第1回開催、そして金沢支店オープン時に届いた花々へ——復旧の“過程”が見える構成でした。ここは写真点数が多く、会場でもテンポよく割愛しながらの紹介でしたが、「やっとここまで来れたな」という南谷先生の言葉が、ひとつの区切りとして残りました。
見えてきた「能登にお金を流す」発想
中盤は、堀田先生と南谷先生の会話が中心になります。堀田先生は、南谷先生の店が扱う商品の幅広さに触れ、「ウェブで見せてもらえますか。能登はバラエティがとっても多い」と促しました。z

南谷先生は、震災前は自社製品が中心だったが、震災後は「能登にもお金を流したい」と考え方が変わったと説明します。自分だけが走り出せればいいのではなく、売りたくても売る場所がない生産者や商売人がいる。オンラインショップを持てない、販路がない——その状況を見て、「今の私ならお手伝いができる」と思ったといいます。
堀田先生が「和倉温泉がなくなっちゃったんで」と合いの手を入れると、南谷先生は「はい」と応じつつ、能登へ何度も足を運び、「一緒にやろう」と声をかけて、刺身が届く仕組みや牡蠣、肉、しいたけ(能登の肉厚で評価の高い商品)なども取り扱うようになった経緯を話しました。
堀田先生はさらに、「ベースになるのは、全国にいいお客さんが付いていることですね」と整理します。南谷先生も「全国に南谷のファンがいますので」と返し、ファンに自社商品だけでなく能登の他の商品も知ってもらい、少しずつでも協力につなげたい、と語りました。
話題は金沢支店へ移ります。堀田先生は、金沢が観光地である一方、能登の食材が金沢の食を支えている関係性を示しつつ、「金沢に支店を出されたのは、そこを開拓する意図ですか?」と問いかけました。ここで南谷先生の返答がはっきりしています。
「観光客相手に商売をしたいとか、そういう思いは一切なくて。全国発送する拠点が欲しかったんですよ」
輪島に戻っても発送する場所がない。ヤマトや佐川も被災し、集荷が間に合わない。朝取れたものを加工して夕方出し、翌日届く——その時間感覚が商売の前提だったからこそ、物流が止まると成り立たない。そうした現実の中で、金岩地区の人たちから「店舗をしてくれ」と背中を押され、当初はやりたくなかった店舗も、急遽カウンターを作り冷凍庫を買い、棚を用意して“金沢支店”として形にした、と語られました。堀田先生も「全部広く、広くして」と相槌を打ち、会場には「やむを得ない選択」だったことが伝わるやりとりになっていました。
「同じ町おこしでも環境が違う」二人の締めくくり

終盤、堀田先生は二人の取り組みを対比してまとめました。虎杖浜は商品数や魚種が多いわけではない中でも、特定のブランドを磨き、町を何とかしようとしている。一方、南谷先生は能登全体の産業を、魚に限らず支えたいという視点から、金沢の流通機構を活用して販路を作らざるを得ない。同じ「町を起こす」でも置かれた環境が違い、アプローチも違う——その点を、参加者に分かりやすく言語化しました。
さらに堀田先生は、祭りや太鼓、獅子舞といった能登の文化継承に話を広げます。南谷先生は、能登がいかに祭りを大切にしているかを語り、「正月と盆に帰れなくても祭りには帰ってくる」ほどだと説明しました。コロナ禍や震災後も、道がガタガタな中で時間短縮しながら祭りを続け、今年はキリコの数も増やし時間も少し延ばして実施したという話が続きます。堀田先生が「海の安全を祈る祭りですか」と問うと、南谷先生は「安全祈願みたいな」と答え、漁師町では神輿を担いで海に入る祭りもあると補足しました。
そして堀田先生は、本題である「能登の漁業の今」をデータで示しにくい現状に触れつつ、だからこそ漁業を支える側——販路、加工技術、付加価値づくりに若い世代が関わる重要性を強調しました。最後に「お二人ひと言ずつ」と促し、まとめの言葉へ入ります。
蒲原先生は、同じ意思を持つ人が日本全国にいるはずだと述べ、各地の知見や歴史を白老(虎杖浜)に学びとして落とし込めたら、それが文化として根付く、と語りました。「いつ始めたっていつでもスタートライン」と前向きに締め、「死ぬまで勉強し続けなければならないので、いろんな知見を教えてください」と、協力を呼びかけます。
南谷先生は、復興には「まだ10年ぐらいはかかるのでは」と見通しを述べつつも、「なくなったものを数えても仕方がないので、前だけ見て」と言い切りました。いただいた仕事を一つひとつ大切に、真心を込めて続けていくこと。そして、応援の形として「オンラインショップ」や「出張輪島朝市の催事」への声かけを案内し、「明るいおばちゃんたちなので、きっと楽しいと思います」と、場の空気を少し明るくして締めくくりました。
全体としてこのディスカッションは、被災地の現実を“写真と生活の具体”で見せながら、同時に地域の未来を“流通・文化・継承”の言葉で結び直す時間になっていました。