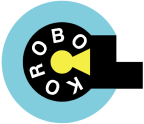大間ジローさん率いる「天地人」自身も東日本大震災で被災し、その後「やってまーれ!」の声を集めながらずっと復興支援コンサートを行って来た。
新年会で飲み進むうちに、大間さんも私も「やはり能登半島に行かなきゃ。。」という感じになったところで、まきりかさんが「まだ交通や地元の方々の事を考えると現地は時期が早い気がする。やるなら高岡の瑞龍寺でしょう」と言ってくれて、私たちの心にすとんと落ちた。「大間さん、まずは瑞龍寺でやりましょう」。この辺のまきさんの才能はすごい。すぐに高岡の開さんに瑞龍寺の四津谷道宏住職に繋いでいただき、週末に私は瑞龍寺にいた。
瑞龍寺自身も被災し、壁が落ちるなどの状況だったが、ありがたいことに昔高岡熱中小学校の授業をさせていただいていた、大茶会の部屋の提供を即答いただけた。四津谷住職さんは多忙な中で全国熱中小学校にも行っていただいており、本当にありがたいご縁をいただいている。
「天地人」に加えて、熱中小学校の教諭である、竹田元さんが友情出演。司会は同じく教諭の石川文子さん、ゲストには地元の音楽演奏家の皆様や東京からは講談家の神田紫さんに参加いただいた。そして高岡熱中寺子屋の皆様のご支援もいただいて6月8日(土)に成功裏に終了する事が出来たのだ。

まだ現地のプログラムの組み方がわからいままではあったが、瑞龍寺の成功から能登半島現地での実施について顧問先の株式会社内田洋行の協賛支援を得るべく動き出した。
(株)東洋ライスの江原さんからは農水省関係者で珠洲市の避難所におられる方をご紹介いただき、会いに出かけた。正月に実家に戻っていた際に被災し、そのまま支援活動で避難所に残られていた方で、その方の手記の最初の部分を以下に紹介する。
「私の家は、幸いにも屋根瓦が 20 数枚破損したり、ずれたりして雨漏りはしていたが、周囲の家屋からみれば比較的軽い被害ですんだ方である。現に、珠洲市からは「準半壊」の罹災証明を発行して頂いた。また、私には、横浜に家族の住む自宅があり、帰ろうと思えば、いつでも帰られる環境にあった。しかし、完全に倒壊した家、半壊状態の家やそこから命からがら脱出し、避難所でたどり着いた人たちを目の当たりにして「私は、横浜に安全な自宅があるから帰ります。」とは、とても言えなかったし、私の人間としてのプライドが、それを許さなかった。
私は、人前で涙した事が記憶にある限り無い。しかし、地震と津波のダブルパンチを受け軒並み壊滅した集落の悲惨な光景を見た時、ただ呆然とし、溢れ出る涙を止めることが出来なかったし、カメラを向ける気にもならなかった。」

「堀田さん、今ここで音楽ですか、と言われることを覚悟しておいた方がよいでしょう」。それが彼の貴重なアドバイスだった。今でも彼は住民に、できるだけ自助、共助を仲間に呼びかけているはずだ。専門の米の栽培についても、亀裂、断層が生じている水田で何とかして農家に残ってもらう事に尽力されていると思う。
もう一人のご縁の人は、柏原光太郎さんから紹介いただいた石川県庁の復興課の課長さんだ。国の役所から出向し、「創造的復興」の在り方について日夜考えている人だった。
やがてこのプロジェクトの石川県の後援やトップの方への橋渡し役をしていただくことになるのだが、何をもって石川県の言う「創造的復興」に参加できるのかが宿題になった。
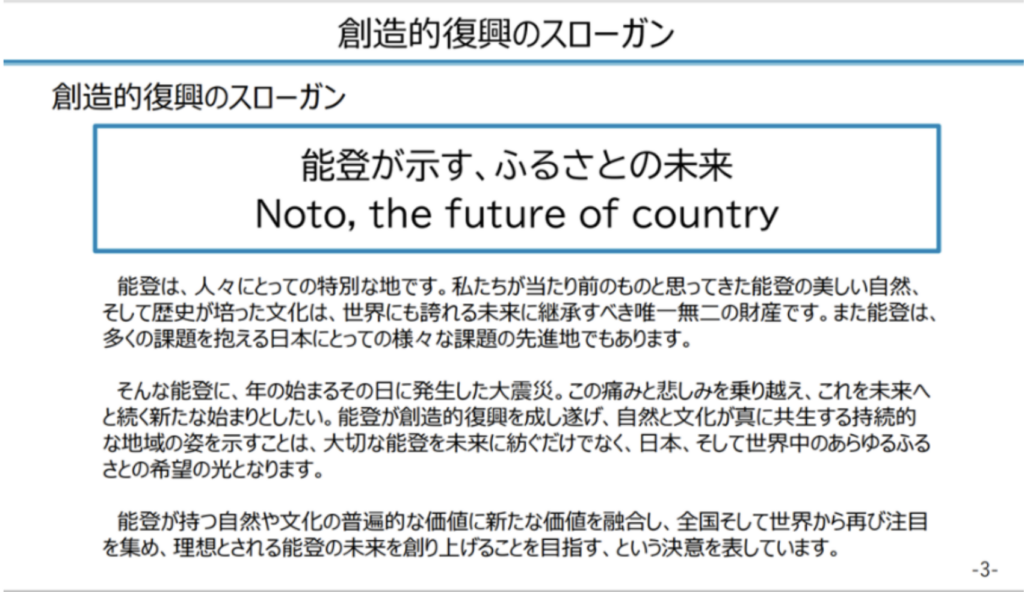
開さんには「一般社団法人熱中学園能登復興支援担当」の名刺を持って金沢の音楽関係者を回っていただいた。そしてついに能登町と珠洲市で、中学生から大人までが参加する吹奏楽のグループと接点ができて私も会いに行くことができ、現場が少し見え始めてきたのは8月のことだった。
(次回へ続く)