一般社団法人熱中学園(代表理事:堀田一芙/所在地:東京都墨田区)は、株式会社ジャパンタイムズが主催する 「Sustainable Japan Award 2025」において「Satoyama部門 審査員特別賞」を受賞するという嬉しいニュースをいただいた。
本アワードは2017年に創設され、持続可能な社会の実現に貢献する企業・団体・個人を対象に、その取り組みを顕彰するユニークなものだ。地域活性化や地方創生を対象とする「Satoyama部門」と、企業を中心とした持続可能な活動を対象とする「ESG部門」の2部門で構成されている。
2015年にスタートした「熱中小学校」プロジェクトは、全国各地の自治体や企業と協力しながら、地域に根差した新しい学びと実践の場作りに挑戦して来た。「熱中小学校」の特徴は地域に関わる人達が自主独立の精神で運営する大人の学び舎であること。7歳の目、つまり好奇心旺盛な時の気持ちに立ち返り地方での生き方を考えようという理念は最初から今まで一貫している。
現在、廃校や休校した地域もありながら国内15校・海外1校に広がり、2025年7月時点で 約1000人の受講生 が参加。350人を超えるボランティア講師による授業を通じて、地方創生を担う人材を育成してきた。開始から10年、高畠熱中小学校では記念行事が予定されている。
自立的なネットワーク組織であるから各地の学校の経営や考え方に規則はないが、10年の時間の中で進化のレベルはおぼろげながら解ってきた部分もある。
アワード受賞理由に、
「人と地域をつなぎ直す “社会教育+地域再生” モデルであり、持続可能な地域づくりに資する取り組み」
というコメントをいただいた。「学びと地域振興の融合」や「人を通じて地域資源を伝えるしくみ」にも通じるという評価に応えていくには、このプロジェクト自身の持続可能性も考えなければならない。
熱中小学校の進化ステップは、生徒さんが ①先生の授業の魅力で参加 ②生徒同士の交流による自身の成長を感じる ③地域の為に起業やボランティア活動を実施 というレベルがあると仮定してみる。第3ステップの活動が生徒さん達の手で進められる段階になって、かなりの時間が経過して、やっと地域からも評価されて持続可能な学校に進化するのではないだろうか? 地域の持続可能性向上の活動に対して生徒が中心になって開始し、自治や企業、地域の団体とも共に取り組んでゆく活動を支援するにはどうしたらよいのだろう?
そうした折に、開校から3年経過した紀州かつらぎ熱中小学校のオープンスクールの講師として呼ばれ、これを機にこれまでのパッケージを大幅に変更した。
受賞を機に、困難で時間がかかるが新しいトライを重ねていきたいものだ。


2025年9月13日 紀州かつらぎ熱中小学校 オープンスクール「もういちど7歳の目で世界を」講演資料はこちらからダウンロードいただけます。
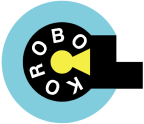



コメント