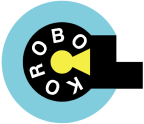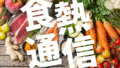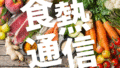①展開中の能登支援ツアーのクラファン継続中です。ご支援、拡散よろしくお願いします!

②「のと熱中授業」第4回は、「再び、牛と興す、能登」をテーマに7月12日(土)13:30〜配信します。ぜひご登録の上、ご視聴ください!

**************************************************************************
食の熱中小学校の魅力は、新たな出会いです。先日、参加者から「この歳になって友達ができると思わなかった」という声を聞きました。 確かに友人は、学生時代からの友人、趣味の友人、色々ありますが、これからそう広がるものではありません。食の熱中小学校をきっかけに美味しいものが大好きで、食の生産者や現場に興味がある“Foody”な友人が広がることは素晴らしいことです。是非、食の熱中小学校で新たな友人を見つけてください。
教頭 松田智生 丸ノ内プラチナ大学副学長


座学:5月28日(水)18時45分 3x3LabFurture
講 師:高 利充 先生 (NOTO高農園 社長)
テーマ: 「能登から見えるお店の風景」

NOTO高農園の高利充と申します。私共は2000年に脱サラをして農家になりました。つまり家が代々農家だったわけでもなく、ただ食べることが好きで自分達で作ればいっぱい食べられるなという不純な動機から始めました。なので当初は自分達が食べたいもの、ジャガイモやさつまいも、かぼちゃ、キャベツ、かぶだけ作っていました。始めて今年で25年になるんですが、17年ぐらい前に転機がありました。七尾市で食育のイベントがありまして、四谷のオテル・ドゥ・ミクニの三國シェフがいらっしゃって野菜を提供させていただいたのですが、その時「普通の野菜しか作ってないの?」って言われまして。直売所等で50種類ぐらいの野菜を作っていた時です。驚いて、普通じゃない野菜って何ですかって聞いたら、一度四谷においで、って言われて四谷にうかがいました。行った時はどこかの大使館のレセプションをしている中、三國さんが後ろでささやきながら、海外からちりめんキャベツが来てるよ、カーボロネロが来てるよ、とか、これはまだ日本ではあまり作ってないから輸入しながら作ってみたら、僕ら日本人がフランス料理をしたらジャポネじゃないんだ、だからこれをちゃんとジャポネでできるようにしたいからこういうのを作ったらどうだね、ということを言われまして。その時から ”普通じゃない野菜” を作り始めました。それが北陸新幹線開業の3年前頃で、石川県がいしかわ百万石マルシェという、東京都内のシェフに石川をもっと知ってもらおうというイベントを企画して、そこからスタートして、丸ビルのモナリザのシェフに一番最初に使っていただきました。その時はまだ5〜10種類しか作っていなくて、それじゃ少ないよ、もっと植えなよ、なんて散々言われながら少しずつ増やしていきました。シェフはどんな人なのか、どんな料理を出すのかを興味を持って見ていくうちに、そう調理するならこれ使うんじゃないかな、といった試行を少しずつ繰り返していって、気がつくと今300品種ぐらいまで増えてしまいました。一番小さいと畳1枚分ぐらいの広さです。自宅の周りをラボと称していて、いろいろなハーブとかを、これは能登で生えるのかどうか、能登でうまくいくのかいかないのか、といったことを実際にシェフに聞いてみて、だめと言われるものもあればいいねと言われるのもあり、そんな中から取捨選択をしていってこういう赤土畑に合うものを探すことを続けて25年経ちました。月に1度は東京や大阪へ行って、シェフの方たちがどういう思考で料理を作ってどう野菜を使っているのか、どうやったら使ってもらえるか、を学ぶのがライフワークになっています。また、来たお客様にどんなサプライズを提供するか。入ってないものをいかに入っているように見せるか、というのも考えます。今日はエディブルフラワーのように、入ってないけど入ってる(お花だけどねぎの味がするとか)、を体験できるようなものを一応持ってきたつもりなので、ぜひ後で食べてみていただきたいなと思います。

25年の中で、やはり去年の地震はなかなかひどかったです。24坪ある冷蔵庫がかなりやられて、その修繕だけで1千万円かかりました。畑も20町歩保有のうちの4町歩が未だに修理不能のままです。
いつ頃治るか聞いてもわからないまま。スタッフも9人いましたが家が壊れたりなどで半分になり、残ったスタッフも仮設住宅から通っている状況が続いています。楽ではないです。ただ、昨今お米問題も含めていろいろな形で今僕らはもう1回食を見直すチャンスが来てるんじゃないかなって思ってるので、ここをうまく頑張って乗り切って、1次産業の関係人口を少しでも増やしていけたらいいなと思ってやっています。スターシェフがいて、1次産業の僕らは裏方ですが、裏方でもちゃんと彼らの思考を理解して彼らの力を最大限引き出す努力をしたいと思っています。先ほど柏原校長のお話にあったディスティニー専門レストランの中でもご縁のあるシェフ達が結構いらっしゃるので、そういう中で僕らの価値は何なのかを考えながら仕事させていただいてます。やっぱり食べるのが好きでこの世界に来ましたから、そういったいろいろな人たちに関わるのがすごく楽しいし、関わることでこの食材がどういうふうに化けるかわかることも多くて、今本当に楽しくさせていただいてます。うちのスタッフには非常に申し訳ないんですが、自分たちは日々壊れたものばかり見てるんですけど、このように壊れてないものを見ることで今癒されているなと、改めて思います。逆に今日はこういう場に呼んでいただいて本当にすごく感謝しかないですし、やはり続けられる喜びというのはすごくありがたいなと思っています。
今、お米の値上がりが問題になっていますが、我々も、トラクターを動かせば燃料代がかかり、トラクターもうちで使ってる30馬力ぐらいのものだと1台500万円します。お米農家さんも田植え機がありコンバインがありそれを精米する乾燥機がある。田植え機は地面に擦っていくものなので、5年で地面と擦る部分がなくなっちゃう(プラスティックの部分)。つまり田植え機とかコンバインって5年経つとなくなっちゃうものなので、それでその値段で続けてくださいというと本当にやる人いなくなってしまいます。だから今国会での、米が高いという議論、うーん微妙だなと。確かに安いのがいい人もいるので、それはそのように作ればよくて、ちょっとそこはいろいろ考えていかないと難しいタイミングに来ていると思います。ヨーロッパなんかは、ほぼほぼ補助金で機械を更新できるしくみがあります。その点を日本政府は何も言わない。でも今日の明日、食料の供給が止まってしまったら皆さん大変なことになりますよね。我々農家にしても、農業に欠かせない肥料リン酸はほぼ輸入です。なくなると本当に物を作れなくなっちゃうんです。農水の方々も外交に関わる方々も、ちゃんと考えてやっていっていただかないともう回らなくなる。本当にこれは1人で解決できる問題ではないので、またみんなで考えていただけるチャンスをいただけたらありがたいと思っております。

震災に遭ってすぐの1月6日の出勤の初日にスタッフが来て、社長、何しましょうかって言われて。こういう子がまだいるから頑張らないかん、この子のためにも頑張らないかんなって思いました。大変だけどとりあえずあるものでやろう、って1月10日から出荷再開しました。七尾のクロネコヤマトは業務が止まってるので隣の富山の射水まで片道4時間かけて持っていきました。2月の半ばまでは能越道が使えなかったので下道を走っていって。あと暗くなると段差が見えないので4時には家を出なくちゃいけない。ちょうど実家が富山にあったんで、富山でしばらくちょっとご厄介になりながら、毎日通うということをしてました。うちは準半壊でした。元々建設業をしていて、阪神淡路の震災の時助けに行く立場で、見に行ったときに、こういうふうに作れば壊れないのではという一つの知見を得て作ったんですが、その予想を上回る揺れでした。システムキッチンは1トン耐えるアンカーボルトを10本打ってあったのが全部抜けてしまって、メーカーさんももう絶句していました。
その中で畑仕事を再開しました。畑に行ってみて、水は出ないし地面は割れてるし道路もぐちゃぐちゃだけど、でも野菜は元気だったんですよ。だから、この子たちを無駄にしちゃいけない、何とか料理という形に昇華させてあげないとかわいそうや、何かできることをしようと。地下水が出るところから地下水を汲んできて、冬で水温1度や2度のところに投げ込みヒーターを入れてちょっと温度を上げて洗って出荷しました。

七尾や珠洲の方々が3日ぐらいから炊き出しをやられていて、いやうちらも負けてちゃいけん、頑張らんといかんと思いました。
今如実に表れているのは、ここでは稼げない、仕事がないために働き盛りの世代がポンといなくなっちゃっているんです。さらに、奥能登の支援復興のためにいろんな業者さんが来られますよね。そうすると、和倉温泉界隈って輪島とか行くのに都合がいいのでワンルームマンションとか借りられるんですよ。でも、そんな片田舎にあるワンルームマンションが月9万円とかなんですよ。とても借りられません。働きたいっていう子たちは来るんですけど住む場所がない。やっぱりまだ、被災した人たちの住宅の方がメインであって、新しく移住するとかそこまでは考えてないようです。でも考えていかないとそこで働く人、何か起業する人がいないことになるので本当にもう少し考えてほしいと今思ってます。東北とか熊本みたいにもともと産業があるところは復興させるけど、そうでない地域は人がいなければ税金を投下するのも無駄だから諦めてもいいんや、というモデルを作ってしまう形になりそうな気がするんです。
輪島塗も、例えば赤木明登さんは仲良くてよくご一緒しますが、塗師屋といって最後の仕上げとあとはブランドの総監督みたいな感じです。木地職人さんが1人いなくなると10個の作品ができなくなるそうです。例えば へぎと言う木を剥いで作る工程ができる職人がいなくなった。これからそういうのがどんどん出てきそうなんです。だから、本当にやりたいという希望のある子たちが何とかやれるよう、受け入れる仕組みを作っていきたい。震災前も年間約400人位のシェフや調理師学校の方がいらっしゃっていたのですが、震災後はすごく増えました。現状の畑を見に行きたい、って言うシェフの方がすごく今増えて、大体週に1人や2人は来ていただいてます。本当に僕らはこういう人たちに支えられてるなって思うし、頑張らんといかんなって思います。そして今、赤木さんを見習って僕らも農泊みたいなものをこれからやりたいなと思ってます。いろんなシェフの方とお付き合いがあるので、お客さんも一緒に連れてきてくださいよと言って、畑で自分で抜いた野菜をそのシェフが調理してくれる、というのをやれたらいいなと。60才になるまでにそれをやりたいなと思って、これ最後の野望と思っております。
赤木さんは北崎裕さんというすごいパートナーがいらっしゃいましたけど、僕はこの人と言える人が見つけにくい分、逆にいろいろな方に声がけをしたり、あとそこのお店を上がって自分でやりますよ、とか、前のポップアップで2週間だけやりたいなとか、アメリカでアリス・ウォータースさんの「おいしい革命」ってあったじゃないですか、あれを目標に何かできたらいいなって思ってます。実際今お付き合いしてるお店がそういう形で回していて、僕らもすごく賛同する部分があって、それをみて何かできるかなって今思いながら今やってます。

まずは皆さんに能登に来ていただけると嬉しいです。あとは東京でも食べていただいたりしていただけると。今日お持ちしたものでバーニャカウダサラダセットっていうものがありまして、今三越さんと伊勢丹さんで売らせていただいているのですが、これはもともと西麻布のレフェルヴェソンスさんのサラダを見て、50種類ってのはちょっと難しいけれど主幹になっている野菜を選んでこういうふうに食べられたらいいんじゃないかと、そういうコンセプトで作り始めました。単純にそれを切るだけで作れるというモノ体験、コト体験をしていただけたらいいなと。また、そうか能登は今こんなのが獲れるんだ、って見ていただくだけでもすごくありがたいなと思います。
能登の人は来ていただければ元気が出ます! 県外からいらっしゃるということは見捨てられていないんだと能登の人は思います。6月以降は部分開通ですが能登島にはもう1本の橋が繋がるので能登空港から30分で来れるようになります。皆さんが来ていただいて、まだ大変だと言っていただくことで、行政にも圧力になると思います。やっぱり声を上げ続けることが大事で、実はサッカー日本代表の中田英寿さんが畑に来てくれるのですが、お前らアピールが足らん、ファールだったら今のはファールだろって抗議するよ。お前らはそれを言ってない、言わなかったのはお前らが悪い。今からでも遅くないからちゃんと言えと言われています。
今日は、とりあえず今能登はこういうことだよというのをちゃんと説明してきてねと皆から背中を押されて今日は来ました。自分だけではなくいろんな方の思いを今日は背負ってきたんじゃないかなと思います。少しでも現状がお伝えできたからよかったかなと思います。本当にありがとうございました。


高知県中土佐町 2025年5月24日(土)〜5月25日(日) 1泊2日
〜鰹一本釣りの町で出会う、 貴重な国産七面鳥、日本一のトマト、カツオで作る野菜〜
今回は動画でご報告いたします。
***************************************************
事務局より:
「梅雨の晴れ間」なんて優雅なものじゃない! なんだ、この暑さは!……..という灼熱の日々が続いています。皆さま、熱中症にはくれぐれもご用心ください。それで思い出したのですが、昭和の時代にはまだ「日射病」とか「暑気あたり」などという言い方も残っていて、運動中は水を飲むな!というとんでもない指導が当たり前でした。水分を摂るとバテるとか、胃腸を冷やすとかいう理由で、実際は精神修養、根性論がまかり通っていたんですね。ちなみに、厚生労働省の省令が改正されて、今月から職場における熱中症対策が義務化されました。ようやく…….ですね。

「食熱通信第15号」発行:食の熱中小学校事務局(一般社団法人熱中学園内)
公式サイト:https://shoku-no-necchu.com/
Mail to:hello@shoku-no-necchu.com