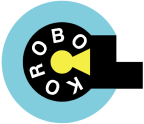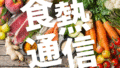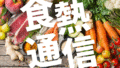【今月の特報】
①一般社団法人熱中学園がジャパンタイムス主催“Sustainable Japan Award 2025”でSatoyama部門審査員特別賞を受賞!!
◆記念講演会を開催します。
どなたでもリアル、ZOOMで参加可能です。参加は無料です。
日時:2025年9月30日(火)18時30分―20時30分(受付開始18時)
会場: ユビキタス協創広場 CANVAS
18:00 ~ 受付開始
18:30
開会 司会 綛谷久美 食の熱中小学校教頭
ご挨拶 堀田一芙 一般社団法人熱中学園代表理事
来賓挨拶 末松弥奈子 The Japan Times 代表取締役会長兼社長
来賓講和 雜賀慶二 株式会社東洋ライス株式会社代表取締役 食の熱中小学校名誉校長
19:10 ~20:20
記念講演 柏原光太郎 日本ガストロノミ―協会会長 食の熱中小学校校長「日本各地に続々誕生!デスティネーションレストランの魅力」
終了挨拶 大久保昇 株式会内田洋行代表取締役社長 一般社団法人熱中学園理事
申し込みサイト https://forms.gle/SGq57rpKgHGKxevYA

②第5期生徒募集中!!
-サスティナブルな学校へ・各プログラム同士のクロッシング企画もー
申し込みサイト https://shoku-no-necchu-5.peatix.com/
募集要項 https://shoku-no-necchu.com/application/
第5期 講師紹介&スケジュール https://shoku-no-necchu.com/schedule-term5/

**************************************************************************
食の熱中小学校・第5期プログラムがスタートします。もうご覧になりましたか?
地域と都市をつなぐ関係人口づくりの先駆的な取り組みとして、各地の生産者や事業者と、食に関心の高い都市生活者をつないできました。
授業に参加するだけでなく、現地での給食体験や懇親会で交わされる何気ない「おいしかった!」という言葉が、実は生産者の心に深く届いているんです。
7月に訪れた新潟・糸魚川市、8月の北海道・芽室町でも、「直接声が聞けて嬉しかった」「励みになった」といった声を何度もいただきました。それは商品を買う以上に力強い応援となり、地域の未来をつくるエネルギーになります。
食の熱中小学校は共に創るプロジェクト。あなたの存在が次の一歩を後押しする力になります。第5期もぜひご一緒しましょう。
教頭 綛谷由美


座学: 2025年7月30日(水曜) 18:45 ~ 3×3 Lab Future
授業テーマ: 「諏訪の風土を通して見る 食の魅力」
講師: 金子 ゆかり 先生(長野県諏訪市長) 宮坂 直孝 先生 (清酒「真澄」蔵元・宮坂醸造(株)代表取締役社長) ※進行役 松田智生教頭
プログラム: ①「諏訪の魅力、食の魅力」金子市長 ② 「長野発酵バレーの魅力と真澄の魅力」 宮坂社長 ③ 三者 鼎談 (進行 松田教頭)
金子ゆかりと申します。長野県の真ん中にある諏訪市は、名古屋からも東京からも大体2時間ちょっとの、人口4万7千人ほどの地方都市です。自然と歴史文化に恵まれており、諏訪大社は最近では「逃げ上手の若君」、少し前では「君の名は」というアニメ映画の舞台になるなどいろいろな素材を観光に生かしています。一方、もの作りの伝統が息づく先端技術産業の集積地ということで、諏訪圏域には800社ほどの製造業があり世界の最先端で戦っている企業がたくさんあります。諏訪湖の花火は、8月15日を中心に今は7月26日からサマーナイトが始まり、9月には新作花火大会、今年からは勝ち抜き戦の個人花火師のコンペティションを計画しています。諏訪湖上ではカヌーだったり、湖周16キロの自転車道が昨年完成しています。7月27日には諏訪湖サービスエリアにスマートインターチェンジが開通しました。霧ケ峰高原は360度のパノラマで、全国の百名山のうち35山が眺められるという高原で、魅力の架け橋、高原の湖畔都市、なんていうキャッチを付けております。標高は749mと高く湿度が低く爽やかで、内陸ですので晴天率は高く、そして寒いですが降雪量は少ないです。諏訪湖はかつて凍って膨張によって亀裂ができました。これが、神様が彼女のところに渡った足跡と言われる伝説の御神渡りです。582年間ずっと宮司によって行なわれてきた観測記録が残っていて、この自然現象の定点観測記録は世界一、世界も環境省も大注目していて、ここ50年間で凍らない「明けの海」が増え、昨年のCOP29でも映画で紹介され問題提起されています。

こうした環境の中で、古くから地域の人たちはどう食を維持してきたでしょうか。まず戦後は冷蔵庫がありませんでしたから海産物は塩漬けです。塩漬けの鮭や塩サバ、そして塩丸イカは諏訪地方特有で、茹でて塩漬けにして運ばれてきた。そのまま出したらしょっぱくて食べられないので塩抜きして使うんですよとお嫁さんは教えられました。また珍しいのが海苔で、海苔の品質は諏訪人が決めていたと言われています。冬働く場所がなくなるので千葉や大森などの海辺の海苔屋に出稼ぎに行って海苔の品質検査をする人が多くいました。海苔には検査印がありますが、検査結果の評価を高めに出すよう海苔屋さんから接待されて対応してしまう検査員がよくいたそうですが、真面目な信州人の検査員はそんないい加減はしなかったので、そこから信州人の評価した海苔の品質は確か、海苔の品質は信州人が決めると言われたわけです。諏訪大社に御湯花講というのがあり、これは海苔の検査員たちが奉納したものです。田舎の山の中の暮らしを示すジビエは、江戸時代は四つ足を食べてはいけなかったのですが諏訪大社では禁じられておらず、鹿食免という肉食を許可する免罪符を発行してジビエ料理を許し、またそれを食べるときには鹿食箸で食べることで怨念が救われるという言われがあったそうです。
厳しい自然の中で山の暮らしの知恵として食を繋いできたのは長期保存できる発酵食です。味噌やチーズ、醤油、お酢、納豆等常温でも腐らない発酵の力を生かした食品が活用されてきました。味噌は、赤味噌の価格は信州が決めます。例えば八丁味噌は名古屋、白味噌は都、赤味噌は手前味噌、つまり全国各地で自分の家で大豆を煮て塩で置いて干して味噌を作っていました。ですがそれを流通に乗せるには味や安全の評価基準が必要だ、と言い出したのが信州人です。これも信州人の真面目さからで、信州は赤味噌の生産は全国1位、今でも赤味噌の組合や味噌の全国組織の組合長は諏訪のタケヤ味噌さんや長野市の神州一味噌さんなど信州の方が有名です。

長野県は健康長寿日本一ですが、塩分摂り過ぎで脳卒中の発症率が高かった。これに気付いた佐久総合病院の若月俊一先生が減塩活動を始めました。この運動は諏訪市の89の近隣自治区から毎年200人もの方達が参加2年ごとにバトンを渡していきます。講習会を受け、減塩の料理を作ったり、お酢で漬けを変えるといった調理方法を学びます。わかさぎはかつて諏訪湖でたくさん取れました。諏訪のお菓子屋さんが真澄さんの酒粕でチーズケーキに味わいをつけたらどうかということでホテルと共同開発したチーズケーキアントルメは通販でいっぱい売れてます。ところてんや寒天の原料のテングサ、これを乾燥してしっかり煮てそれを凍らせますが、冷凍庫のない昔は全材料を凍らせるために山の上に持ってきました。それで諏訪地域は寒天の生産量が非常に多いです。諏訪味豚(びとん)という豚肉は、後山という30戸ほどの地区、住民は80何歳と高齢化していますが要介護の方が少なくて、長寿で今でも畑に出て頑張っているという村があり、その村唯一の養豚場さんが出している肉でなかなか美味しいんです。数量限定なので限られたところでしか食べられません。あと後山は松茸も産地で高級品質の松茸が獲れます。白いトウモロコシのピュアホワイトは生で食べても美味しいです。いろいろな種類を育てていると花粉が一斉に飛んで黄色の品種と混雑してしまいますが、山の中でこれだけ作っていると完全な純ピュアホワイトが生産されます。長野県が開発したひすいそばの種はここで生産しています。それから蜂蜜、これも濃厚で美味しいです。食を応援する皆さんが諏訪のB級グルメブランドを作れないだろうかと、10数店舗で共同して開発したのが味噌天丼です。天丼ですがタレを少し甘めの味噌を溶かした味噌ダレにして具材は店ごとのオリジナルで違います。大根はたくわんにするのに最適で、江戸時代にはお殿様への献上品に指定されていました。コリコリと歯ごたえが良くて、ところがその後交雑してしまい品種がわからなくなってしまったのですが、信州大学農学部と共同開発して原種に戻すことができ、上野地区で復活しております。これも限定で、毎年いつも売り切れているという大根です。このようにたくさんの魅力ある食に恵まれた、健康長寿日本一の土地でございます。
<ここから宮坂醸造・宮坂社長のお話>


諏訪で真澄という銘柄の日本酒を造っております宮坂です。創業は1662年、今年で367年になります。県内では4番目に古い酒蔵です。酒蔵はもともと諏訪にあったものと私の父親が八ヶ岳山麓に新しく富士見という蔵を作り、2つありますが、今は富士見蔵だけに集中させています。真澄の名前の由来は、諏訪大社の宝物展に保存されている銅製の鏡「真澄の鏡」から名前をいただいて名乗っております。現在の販売先は、長野県内が40%、県外が45%、海外で15%ぐらいの割合で、中堅の酒屋になります。従業員は大体70名くらいです。もともとは諏訪のお殿様に仕える武士だったらしいのですが、1662年に武士をやめて酒屋になりました。ところが、なかなかうまくいかず大変貧乏な酒屋だったようです。このままでは潰れてしまうということで私の祖父の宮坂勝が1920年代当時、地元出身の窪田さんという方を杜氏(酒造りの責任者)に抜擢して酒造りに奮闘します。田舎の小さい酒屋は品評会で一等賞をとるようなことをしないと生き残れないと、本当に2人で頑張りまして、1943年に全国清酒鑑評会という、日本で一番権威のあるお酒の品評会で1位をいただきました。聞いたこともない貧乏酒屋が権威ある品評会で一等賞を取るなんて不思議だねと業界で言われていました。そのうちにさらに成績が良くなり、1946年には春と秋の2回開かれる全国の新酒品評会で春も秋も1位から3位まで全部真澄が受賞ということがあって、いよいよ何か秘密があるに違いない、といろいろな研究者がやってきました。そして酒蔵にあるもろみを採取して分析し、この蔵には特殊な酵母が住んでいることがわかりました。国が7番目に認定した優れた酵母ということで7号酵母と名付けられました。そうして名もない酒蔵が全国に知られていくことになっていったわけです。ただ、祖父はいい酒は作れましたが商売っ気がなかったのでまだまだ貧乏酒屋でした。そこへ立教大学の経済学部を出て帰ってきた父はどちらかというとマーケティングの人間だったので、いい酒を祖父が作り父がそれを販売する、といういいコンビが出来上がり、売り上げが急速に伸びていきました。父は瓶詰めの工程を新しくしたり、設備を近代化するのが好きで、機械も大好きだったので、これも成長に大きく貢献したと思います。そして次は私が1982年に戻り、父と喧嘩をしながら商品や酒の味を直すといった再挑戦が始まりました。90年代の前半ぐらいまでは地酒ブームで、特に東京市場で非常に売れていたんですが、だんだんブームが去ってなかなか売り上げが思うようにいかないようになり、その頃から私は世界へ挑戦を始めました。2013年に長男が帰ってきて、今の真澄の酒は美味くないとかボトルが格好悪いとか、ラベルデザインが洗練されていないだとかいろんなこと言い出して、怒りが込み上げてきたんですが、よく考えるとそれは30年前に私が父親に向かって言っていたことと同じでした。やっぱり若い世代の言うことは聞かないといけないなと思って、2019年に、かなり大きく酒の味を変えたり、ラベルデザインを息子に任せて一新したりといったことを始めています。7号酵母の特徴は、発酵力が非常に強く、低温でしっかり発酵してくれる。それからバナナやメロンのような香りを生成しやすい。穏やかな香りを作る酵母で、またどちらかというと香りより味のバランスの良さが特徴で、それが一世を風靡しました。新しいロゴは、酒を満たした盃の先に宮坂家の家紋である蔦の葉が映っている様子をデフォルメしていて、デザイナーの方に作っていただきました。輸出に力を入れていく中で、海外の方々は漢字が読めませんのでむしろ印象付けのためにここでロゴマークをしっかり打ち出したのは今でも良かったと考えております。

私はこの20年の間、4つの夢を掲げてきました。1番目は日本一うまい日本酒を造りたい、2番目は人々の食卓をお客様の食卓を和やかにしたい。3番目は諏訪のまちに賑わいをもたらす酒屋になりたい。4番目は日本酒を世界酒にすること、です。この4つに本気で取り組み真澄ブランドを理想像に近づけることで、売上と高い経営・営業利益を実現して従業員の賃金の引き上げや未来志向の投資をどんどんしていく、そういう会社になりたいというのがビジョンでございます。また国際化を大切にしたいという思いもあります。酒屋をもうかれこれ40数年やっていますが、日本酒ってとても幸せな商品だなと思っていて、この幸せを多くの方々に分けていきたく、社員にもそう呼びかけています。4つの夢をどうやって実現していくか。まず日本一うまい酒を造るには、これは造り手である私達自身が舌鼓を打って飲める酒です。まずうちの社員や家族が美味しいと思わない酒はお客様に売るべきでないというのが私の考え方です。普段私は妻と2人で夕飯を食べていますが、その食卓の真ん中に四合瓶があり家庭料理をいただきながら毎晩4分の3程度は空けてしまうような酒でありたい。なるべく多くの方々の舌に合うようになんてことを言い始めると何がいいかわからなくなって方向性が狂いますので、我が家や会社のための酒を作っているんだというぐらいの意気込みが重要です。添加物でごまかしたりせず家族に安心して飲んでもらえること、友達にこれがうちの会社の酒だよと自慢できること、それがとても大切だと思い毎日頑張っています。また。日本酒は傷みやすい商品なので、光が当たったり高い温度に晒されないようにする流通はとても大切で、販売店との関係強化も重視しております。量が売れればどこへでも出すのではなく、我々の気持ちをわかってくれる流通の方とだけ組むというのが我々の意志で、海外向けもそうです。2番目の、人々の食卓を和やかにしたい、に関しては、実は4つの中で私が一番大切にしていて、食卓が和やかであるかはとても大切だと思います。豪華な美味しいグルメを食べようという意味ではなく、質素でもいいのでちゃんと心を込めて作られた料理を、家族や友達とコミュニケーションしながら食べるということ、ここから人間の幸せは始まると私は強く信じており、それを実現できるような酒屋になりたいというのが夢ですね。7号酵母は控えめだけど、お料理をすごく引き立てる酵母なんです。先ほど7号酵母ファンという方がいてくださってとても嬉しかったですけれども、非常に控えめだからこそお料理とぴったり合う食中酒ができる。これでいこう、と2017年に言い出したのはうちの息子でした。7号酵母の発祥の蔵なのに、7号酵母以外の香り系の酵母を少し使ったりしていました。でも駄目だと言って全部7号酵母に原点回帰しまして、今思うと良かったなと思っています。ただ、食生活は変化するのでそれに合うように新しいスタイルの酒の開発は必要だと思っていて、絶えずチャレンジしていきたいです。今日はそんな中から発泡性のお酒と多酸性のお酒、低アルコールのお酒をお持ちしましたので召し上がっていただきたいと思います。とにかく食卓の大切さは本当にアピールしていて、TVCMや紙媒体、SNS等すべて食絡みの情報にするよう社員に言っていますし、私共のオンラインショップで食器や食材まで幅広く販売させていただいているのは、皆で食卓を大切にしようというメッセージの別の形のアピールでもあります。それから、先ほど市長も触れられた「発酵バレーNAGANO」というコンソーシアムが2年前ぐらいから立ち上がっていて、酒だけではなく長野県全体の食のレベルアップもやろうよと積極的に取り組んでいます。3番目の夢も大切にしています。私は2000年から2020年くらいまで海外に行き、主にヨーロッパのワイナリーやビールメーカー、スコットランドのウイスキー工場などを廻ってきまして、有名な酒屋がある場所はツーリズムの拠点になっているということを確認してきました。諏訪市には5軒の造り酒屋があり、父の代は喧嘩ばかりしていたらしいですが今はとても仲が良く、協力しながら手を組んで各蔵でショップを作ったりテイスティングルームを作ったりと、賑やかになったと市長に言わせてみたい思いでいろいろやっております。やがてはこだわりの新しい信州料理のレストランを持ちたいと研究していたらお腹が出てきちゃいました(笑)。今年の10月4日には市長の肝入りで、国道20号線を5時間歩行者天国にして僕らのイベントをやりますのでぜひ皆さんお出かけください。去年は大体3500人ぐらいの方々が来ました。またこの日でなくても、クーポン3000円で5蔵を飲み歩いて楽しむ「いつでもごくらく酒蔵めぐり」というのを毎日やっています。こちらは1年間で大体1万人ぐらいの方々が来てくださるようになりました。

4番目は、日本酒を世界へ展開させたいということです。私は富山県の満寿泉さんととても仲良くさせていただいていて、一度フランスのワイナリーに連れてってやるよと言われ1995年に初めてフランスのボルドーとブルゴーニュの中堅の蔵を廻りました。これが僕にとって非常にエポックメイキングな旅行となり、もっと日本酒でこだわって世界へ出ていきたいと思うようになり、2000年くらいから輸出に取り組んできました。海外人材を雇用し、教育的マーケティングと標榜しまして彼らを世界中のレストランに行かせて日本酒について伝えることをしています。どういう工程で作られるのか、どのように飲んだら美味しいのか、貯蔵はどうしたらいいのかといったことを教育しながらお酒も少しずつ買っていただいています。世界的な展示会にも出展したり、香港や深圳には小さい営業所まで構えて、出かけていっては美味しい中華料理を食べるのが楽しみです。
<ここから松田教頭も入ってのミニ鼎談>
松田教頭:ありがとうございました。ここでお二方のパーソナルヒストリーをお聞かせください。
金子市長:企業のOLだった時、議員である父の秘書をしていた母が余命宣告をされ6ヶ月で亡くなってしまいました。手伝ってほしいので帰ってくるようにと父に呼び戻され手伝いをしていた流れで、議員の世界に足を突っ込むことになりました。そして後援会の皆さん達との活動の中で生まれた、諏訪という素晴らしいこの地を磨けばもっと輝くまちになるだろうという思いから、僭越ながら市長に手を挙げてしまい、2期目の逆風も経験しながら今に至っております。
宮坂社長:私は典型的な酒屋の息子で、そもそも酒が何なのかもわからない。大学を出て戻ってきて遊び暮らしていればいいと思っていたら、親が、英語ぐらい喋れなきゃ商売にならない、自分で受験してアメリカに留学してこいと。向こうのビジネススクールはケーススタディしレポート提出の連続で、ある時、薬のケースを探してレポートを書けと言われ困っていたら、酒屋の息子なら酒をテーマにしたらいいと教授に言われた。そこから酒屋としての意識が少し芽生えて、帰ってきてそのままやっている感じです。

松田教頭:ありがとうございます。では次に諏訪について、良いところがある一方で課題もあると思います。今諏訪が抱える課題があれば、それぞれお話ししていただけますか。
金子市長:諏訪は四方を山に囲まれているので見える範囲で生活していた歴史が長く、判断基準やお手本が狭く身近なもので済んでしまっていました。しかしこれからは峠の向こうはもちろん、海外にまで目線を移していく必要があり、昔ながらの判断基準が強く出ないようにと言っています。そういう環境だったからこそ精密機械のような真面目でコツコツと根気がいる産業が生まれたとも言え利点と欠点は表裏一体なのですが、気づくことが重要ですね。
松田教頭:まちを出ていった人が後からその魅力に気づくことがありますね。
金子市長:パリでレストランを経営し2020年にアジア人で初めてミシュランの三ツ星を獲得し5年連続受賞した小林圭シェフは諏訪市出身なんです。実に創造的な、ジュエルのようで食べるのがもったいないような素晴らしいフランス料理です。パリで評判を得て静岡の御殿場に出した第2号店は彼の右腕の佐藤充宣シェフに店長を任せました。昨年は和菓子屋のとらやさんのスポンサーで銀座7丁目に小林さんのレストランが、またザ・リッツ・カールトンホテル東京の最上階にも小林さん監修のレストランができました。市長表彰特別賞受賞の際に対談をしまして、パリにいる彼が故郷の諏訪から何か食材を送れないだろうか、何がいいかと考えた時、生鮮食料品は新鮮さが大事だから近くから調達したい、田舎から取り寄せるとしたらやっぱり発酵食品ですねとおっしゃっていました。彼がこの先目指すのはレストランの展開ではなくブランド化、「Kブランド」なのだそうで、それから本当に2、3年でリッツ・カールトンの上のレストランの監修などの展開を始められて、世界で成功する人というのはやっぱり見ている視点が違う、世界を向いているなと感じているところです。
松田教頭;ありがとうございます。次は宮坂社長に伺います。課題とあとそれを反転させるためのもっとよくなる諏訪っていうことでお話をいただけますでしょうか?
宮坂社長:先ほど申し上げた満寿泉の桝田君に連れられて行ったフランス旅行は、私にとって人生を変える旅行で大変恩義を感じております。旅行中3つ感じたことは、1つは当時のワインメーカーは華やかな世界どころか大変苦しんでいたのですが、苦しむ中もう一度品質をきちんと見直すこと、ワインカントリーツーリズムにしっかり取り組むこと、自分たちのワインの価値を理解してくれる国へ輸出し売りに行くこと、この3つを一生懸命やっていました。私の夢も正にこの3つをやっているわけですが、諏訪盆地には9軒の造り酒屋があり長野県全体では80軒の酒蔵があり、みんな真面目ですし技術力も高い。けれど何か足りない、もう一つ突き抜けられないというのが現実です。今長野県80の酒蔵組合の代表をさせていただいているので、私が務めている間に何とか皆にもう少し海外を向いて視野を広げてもらいたい。それが糧となった時に品質のブラッシュアップに繋がったり、いろいろな情報発信の活動に磨きがかかるようになるし、そのことで酒屋はすごく良くなるしまちにも波及効果を呼ぶというふうにしたいなと思っているところです。
松田教頭:ありがとうございます。最後に受講者の方、また首都圏人材へのメッセージを一言お願いできますでしょうか?
金子市長:今日、こんなに大勢の方々が私達の話を熱心に聞いてくださり心から感謝申し上げます。1つでも印象に残ったり興味を持っていただいて、機会があれば訪ねていただいたり、また、遠慮なくご意見もいただければ大変嬉しく思います。ありがとうございました。
宮坂社長:私はあと半年くらいで70になりますが、身体がいうことをきくうちはできる限りのことをやっていきたいと思っています。今やらなきゃいけないと思うと結構元気が出てきて、経営や新商品のアイディアがどんどん湧いてきます。そんなふうに頑張っていきますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

新潟県糸魚川市 2025年7月12日(土)〜13日(日)(1泊2日)
石井睦子さんレポート







***************************************************
事務局より:
8月の「のと熱中授業」では、まきりか先生が能登キリコ祭りを取り上げ、「祭りが、日本を救う」というテーマで講義されました。勇壮な祭りの背景にある地域としての意義や、現地の方々の復興への思いに触れることができました。近年はインバウンドの参加も増え、祭りの国際色も高まっています。
ところで9月末から10月にかけては、国際的な食文化をテーマとした祭りとして「オクトーバーフェスト」が開催されます。1810年にドイツ・ミュンヘンで始まった世界最大級のビール祭りで、現在では日本各地でも開催され、本場直輸入のビールやソーセージを楽しめるだけでなく、民族音楽や乾杯の歌に合わせて会場全体が盛り上がる雰囲気を体感できます。その魅力は単なる飲食イベントにとどまらず、文化交流の場としても大きな意義を持っていると思います。日本でも秋の風物詩として定着しつつあり、国際理解を深める架け橋となっている点は、きわめて興味深いですね。

「食熱通信第17号」発行:食の熱中小学校事務局(一般社団法人熱中学園内)
公式サイト:https://shoku-no-necchu.com/

Mail to:hello@shoku-no-necchu.com