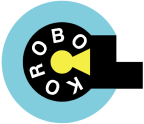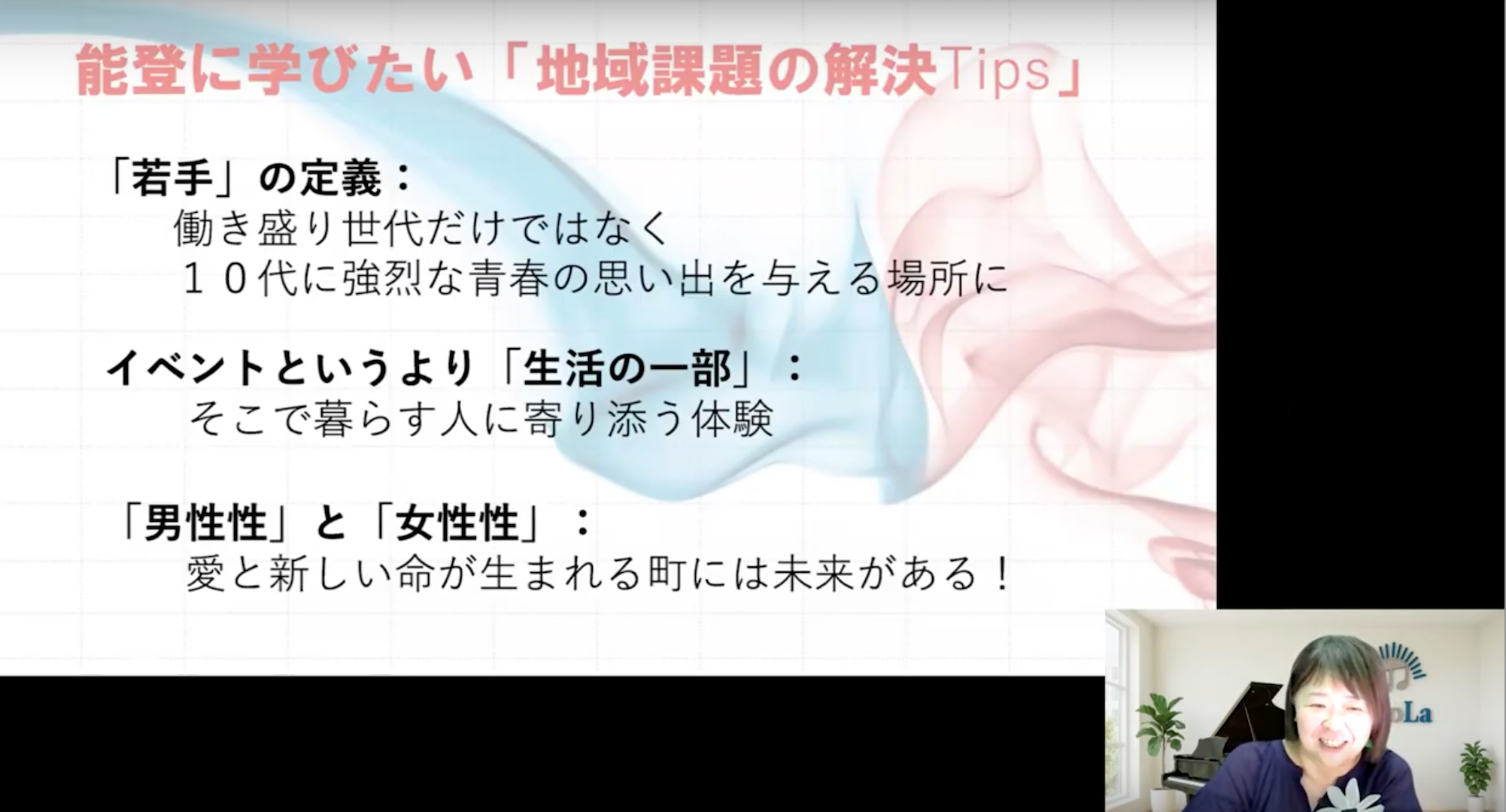皆さま、こんにちは! 能登復興支援の一環として、能登への関心を持ち続けていただくことを目的に開催されている「のと熱中授業」。その第3回が、2024年6月8日(土)に七尾市山里海里キッチンにて開催されました。今回は「花嫁のれんを料理する」をテーマに、能登の豊かな食文化や食材に触れる授業となりました。
授業には、熱中小学校教諭で料理家の山田玲子先生、能登で醤油蔵を営む鳥居醤油店の鳥居正子先生、そして七尾市でカフェ「ICOU」を経営する白藤菜都未先生にご登壇いただきました。現地からのライブ配信は、丸森熱中小学校の伊藤航さんが担当してくださいました。

能登で活躍する先生方のお話
鳥居正子先生(鳥居醤油店)
鳥居先生は、能登の地で代々続く鳥居醤油店の女将さんです。能登では、お嫁さんが家業を継ぐ風習があるそうです。鳥居醤油店は、原材料に強くこだわり、大豆は30年以上前から珠洲市の末正さんにお願いして作ってもらい小麦は隣町の中能登町のものを使うなど、「顔の見える原材料」での手作りの醤油づくりをされています。機械を一切使わず、大豆洗いからラベル貼りまで全て手作業で行われているそうです。
昨年の1月1日の地震では、お店や蔵も被災されました。壁が剥がれたり、歪んだり、仕事場が砂埃まみれになったりと、一時は醤油づくりをやめなければいけないと思ったほどの状況でした。しかし、奇跡的に桶ともろみが無事だったことから、醤油づくりを続けようと決心され、若い設計士さんの助けやクラウドファンディングでの多くの支援を得て、蔵の再建を進めていらっしゃいます。
現在は、仮設店舗でお店を開き、ホームページでのオンライン販売も行われています。
白藤菜都未先生(ICOU)
白藤先生は、七尾市でカフェ「ICOU」を経営されていました。お店の名前「ICOU」には「イコイコ」という意欲的に進む「行こう」、くつろぐ「憩う」、移り行く時間(時代)の「移行」、そして I(私)とU(あなた)をCO(つなぐ)という意味が込められているそうです。
築100年以上の古い酒蔵を家族でリノベーションした素敵なカフェでした。地元の食材を積極的に使われ、鳥居先生のお醤油やお塩、地元のお野菜やお魚などを使った綺麗なお食事を提供し、子どもたちにも人気のお店だったそうです。
しかし、ICOUもまた、昨年の地震で被災してしまいました。壁が落ち、物が散乱し、断水のため水も使えず、気力も失われるような状況だったそうです。そのような大変な状況の中でも、白藤先生は炊き出し支援を始められました。県外からの支援や、たまたま水が使えた近所のお魚屋さんから食材を得られたことで、炊き出しを継続することができたそうです。この炊き出しは半年間ほど続けられたとのことです。
現在、お店の再建に向けてクラウドファンディングや補助金申請を進めていらっしゃいます。今は食堂営業はされていませんが、お弁当やお惣菜の注文販売は続けられています。ICOUの再開に向けて、皆で応援したいですね。
山田玲子先生
山田先生は熱中小学校の家庭科の先生であり、本業は東京で活躍される料理家です。熱中小学校が始まった当初から能登との深い縁をお持ちです。かつてミラノ万博で鳥居先生にお会いしたことがあり、七尾に素晴らしい醤油屋さんがいると聞いて、いつか訪れたいと思っていたそうです。その後、高岡熱中寺子屋を通じて七尾を訪れる機会があり、鳥居先生と再会されました。震災後には、東京の料理教室で募金活動をするなど、鳥居先生を支援されてきました。 今回の授業では、能登の伝統料理にインスピレーションを得て、能登の食材を使ったオリジナルのレシピを考案してくださいました。
能登の伝統料理と山田先生考案のレシピ
授業では、能登の食文化を象徴する伝統料理と、それらをヒントにした山田先生の創作料理が紹介されました。
「ペロペロ」

白藤先生にご紹介いただいた能登の伝統料理です。だしと卵を寒天で固めた料理で、少し酸味があるように見えますが、酸味はないとのことです。お祭りなど祝いの席で食べられることが多いそうです。
「押し寿司」



こちらも白藤先生にご紹介いただきました。お祭りの時に各家庭で作られる料理で、彩りがとても綺麗です。小肌(能登では「べっと」と言うそうです)や、古代米を使った鯛のお寿司、青さ、わらびなどの山菜、干し竹、エビなど、たくさんの具材が使われます。お祭りやめでたい時の「ハレの日」のご馳走です。
「めった汁」

能登のお味噌汁です。特徴は、ちくわとさつまいもが入ること。何でも「めった」(たくさん)入れることから名付けられたという説があるそうです。冬の寒い時期に日常的に食べられる「ケの日」の汁物です。七尾はカニカマ発祥の地であり、ちくわなど練り物が多いのも特徴のひとつだそうです。鳥居先生のお母様も作られるとのこと。
「ちまき」

鳥居先生にご紹介いただきました。旧暦の節句に作られる伝統的なちまきです。山に入って笹の葉(奇数である5枚使う)や、ちまきを結ぶための紐(すげの傘のすげ)を取ってきて作るそうです。鳥居先生のお祖母様がお菓子屋さんだったこともあり、作られていたとのこと。かつては、お寺や仏壇、神棚にお供えするために作られ、その「お下がり」をいただくという意味合いもあったそうです。東京のちまきはプラスチックの笹で作られているのとは異なり、山から採ってきた自然の素材を使う、豊かな文化ですね。
山田先生考案レシピ
山田先生は、能登の伝統料理や食材からインスピレーションを得て、以下の3品を考案・紹介してくださいました。
「輝け桜貝の調べ」

志賀町(富が来ると書いて「と」と読む)の「もち麦桜貝の調べ」(そうめん)を使った一品。鳥居醤油店の出汁醤油を使った麺つゆをゼラチンで固めてジュレにし、フォークで崩すとキラキラと輝くことからこの名前をつけられたそうです。ベロベロにヒントを得たとのこと。トッピングには、能登ポーク、志賀町のサザエ、能登島の高農園さんのエディブルフラワー(食べられる花)など、能登の食材がふんだんに使われています。夏にぴったりの、見た目も華やかな料理です。
「グリーンピースのピューレ」

中能登町の稲葉農園さんの美味しいグリーンピースを使ったピューレ。茹でてピューレ状にし、サワークリームなどと混ぜてクラッカーに乗せていただきます。マメご飯などとは違う、グリーンピースの新しい楽しみ方です。
「能登ポークとバジルの魚醤炒め」
美味しい能登ポークを使い、レモン汁といしる(魚醤)でエスニック風に味付けした炒め物。高農園さんのハーブ(イタリアンパセリ、バジル、ミント)や、唐辛子、赤玉ねぎ、ネギなど、彩り豊かな野菜と共にいただきます。いしるを使うことで、魚醤の風味が加わり、普段とは違う美味しさになるそうです。
試食と参加者の声
授業の後半では、紹介された能登の伝統料理とめった汁、そして山田先生考案の料理の試食が行われました。会場では皆さんが美味しそうに召し上がり、笑顔があふれていました。オンラインで参加されている方も、山田先生のレシピや鳥居醤油店のオンラインショップの案内をご覧になっていました。

試食された参加者の方からは、以下のような感想が聞かれました。
「能登の食材を使ってこんなに素敵な料理ができるのが嬉しい。心にも効く料理だと思った」
「いしるとレモンの組み合わせが新しくて参考になった」
「能登の食材がこんなに生かされて美味しいのが感動した」
「すっごく美味しい!家で是非試してみたい」
「素材の味もすごく美味しくて感動した」
「全て美味しかったです。一つ一つが能登の食材を使っていて、すごい豊かな所に住んでいると感動した」
「初めて来たけど、こんなに地元の食材があるのを知らなかった」
「能登の美味しい食材がまた知れたのと、生かされてて参考になったし美味しかった」

鳥居先生も、ご自身の出汁醤油が山田先生の料理で「こんなに変身してくれて嬉しい」と述べられていました。
また、オンライン参加者からの質問にもお答えいただきました。お肉にかける野菜の味付け(いしる+レモン汁)や、手作り味噌の賞味期限と使い方(液状のものは醤油代わりに使える)について、山田先生や鳥居先生から丁寧な回答がありました。
授業を終えて
山田先生は、今回の授業を通して、能登の地元でお料理を作っている方々とコラボできたことがとても楽しかったし、自身も勉強になったと述べられました。また、皆さんが綺麗な料理をとても好むことが分かったので、食卓に花を添えるような料理が大切だと感じられたそうです。
「能登の未来は日本の未来」。能登の食材を華やかにすることで、日本の食卓、そして日本の未来が輝けば、というメッセージで授業を締めくくられました。能登で育まれる豊かな食材や、それを使った料理、そして何よりも能登の方々の温かい人柄や復興に向けた強い思いに触れる、素晴らしい時間となりました。
今回ご紹介した鳥居醤油店の商品は、オンラインショップでもお取り寄せ可能です。山田先生のレシピを参考に、ぜひ能登の味をご家庭でも楽しんでみてください。そして、これからも能登に心を寄せ、応援していただけたら嬉しいです。・
ありがとうございました!