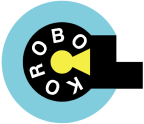先日読んだ調査によると、インバウンドの9割以上が日本の地方に行きたいと思っているのに、実際には行っていないという結果が出ていました。理由として二次交通や宿の問題もあるのですが、それ以上に大事なのが地方の楽しさがまだまだ伝わっていないということ。食の熱中小学校のツアー参加すると毎回、地方の食の豊饒さに気づかされます。特にこれからは冬の食材の美味しさが際立つ時期。ぜひ一緒に出かけ、地方の楽しさを世界に伝えましょう。
校長 柏原光太郎


座学:11月29日(水)19時 3x3LabFurture
講師:臼井壯太朗先生 株式会社臼福本店 代表取締役社長
テーマ:「海と生きるー持続可能な漁業を目指して」
私の大学時代は体育会一色で、元フェンシング日本代表にもなりました。気仙沼市の家業である株式会社臼福本店に1997年入社し現在に至っています。会社の創業は1882年、 マグロ漁業を中心にやっています。初代はマグロの問屋、2代目から漁船漁業に参画いたしました。現在気仙沼の漁業は養殖、沿岸、沖合、遠洋漁業と分かれています。養殖漁業といえば、ワカメ、牡蠣、ホタテとか。そして沿岸漁業というのは定置網であったり、川を遡上する鮭を採卵して育てたり、あとは突きん棒漁と言って魚を突いたり。沖合漁業というのは二百海里内でサンマだったり、カツオの一本釣等です。気仙沼は生鮮カツオ水揚げ日本一です。最後の二百海里の外に行く漁業ですが、遠洋マグロ漁業はこれです。マグロの獲り方はいろいろありまして、定置網を仕掛けて、そこに魚が入り込んできて、 出られなくする漁。あとは流し網、網を流してそこに刺さった魚を獲る。まき網漁業というのは、一網打尽という言葉のように一気に獲る漁です。小型から大型まで全て獲ってしまうので、いま世界的に問題にもなっています。

さて、遠洋マグロ漁船には日本人が約6、7名乗って、インドネシア人と合わせると25人くらいのチームです。 出航するときは餌をたくさん積んでいき、獲った魚と交換していくような感じになっています。操業期間が約1年、短くても10ヶ月。船の後ろから仕掛けを流します。長さが150キロです。それを仕掛けるのに1日7時間かかります。そして巻き上げに12時間。長さで言うと東京から静岡ぐらいまでになるんです。数本しかかからないこともあって非効率的ですけども、資源には優しい伝統漁業です。
さて、日本の漁業従事者が今どうなっているかといいますと、3年前の水産白書によれば水産業全体で平均年齢が56.9歳、今は59歳くらいになっているでしょう。 14歳以下の人がわずか5000人しかいません。このままいくと本当に生産者がいなくなるという状況になっています。マグロ船は世界で約1000隻。大体130隻ぐらいが日本船です。この他に国際登録する必要がない24メートルを下回る船っていう幽霊みたいな船がこのほかに世界中にたくさんいるのが現状です。

世界全体では漁業生産量がどんどん増えているにも関わらず日本だけが下がっているのが現状です。現在はピーク時の約3分の1の漁獲量です。日本の遠洋マグロ漁船というのは30年前ちょうど私が実家に帰ったあたりの頃は約1000隻いたんですけど、現在どんどんどんどん減って、130隻までになりました。日本人の魚食離れは著しく、平成22年を境に魚食と肉食が逆転しました。世界では魚食がすごく伸びてきています。シーフードを食べると身体にいいというということで日本食だけでなく魚を食べるということが世界でブームになっています。
2011年3月11日、東日本大震災でうちの会社も家も全部流されました。家族は全員無事だったのが幸いでしたが、本当に大変でした。もう震災の翌日は本当に地獄の風景でした。
でもこの震災を経験して気づいた3つの大切なことがあります。
1つ目が「エネルギーの大切さ」です。福島の問題もありましたけども電気が半月停まりました。ろうそくの灯りだけで生きてきて、久しぶりに電気が点灯して電気ってこんなに明るいんだなと、久しぶりに車に乗ったときには車ってこんなに便利なんだなと、だから、なくなってみて初めてエネルギーの大切さがわかりました。
2つ目が「食の大切さ」です。衣食住の中で着るものは数日間同じもの、住むところはテントでも体育館でも過ごしてこれました。でも、食べる物と水は、なければ人間生きていけないんだということを身をもって体験しました。食べるものというのが生きる上では一番大切なんです。
3つめは「人の繋がりの大切さ」。いろんな方々に応援いただいて、ここまで来ました。隣の家の奥さんが見つからず、3日後に見つかったときに一緒にもうほとんど喋ったことない人だったんですけど握手しながら、泣きながらよかったねっていう話をしたりとか、頑張ろうねって歩きながら知らない人と話したり、人の繋がりっていうのは本当に大切なんだなというのを感じました。生き残った私の役目とは何か、を考えたときに、この3つの大切なことをできるだけ多くの人たちに伝えることなんだというふうに思っています。
日本の漁業を今一度未来のある成長産業に生まれ変わらせたい。私が生きるも死ぬも本当に紙一重だったあの時、生き残ったというのは生かされたということを思いながら、様々な活動をさせていただいております。

さて、弊社の取り組みを3つお話しします。
1つ目が漁業を魅力的な産業へ変えるということ、2つ目は魚の資源管理です。魚を獲り過ぎて魚がいなくなってしまったら我々は商売続けていくことができません。その資源に配慮しながら、環境を壊さないように魚を獲るということ。3つ目は食の大切さを伝えるということです。
1つ目の、漁業を魅力的な産業に変えるということでは、震災後に新しい船を2隻建造しました。コンセプトは人が集まる魅力ある漁船、つまり職場です。船員にとって漁船というのは海を移動する家でもあり、できるだけ陸上にいるような暮らしやすい環境を作ってあげたいなと思いました。自分の家族、子供、親を乗せられるような、そういう船じゃなきゃだめだなと思いました。nendoという有名なデザイン会社の佐藤オオキさん、乃村工藝社のチーフデザイナーの青野恵太さんに頼んでデザインした漁船が、漁船で初めてグッドデザイン賞を受賞しました。外装は屋号をデフォルメして、船体に色を塗ったというような感じです。ハーマンミラーの椅子が入っていたり、モダンで斬新で明るい食堂、デザイン性のある船員の個室。インターネットの高速通信を入れて洋上でTV電話をしたり、船員さんたちが YouTubeを見たりニュースを見たりして情報入手や発信ができます。SNSを活用してFacebookで洋上の様子なども発信しております。洋上で暮らす船員さんたちが陸を思い浮かべてゆっくりと休んでもらいたいなと思いましてエアアロマも取り入れました。当時、コンラッドホテルのアロマデザインをやっている友人がいて、その彼女にちょっとマグロ船の魚臭い男臭い空気を変えたい、寝る時間にゆっくり故郷を思いながら安らかに寝てもらいたいなと話しましたら、クリストフ・ロダミエルさんという世界的に有名な調香師さんにお願いをしてくれて、無償で香りを作ってくれました。(ここで会場に香りを撒く)。これを船のダクトにつけて、寝る時間にタイマーをセットして拡散しています。アニメのプリキュアにも、主人公の女の子のお父さんがうちのマグロ船の船長いうことで取り上げていただきました。
2つ目が資源管理の徹底とエコラベルの取得です。世界に先駆けて、日本の遠洋マグロ漁船は資源管理を徹底しています。マグロ漁には世界に5つの会議体があります。ここに各国の水産庁の方々が1年に1回集まって科学者の人たちも来てその国が1年間取ってきた漁獲量とか魚のサイズなどを科学的に分析して、次の年の世界全体の漁獲量を決め、それを各国に配分します。うちが操業している大西洋クロマグロの総漁獲量は年間4.3万トン。そのほとんどが日本国内に輸入されており、日本の総漁獲量は全体のわずか8.7%です。日本の出漁希望船は49隻、基本漁獲枠は均等に配分します。そして農林水産大臣の方からあなたの船は 何トン釣っていいですよという指令書が届きます。弊社マグロ船では獲った魚に全て通し番号入り、QRコード付き電子チップ内蔵のタグを取り付けています。毎日何キロのマグロをどこの場所で釣ったのかということを毎日水産庁に報告します。これを報告しなければ禁固刑や罰金刑などの罰則があります。
うちは静岡県の清水港で水揚げをするんですけども、日本船の水揚げには水産庁の検査官が必ず立会い検査に来ます。先ほど言った与えられた漁獲量をオーバーしないように監視しています。
まず日本が襟を正してから海外に対して物を言いなさいと言われてそのようにしてきました。このマグロが豊洲などに並んで、しっぽを切って品質を見て、それで競り落とされてカットされてスーパーに行くわけです。私たちが行ってきた大西洋での資源管理は徹底していて、30キロ以下の小さい魚は獲ってはいけない。あと産卵時期は産卵場所では絶対に獲りません。
日本近海は、ちょうど対馬のあたりが産卵場所でたくさんの魚が集まってくるのですが、日本の大手水産会社の人達はそこでまき網で一気に獲ってしまう。国は一お咎めなし、それが非常に問題です。タグによる厳しい管理をしっかりやれば資源が回復します。大西洋はそれで一度減った資源が一気に戻った。一度減った資源が増えたというのはおそらく今の水産業でマグロだけらしいです。みんなで国際的に守ったということの結果です。そのおかげでワシントン条約の、よく言われているレッドリストですが、2022年に大西洋クロマグロは「危機」から「低懸念」に引き下げられました。アンチ魚食の影も見えるような環境保護団体の中でも堂々と話ができるようになりました。
資源管理を真面目にやってきた理由の一つが、資源管理をすれば価格も上がると水産庁から言われてきたことです。しかし我々が減量した分、ルールを守らないアジア諸国による違法漁船と漁獲量が莫大に増えてしまい、価格(浜値)は下落しました。漁獲量も価格(浜値)も下がるという苦しい環境になっているのが現実です。
その中で付加価値を求めて資源認証を取得しようと考えました。環境や資源に配慮したものであるということを示すラベル付けはヨーロッパに行くと当たり前です。魚はMSC認証が世界でNo.1の認証です。私たちは資源管理をきっちりやっているから絶対取れるという強い信念でトライして、2020年に世界で初めてMSC認証を取得しました。クロマグロはうちの会社とあとフランスの定置網の人しかまだ取れていません。なぜ認証を取ったのか。1つ目は先ほど言った、違法漁業と差別化したい。日本国内にはグレーな魚と黒い魚と白い魚が混在しています。それとしっかり差別化をしたかった。
2つ目は意見するため。こういう認証を取ったからこそ、行政に対してもサプライチェーンに対しても言いたいことを言えると思いましたし、事実、サステナブルシーフードを使いたいという人たちがたくさん出てきました。
3つ目が次の世代に繋ぐためです。次世代を担う子供たちに、私達が暮らすこの気仙沼地域には世界に誇れる食や水産業があるということを学校給食を通じて知ってもらいたいなと思いました。そこで、気仙沼の魚を学校給食に普及させる会というのを2012年に作りました。学校給食っていうのは全国の子供たちが1日1回必ず食べるものなんです。気仙沼という町にはいろいろ優れた食材があるんですが、子供たちがそれをあまり知らないんです。
学校給食週間のときに魚の西京焼が出たんです。調べたら海外で獲られているホキという魚。気仙沼には生鮮のカツオだったり、メカジキだったり、サンマだったりすごく美味しくて水揚げ日本一になっている魚も、内閣総理大臣賞を取ったような加工品もあるのに、そういうものをなぜ使わずこういう海外のものを使ってるのかなと疑問に思いました。三陸沖サンマ?という表示があったので調査したところ、日本の二百海里の外で台湾や中国の船が獲ったものだった。外国漁船が乱獲した魚を気仙沼の子供たちが食べさせられているというのはとても残念でした。本来給食というのはトレーサビリティ、誰が作ってどこで加工されて、このテーブルまで届いてるかということを知って食べるっていうこと。学童期のときからそれを考えて食べることをしていけば、大人になったときに、価値あるものに対してお金を出すことになっていくんじゃないかなと思っています。
大人になって、気仙沼には何もない、俺は都会に行くと言って東京や海外に行ったりして帰ってこない人たちがたくさんいます。ここにはこんなに誇れる食料産業があるんです。その子たちが東京や海外で学んだり働いて、鮭じゃないですけどもまた戻ってきてくれて、そして地元の食料産業を盛り上げてくれたらいいなと思っています。
インドネシアはうちの漁船の基地になっていて、毎年バリ島に船が入った時にはうちの船員さんたちの子供たちが通っている小学生や地元の水産高校生を呼んで漁船見学会などもやっています。

なぜ日本の漁業は衰退しているのか。浜値が安く、年々高騰する燃油代など経営環境は悪化する一方です。日本は、世界中から違法漁業で獲られた違法水産物や食品偽装された安い魚を大量に輸入しています。国内に入ってくる魚の24%から36%が違法漁業で獲られたという調査結果もあります。日本の大手商社や中間の流通にも問題があります。
2019年のG20で違法操業を撲滅することが決まり、欧米は率先して動きだしました。輸出入流通に漁獲証明制度が義務付けられたんです。日本も2022年に水産流通適正化法ができましたが、まだマグロは含まれていません。欧米に受け入れられないものが日本に入り、価格下落を起こしています。なぜ我が国は漁業者には厳しく取り締まって、大手サプライチェーンや商社には規制をかけないのか、憤りを感じます。世界から違法漁業を撲滅して、日本の漁業を成長産業に生まれ変わらせるためには、国内漁業者だけを厳しく取り締まるのではなく、輸入品も含めマーケット全体を見てくれないとだめなんじゃないかなと思っています。
最後に養殖の話をします。世界全体で養殖が天然を越えました。養殖は本当に環境に優しいのか?マグロというのは1キロ太らせるのに15キロの餌が必要な魚なんです。餌には天然の魚を使っています。餌も養殖しているわけではないから完全養殖ではないんです。小魚を大量に取ることによって天然の魚が減ってしまいます。養殖も悪いのではなくやりすぎてはだめだということです、漁業も養殖も同じです。
ヨーロッパでは、自分の地域や自国のものを食べれば国が豊かになるんだということを理解しています。日本は一次産業が衰退しています。ヨーロッパの一次産業が成長しているのをよく考えてみると、国境を守っているのは誰だと考えると、軍隊ではなく農家さんです。農家さんが国土を耕すイコール国を守っている、ナショナリズムを持っているし、国を挙げて一次産業を大切にしてるんです。世界中のどこを見ても地方の基幹産業は一次産業なんです。日本はちなみに、日本の国境を守ってきたのは誰かと言ったら、海を職場にしている全国の沿岸漁業者さんたちです。
日本の地方を活性化させるためには、地方の基幹産業である一次産業を活性化させなければ駄目だと思っています。これから起きる食料問題、食料や資源確保の闘いが始まっています。異常気象で作物が獲れなくなる。みんなそれが当たり前になっていきます。資源の奪い合いが起き、国境を越えて取引される食糧というのがどんどんどんどん減るはずです。そんな中で、こんな今の状態でいいのかなと私は思っています。日本の漁業を、もう一度世界で闘える産業にするために、我々も一生懸命これからも頑張っていきたいと思います。これからも皆さん応援のほど、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。











*********************************************
事務局より:
2024年もあと少し。皆さんにとってどのような1年だったでしょうか。能登を襲った巨大地震と水害により多くの方々が被災されました。そして1年が経とうとしている今もなお、厳しい毎日を過ごされていらっしゃいます。個人として、そしてコミュニティとして、今できることは直ぐに実行しなくては・・と思います。一方で大谷選手の大記録達成、パリ五輪での日本人の活躍などに拍手を送る自分もいました。町中華で舌鼓を打ちながら、TVで選挙速報など観てたりします。悲喜こもごも。来年は良い年にしたいですね。

「熱中通信第9号」発行:食の熱中小学校事務局(一般社団法人熱中学園内)
公式サイト:https://shoku-no-necchu.com/
Mail to:hello@shoku-no-necchu.com