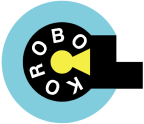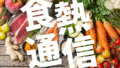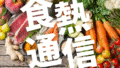【今月の特報】
①第5期生徒募集開始!!
-サスティナブルな学校へ・各プログラム同士のクロッシング企画もー
申し込みサイト https://shoku-no-necchu-5.peatix.com/
募集要項 https://shoku-no-necchu.com/application/
第5期 講師紹介&スケジュール https://shoku-no-necchu.com/schedule-term5/

②初の海外開催!米国シアトルで食の日米交流会とワイナリー&創作アメリカ料理を味わう旅
2025年10月16日(木)〜19日(日) 3泊4日 シアトル熱中小学校 7周年記念イベント
詳細とお申込みは下記から。定員13名、お早めに! (5期の生徒様のプログラムになります)


**************************************************************************
数えてみると昨年、私は年間127日地方に行っていました。 3日に1日くらいです。今日も別府から帰ってきたところです。
食の熱中小学校校長に就任して2年ほどですが、それまではいまほど地方に興味があったわけではありません。しかし食熱の座学とツアーに参加してからというもの、地方の食の面白さにハマっています。
ここ2年を振り返っても、地方の友人が誘ってくれたり、仕事だったり、地方を訪れた時の気づきはさまざまでしたが、食熱のツアーはひと味違います。首長をはじめとして、その地方に精通している人々がその土地の食文化の面白さを徹底的に教えてくれるのです。大手の旅行会社のツアーではけっしてできないことです。
第4期も折り返し地点を過ぎ、いまは第5期のプログラムを考えているところです。掛け値なしにいいますが、第5期の座学もツアーもとても面白いです。私が会いたかった先生の授業や、行ってみたいツアーを具現化しています。秋以降、またみなさんとお目にかかれることを楽しみにしています。
校長 柏原光太郎 一般社団法人日本ガストロノミー協会会長


座学:6月25日(水)18時30分 ユビキタス協創広場CANVAS
講 師:小野愛美先生 (合同会社Maternal代表社員/フードプロデューサー)
テーマ: 「地方美食都市戦略」 〜私たちの10年の場合〜
山形県鶴岡市から参りました合同会社Maternal代表の小野と申します。今日は鶴岡市のこれまで歩んできた10年についてお話したいと思います。

山形県は米どころで米の生産量全国第4位です。いろいろな種類のお米を生産していて、中でもコシヒカリとかそうしたお米の親品種となる亀の尾というお米を開発した方は庄内の方です。庄内地方は今、稲が青々としている時で、平野がきれいに水を張って本当に美しい風景が広がっています。私は山形県の生まれで、子供の頃自然が身近でした。両親は公務員で、2人の叔父がそれぞれ専業農家と専業の漁師だったことが今の私に影響しています。20代の頃は、ブライダル業でウェディングプランナーをやっていました。食の業界に入るきっかけとなったのが、今から25年ぐらい前の時、この地域ってほとんどの人が兼業農家や何かしらのものを生産しているにも関わらず、この人生最良の結婚式の日にそれらの食材が使えないのはなぜだろうと思ったのが始まりました。何とかこの地域の食材だけで婚礼料理が作れないものかといろいろな生産者さんのところを回り、その結果ほぼ100%地元産で婚礼料理を作ることができ、それを売りとするホテルウェディング結婚式となりました。その活動を見ていた方が、やっている仕事は同じだから日本料理店をやらないかと誘われ、そこから料理業界に転向いたしました。この日本料理店が、鶴岡市にある日本料理店でした。その頃ちょうど鶴岡市はユネスコ食文化創造都市に認定されるための活動をスタートさせたところでした。私は、飲食店側として、鶴岡市が認定活動として行っている活動をしながら、4年間の女将業をさせていただいた後、山形大学農学部で在来作物の生涯学習講座というのが立ち上がっており、そこでコーディネーターとして1年間勤務させていただきました。この年の12月に鶴岡市はユネスコ食文化都市に加盟することができまして、その翌年からは、鶴岡食文化創造都市推進協議会という鶴岡市の外郭団体において、ユネスコ関連の食文化推進事業を行う事業推進員として7年間お仕事をさせていただきました。こうしたバックボーンを持って料理人の高度育成と生産者との連携構築ということを軸に仕事させていただいてきました。ただ行政と仕事をしていくと、縦割りの中、それは観光だ、それは農政だ、水産だ、学校教育だ、とたらい回しにされて、食というのは本来すべてつながっているのに思うように事業が進められないジレンマに陥りまして、それで心機一転、退職して現在の会社を設立したというのが現在に至るプロフィールでございます。

鶴岡市は2014年に食文化創造都市としてユネスコ創造都市ネットワークに日本で初めて認定されました。現在認定された都市は、世界で56市、日本では鶴岡市と大分県臼杵市の2つです。1400年前に開山した出羽三山、養蚕から絹織物までを現在も行っている唯一の地としてのシルク産業、そして北前船の寄港地として栄えたこと、この3つを日本遺産として特色のあるまち創りを行っています。具体的には、最先端のバイオサイエンスを核とした未来創造田園都市サイエンスパーク。その中に建っているスイデンテラスというホテルに、今回9月のツアーではご宿泊になられるかと思います。また国宝の五重塔もある出羽三山の羽黒山で提供される精進料理、養蚕場、北前船の寄港地として認定されている加茂の地域にあるクラゲ水族館、この4つが鶴岡の特色ある都市作りの核となっているものです。
市町村合併で鶴岡市になり、2009年にまち作りの柱として鶴岡ルネサンス宣言というものを発表したのが食文化創造都市を目指したきっかけでした。創造文化都市、観光文化都市、学術文化都市、安心文化都市、森林文化都市という5つのまち作りを推進するということを行政が打ち出し、そのうち創造文化都市部門における象徴的な取り組みとしてユネスコ創造都市ネットワークへの加盟につき全市を挙げて推進してきたのです。認定されたポイントは4つあります。1つ目は、各家庭に受け継がれる行事食や郷土料理。鶴岡市で生まれ育った小説家の藤沢周平先生の作品に出てくるような料理は今でも家庭に受け継がれ食べられていて、食材の保存や山菜などの灰汁抜き、塩蔵など、食材をどう食べるか、またどう冬へと食を繋いでいくかの食べるための知恵が認められたと思っております。2つ目は、精神文化と密接に関わる特有の食文化です。出羽三山に伝わる精進料理は皆さんの考える精進料理とは違って、山の恵みをすべて身体に取り入れることを修行のひとつと考える「山伏精進」と呼ばれるものです。お膳の上に並ぶタケノコやシイタケ、厚揚げなど、これらは明日から修行に廻る地域の隠語になっていて、修行の道標を意味していたりします。山の物をいかに美味しく食べるか、本来食べられなさそうなものでも知恵を使ってすべて食べるように努めました。3つ目は600年もの歴史がある黒川能という能があります。この能は豆腐祭とも呼ばれ、1月31日から2月1日にかけて夜通し踊り続けるのですが、見に来る人々に豆腐焼きという、焼いた豆腐を山椒の汁に浸したものを振るまうのです。神社に奉納する能の舞ということで、精神文化と結びついた特有の食文化となっています。また、生きた文化財といえる在来作物が60種現存しています。すべて種取りをして作物として作り繋いでいますので、種の多様性という意味で認められたのだと思います。9月のツアーでは、宝谷かぶという、焼畑で作られるカブの収穫、間引きを予定しているようですのでぜひ楽しみにしていてください。4つ目は、サイエンスパークの中には慶應義塾大学の先端生命科学研究所があり、更には山形大学農学部、そのほか鶴岡高専があり、鶴岡の食文化を受け継ぐだけではなく数値化や可視化し、新たな創造クリエイティブに繋いでいく、そうしたしっかりした高等教育機関間の横のネットワークがある点も認められたと言えます。


鶴岡の食文化を育んだ背景としては出羽三山の影響がとても大きいです。山伏が伝えた山伏精進。それから昔、西のお伊勢参り、東の奥参りと言われ、西のお伊勢様は天照大神を祀る太陽、陽の方、奥参りと称される出羽三山の方は月の神様、月読命という神様で2つは対と考えられ、一生に一度、対を詣でたいというのが昔の人の信仰でした。日本全国各地から参拝者が徒歩で来ては食事代や泊めてもらうお礼として自分の地域の優れた種、貨幣価値に等しかったその種を置いていったことでいろいろな地域の種がやってきたそうです。また、江戸政府は朱子学を推していた中で庄内藩は自己主体性を重んじる徂徠学を推進してきた。それによって積極的な育種化が育まれました。それから北前船が運んだ京文化。紅花は山を一つ挟んだ山形の方で作られていて最上川を下って酒田港まで来て酒田港で米と紅花を積んでいきました。逆にそこで積荷を降ろしていったので庄内には京文化が根付いていて、庄内だけがお雑煮も丸餅で食べるといった特有の文化があります。北前船によって持ち込まれたと考えられる在来作物に繋がる種に孟宗竹があります。孟宗竹最北の地と言われています。これらがどうして外に流出しなかったのか、またなくならなかったのかというと、やはり冬閉ざされる環境の影響がとても大きいと思います。 このような背景があり長きに渡って育まれてきた文化が世界に認められたのはすごく誇らしいことで、鶴岡市は認定を受けて鶴岡市食文化創造都市推進プランを掲げました。食の理想郷を基本理念として、3つの基本目標を掲げました。1つは食文化の伝承・創造とともに歩む産業振興、2つ目は食文化を生かした交流人口の拡大、3つ目は食文化による地域作りです。私たち鶴岡食文化創造都市推進協議会の事業推進員がこの基本目標を達成するための事業に乗り出したのが平成27年でした。実際に行なった1つが、食文化を生かした交流人口の拡大に向けた、鶴岡ふうどガイドの育成とガイドによるツアーの造成です。これは無償の観光ガイドではなくて、有償で、かつ観光地ではなく生産者さんや食の現場を体験してもらうのを特色としたツアーになっていて、認定前、もう15年近く前からスタートしています。食のイベント開催ということでは一番大きいのが酒蔵さんを一堂に集めた庄内酒祭りを開催しています。酒蔵さんたちの造りがそれぞれで考え方も違うので、どこが自分に合うかなと思いながら巡っていただくととてもわくわくするかと思います。食文化による地域づくりに関しては「つるおかおうち御膳」という冊子を発行したり、子供たちに向けては食文化の授業や、鶴岡市は学校給食発祥の地と言われていますので学校給食を通した取り組みですとか、あとは市民向けの講座の開催や生産者さんや醸造家さんといった食文化を紡ぐ人々を取材した冊子をまとめたりとか、都市間連携の推進ということで、地域の中でもユネスコ食文化創造都市に認定されたことを市民の方々にもちゃんと落とし込んでいこうという取り組みが3つ目の基本目標です。この食文化の伝承・創造とともに歩む産業振興は私が推進役でしたので少し詳しくお話ししますと、まず1つ目に、料理人と生産者の連携構築ということで、地場産の食材の生産、生育環境を知り理解を深めるためのフィールド学習を料理人に対して行ってきました。2つ目は、料理スキルと意識を上げるための研修会の企画運営ということで、地域の食材と食文化の価値を高める料理として、技術だけではなく論理的な解釈や方法論なども含めて、食文化創造アカデミーというものを創設しました。これが本当に豪華な講師陣の皆様にお手伝いをいただきまして、1年全部で12回の講座を料理人に向けて開催しました。そしてその実施を受けてのアウトプットと研鑽の場としての料理人大会を過去3回実施しました。鶴岡市のような市町村単位で料理人のコンペティションを行うのはすごく異例なことだと思います。ユネスコ認定後、昨年鶴岡市は10年を迎えました。10年前当時はまだ行政でガストロノミーの推進に取り組んでいるところはまだまだ少ない現状でした。そこで私は、平成28年に新市長に対して自治体が料理人を育成すべきだというプレゼンテーションをさせていただきました。自治体は食を基軸とする地域ブランディングをし、飲食店の皆さんには国内外の観光誘客の飲食の受け皿として頑張ってもらいたいという思いがありました。弱体化する1次産業の支えの一手である生産物を消費の形として表現できるのは料理人だけでありこれを体現し得るのが料理です。その土地に行かなくても取り寄せられる特産品ではなくて料理人が人を呼ぶ時代。料理でその地域の魅力を発信できる力のある料理人を育成する必要があるんですよとお話ししました。そしてこのときすでに全国に先駆けてそれを確立していたのが奥田シェフなのだから、この地域はそのようにやるべきだと。これらを踏まえて、今後のビジョンをどのように形成していくか。鶴岡の食を牽引しているのは間違いなくアル・ケッチァーノの奥田シェフです。奥田シェフをフロントランナーとして鶴岡は次の世代が続々と地産地消シェフとして活躍しているというイメージを発信し、地域イメージをこのカラーにしていこうと。当時からアル・ケッチァーノは日帰りで来られました。日帰りではアル・ケッチァーノにしかお金が落ちない。1泊してもらえれば、夜はアル・ケッチァーノで次の日のお昼もあるし宿泊も含まれてきます。お土産も買うでしょう。それが2泊になったらもう夢のようで何食も食べてもらえますので、目指したのは2泊してもらえる地域を作ることでした。食文化創造都市鶴岡のブランディングにするには、料理人が地元食材をちゃんと理解している、そして地元の食材を地元のレストランが積極的かつ創造的に活用している。そして先進的なスキル向上の学びに取り組んでいるということを描きました。ネットワークの掛け算をしていくことで未来の人材育成をしていきましょうというのがこのプロジェクトのキーワードでした。

まず導入期、食文化創造都市に認定されて1年目の平成27年度は、食文化創造都市が何なのかを誰も知りませんでした。 1年目は、生産者の方や町場のレストランや宿泊施設の調理場、そういったすべてのところに対し食文化創造都市になったことの認識の普及と、それに伴って自分たちが求められることに応えていかなければならないという意識の向上をひたすらやっていました。現在その私のチームは料理人と生産者の方で90人ぐらいになっています。2年目は、生産者を含む料理人の会の組織立てをして、団体として運営できる力を育むこと。奥田さんの次の代のリーダーをこの中から育成したいという思いがありました。あとはこの会が出来上がったら、他の団体や横の繋がりを作っていって食のおもてなし都市として共通の認識を持ってスキル向上に努めていくような体制を作る取り組みをしました。3年目には、実際に食文化創造アカデミーというものを立ち上げ、これらによって、鶴岡の食に関わり食を生業とする方々が主体的にネットワーク体制を確立して、団体組織が市など他の団体からの要請を受け入れて実行する窓口になるようにする。またこれによって、各自の分野に派生して、新産業とか新商品の開発、農商工間の連携、食を取り巻く活動が自主的に発展する環境ワークを促すのを目標としてやっておりました。都市間の総合的料理人交流による美術や文化の往来によるスキル向上と都市イメージの発信ということでは、世界中のユネスコ創造都市から日本人の料理人を派遣してくれという派遣依頼がすごくたくさん来て鶴岡市の料理人たちはもう10カ国以上の年に海外派遣をさせていただいております。また海外、ビルバオの料理人をこちらに招いて1週間ぐらい市内で研修していただくといった海外との交流も現在もやっていますし、こうして4年目ぐらいから食を生業とする人たちの総合的なネットワークが機能する環境になり、その人たちが次の世代の人材育成をする環境を整備して次世代のシェフを育成する、子供たちに料理の素晴らしさを教えるといったことが、きっとこの料理人、生産者の方々のネットワークの中でできるようになるでしょう。だから、導入期があるけれどちゃんと成長期もあって成熟して、行政はそれを刈り取ることができますから今ここにお金を投じてくださいというお話をしたわけです。

実際これらの実現のために行ってきた一例が、フィールド学習です。料理人の人たちは漁業体験もたくさんしています。たとえば神経締めの違いによる身質の違い、神経締めをしたものか野締めにしたものかとか、あとは背側か腹側かとか、そういったすごく細かい部分までの食味体験も通して漁業の現場を学んでいます。底引き網漁に入ってくる今話題の低未利用魚、あまり食べる文化のない魚ですがこれをどう美味しく食べるかということで、料理人の人たちが作って漁師さんを招待して食べてもらい美味しい料理になりますよと知っていただいたり、あとは在来作物の生産現場にも足を運んで、どんな生産環境で種取りをして栽培されているのかを学んだり。畜産と農業の循環をアップサイクルして確立している生産者さんがいらっしゃるので、そこへ行って堆肥作りとかそれを使ってどういうものを生産しているのかを学んだりもしています。また私たちは、稚魚を育てて海に放流する栽培漁業というのを事業で行っていますが、この栽培漁業の現場を学ぶようなことから、この社会において持続可能な食のあり方を作っていくには自分たちはどんな役割を担うべきか、といったこともフィールド学習で学んでいます。食文化創造アカデミーのカリキュラムの一つ、料理の研修なのですけれども、ガストロノミーを構成する料理技術や文化芸術、郷土学科学農学などを基本として高度な感性を持つ次世代の料理人を育成し、料理を通して食文化を発信できる力のある料理人を育成するための、外部からプロの料理人を招聘したプログラムになっています。令和2年度からはそれに加えて、サステナビリティですとか持続可能な食のあり方などの要素を加えて実施してまいりました。こうした国内トップシェフたちによるセミナーを、平成29年から5年間、年間8講座を実施してまいりました。全国各地の料理や発酵などのプロをお招きし授業をしていただいています。その他、創造実習ということで、先生を呼んでの実習だけではなく、参加しているいろいろジャンルの異なる料理人同士がグループとなって、こちらで出す一つのテーマに対して料理を創造的に作っていくという実習も行いました。こうしたセミナーに出ることで横の繋がりも縦の繋がりもできて、料理人の方々はここ10年本当に一生懸命学んだことで、現在の鶴岡があるというふうに思っています。これらのアウトプットとして料理人のコンペティションの開催をしてきました。1回目の大会が2019年、「通常提供できる【鶴岡】を表現した新メニュー」がこの大会のテーマでした。2年後 の2021年は、コロナ真っ只中でしたが何としてもやるということで「鶴岡ガストロノミーをテーマとした新レシピの考案」をテーマに実施しました。2023年大会に関しては、鶴岡が食文化創造都市認定10年を迎えるpre-yearの年の開催でしたので、「郷土料理の再構築または在来作物の可能性の探求」をテーマとし、これまで郷土食を紡いできてくださった方々や在来作物の生産者の方々にスポットを当てて改めて感謝する大会にしようということで、チームでエントリーするようにさせていただきました。そして今年は、テーマはウェルビーイングにしました。現在絶賛募集中です。昨年10周年を迎えこれから次の10年を見据えないといけないときに来ており、食の業界がこれから確実に見据えていくべきなのはウェルビーイングだと思い「ウェルビーイング ~鶴岡から未来に向けた最高の一皿~」とのを今回の大会テーマにさせていただきました。また今回初めてエントリー対象を鶴岡市内から山形県内全域まで広げました。合わせて、これからの未来を作るということで、25歳以下の学生枠というのも今回追加で作りました。ウェルビーイングを解釈していくと、健康に配慮した食事、ということで、皆さんコロナを経て、食で免疫力を高めるとか、薬膳とか腸活とか、健康と食はすごく関わりが深いということを一般の方もすごく感じてらっしゃると思います。健康に配慮した食事と、あとは地球環境に配慮した食事、そしてアレルギーや嚥下食などの障害、またビーガンやハラールといった食の嗜好性などのよりパーソナライズされた食事、大体この3つに分けられるのかなと思うんですけれども、いろんな角度から食とウェルビーイングというものを表現、提案してもらおうというのが今年の大会のテーマになっています。最終選考会が11月25日で、審査員も本当によくこんな方々が来てくださるなというような豪華な審査員の方々にお越しいただく大会となっております。募集はこれからですが実は一般観覧もありますので、スケジュールの都合のつく方はぜひ鶴岡に大会を見に来ていただけたらなと思います。
こういったことをやってきて料理人はどう変わったか、果たして先ほどの計画通りにいったのか。料理人の方々、計画以上のことを今やってくださっています。料理人主体の料理人による社会活動の一例としては、水産業界において地魚の高付加価値化に向けた取り組みを漁師さんや水産関係の方々と連携して行っています。また、料理人の方々が小学校に授業に行ってくださったり、高校生に対して、自分たちの地域の食材をプロが料理するとこんなに美味しいんだよというお弁当を作って、自分たちの地域を誇りに思いなさいという授業をやったり、また、フルーツ王国の鶴岡が2021年にリンゴや梨などのフルーツが雹被害を受けて出荷できない状態になってしまいまして、廃棄するにもお金がかかるしどうしようとなった時、立ち上がったのが料理人の方々でした。櫛引地域の飲食店を含む23店舗が、雹がぶつかったところをえくぼに例えた「くしびき☆えくぼフルーツフェア」というのを開催し、それらのフルーツを買い取ってくださいました。また「Give me Vegetable」といった食を通じてサステナビリティを定義するイベントも開催して、10人ぐらいの料理人たちが皆自分の店を休んでサステナビリティに対する意思表示のイベントをやってくださったりしています。他にも嚥下障害に対する食の分野なども発展していて、本当に社会活動をよくやってくださっています。その中でも一番大きいのが「サスティナ鶴岡」という、料理人と生産者による食育食農団体があります。料理人コンペティションの第1回目のグランプリを受賞した齋藤翔太という料理人が呼びかけをして、周囲の料理人、生産者が皆一緒になって立ち上がって、2021年2月にこの団体を立ち上げてちょうど活動5年目になりました。これが昨年、農林水産省主催の食育活動表彰の農林漁業者の部で農林水産大臣賞を受賞しました。2025年現在、メンバーの登録者数は料理人が50人、そして生産者が農家漁師含めて35名、そして一般のサポートスタッフの方が50名っていうことで大学生、高校生含めサポートスタッフがおりますけれども、全部で今135名の大所帯となっています。私も独立後こちらの事務局長をさせていただいており現在この運営を担当しているのですが、鶴岡トップクラスの料理人の方々がひと月に2回のペースで食育事業や食農事業を実施しています。
このコミュニティのいいところは、これからその食産業を目指したい大学生や起業したい人、UIターンで飲食店を開きたいといった方々が初めてこの地域と繋がる場としてこの団体を利活用してくださっています。これだけの人数がいるのですごくみんなワイワイとやって、ここで繋がった新しいこのコネクションがまた次の新たな企画をどんどん生んでいく。そういった意味で今本当に料理人が中心となって活発にいろいろな事業が展開されているなと感じています。そうしてユネスコ認定から10年目たった昨年には美食都市アワードを受賞し、評価をいただいています。

このように私達の10年は、ユネスコって何なの?というところからスタートして、10年でやっとここまで参りました。ただ、これからの課題と展望ということで、まだまだ課題はあります。1つは実態の可視化と情報発信です。地方ってすごく発信が下手なんです。本当に素晴らしいことをやっていますし各レストランの地産率を出したらすごく高いのに、それらを数値化や言語化して可視化しするといった点がまだまだできていないなと感じています。それができてくれば、それぞれの個の磨き上げがよりブラッシュアップされて、もっともっとたくさんの方に、日帰り旅行だったのが2泊泊まって5食食べて、どこへ行っても美味しかったと言っていただける街作りになっていくのかなというふうに思っています。
私のこれからの展望はやはりウェルビーイングです。サイエンスパークでは食品を分析して数値化することが可能な施設があったり、この4月には日本初の検便施設もできました。鶴岡のこれからの10年そして未来は、サイエンスと食の融合によるウェルビーイングという高みを目指して独自の路線を進んでいくと考えています。
私の課題は、1番に1次産業の衰退と高齢化です。山形県の漁業者は今250人ぐらいしかいません。また就労・就農していらっしゃる農家さんも65歳以上が7割ぐらいになってきています。あとは、やはり地域全体の高齢化と若者の流出。こうしたすべての課題に対し、食と料理というものは一助となり解決に近いことができるのではないかと考えております。食の力でこの地域の課題解決に導きたいというのが、私のやりたいことです。そのためには、本当に消費いただく皆様の応援が何よりの励ましとなります。9月のツアーはぜひ楽しみにして、ぜひとも良いコメントをお待ちしております。ここまでご清聴ありがとうございました。

福井県坂井市丸岡町竹田地区「山人が創る豊穣のめぐみに出会う旅」(2025年6月21日~22日実施)
黛 哲也さんレポート
















***************************************************
事務局より:
話題の映画『国宝』を観ました。感想はいろいろありますが、特に「人間国宝」という存在そのものに改めて興味を抱き、調べてみたところ、それが「重要無形文化財の保持者」の通称であることがわかりました。さらに調べると、保持者への助成金は国家予算で定められているため、生存する保持者の数には上限があるそうです。また、対象となる分野は「芸能」と「工芸技術」に加え、新たに「生活文化」の分野でも基準を設けて認定できるように告示が改正され、2026年度からは「食の至宝」として顕彰が始まる予定とのこと。「料理人」や「杜氏」などで、どのような方々が新たに“国宝”として選ばれるのか、今から楽しみです。

「食熱通信第16号」発行:食の熱中小学校事務局(一般社団法人熱中学園内)
公式サイト:https://shoku-no-necchu.com/
Mail to:hello@shoku-no-necchu.com